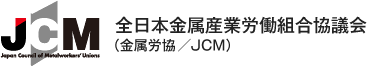1.はじめに
金属産業は日本の基幹産業であり、金属労協としてもその自覚のもとに役割と責任を果たすべく活動してきた。今後も金属産業にはわが国の成長を牽引していくことが期待されており、私たちは金属産業の発展に資する労働運動を展開していかなければならない。
具体的には、金属産業がグローバル競争を勝ち抜くための競争力強化に資する産業政策の推進、あわせて金属産業で働く者への「人への投資」を通じ、雇用と生活の安定、労働条件の向上を図ることにより良質な雇用の確立に継続して取り組む。
ものづくりのグローバル化に伴い、インダストリオールを通じたグローバルな視点での労働運動の強化が必要となっている。ポピュリズム・権威主義の台頭により、分断や戦争の脅威の拡大が顕著となる中、労働者の団結権、団体交渉権、ストライキ権といった労働基本権が多くの国で脅かされている。
このような分断された状況を打破するためには、インダストリオールを中心とした国際労働運動をさらに強化していく必要がある。
私たち金属労協は、インダストリオールの中核組織として、また、アジア太平洋地域を代表する組織として、これからも世界の労働組合との連帯を強め、わが国はもちろん、世界各国で働く労働者のそしてそれぞれの国の発展に向けて、その役割と責任を果たしていかなければならない。
「円安・スイスフラン高」に端を発し、近年、金属労協の財政は単年度赤字が常態化している。この間、経費削減、各種活動の効率化、予算の効率的な執行、財政基金積立金の取り崩しなどにより活動を維持している状況にある。2025年度はインダストリオール会費登録人員の見直しに関するインダストリオール本部との調整を行うとともに、2025年11月に開催される第4回世界大会(オーストラリア・シドニー)での為替激変緩和措置に関する規約改正を実現すべく準備を進めてきた。引き続き、インダストリオール・グローバルユニオン日本加盟組織協議会(以下、インダストリオール日本加盟協)と連携し規約改正を実現していく。
金属労協の持続可能な財政運営に向けて、2024-2025年の2年間にわたり、組織改革推進会議を中心に議論を行い、本定期大会の独立議案として提起した。本議案は産別の負担増につながることから、引き続き各種活動の効率化、さらなる経費削減、インダストリオール本部への働きかけを行っていく。
新しい金属労協のあるべき姿を目指した活動については、連合の2024-2025年度運動方針の中で、組織体制についても検証し必要に応じて見直すことが提起された。
この間、連合と金属労協との組織体制のあり方に関し、連合担当部局との意見交換を行い、特に金属産業政策の実現に向け、いかにして連合の政策活動と連携させていくのかという視点で検討を行ってきたが、現時点で具体案を提起するには至っていないことから、引き続き連合との連携を深めていくこととする。
なお、2026-2027年度の運動方針の策定にあたっては、今後の連合との「組織のあり方」の進捗状況を視野に入れつつ、現行の組織体制をベースとして策定することとする。
2.基本的な考え方
<国際労働運動>
- 国際連帯の重要性が増す中にあって、ドイツ、北欧、韓国、アジア太平洋地域の組織との緊密な連携を図るとともに、インダストリオールの活動における金属労協のプレゼンス向上に向けて取り組む。
- 国内外を問わず、サプライチェーン全体で人権を遵守することが企業に求められている。金属労協として、企業の人権デュー・ディリジェンスへの労働組合の参画を推進する。併せて政策対応などにも取り組む。
- 日系企業の海外事業体における労使紛争がアジア地域を中心に依然として発生している。金属労協として、当該地域のインダストリオール加盟組織からの紛争解決に向けた支援要請を受けており、その解決に向けてインダストリオール本部、地域事務所、当該産別・労連・単組と連携を図る中で解決に努める。
- 国内外における労使を対象とした建設的な労使関係構築に向けた取り組みを継続することにより、労使双方の信頼関係を深めるとともに建設的な労使関係の構築に繋げていく。なお、海外における建設的な労使関係構築の観点から、タイならびにインドネシアにおいて現地労使ワークショップを実施してきたが、今期は効果を検証し、今後の運営や実施方法について見直し・調整を図る。
<多様性の推進に向けた取り組み>
- 男女共同参画を一層推進するため、第4次「男女共同参画推進中期目標・行動計画」に沿って活動してきた。引き続き男女共同参画推進連絡会議を中心に産別横断的な取り組みとできるよう対応していく。なお、第4次「男女共同参画推進中期目標・行動計画」は2026年8月が期限であることから、2026年度中に次期目標・計画を定めることとする。
- インダストリオール台において活動の強化が図られている若年層の労働運動への参画については、産別・単組における取り組みを踏まえ、金属労協における運動のあり方について検討ならびに対応を図っていく。
<人材育成>
- 労働組合の最大の武器は「人」であり、次代の労働運動を担う組合役員の育成は重要課題の一つである。労働リーダーシップコースの実施にあたっては、講師と連携し時代のニーズに合ったプログラムへの改善と内容の充実を図る。
- 産別横断的なネットワークを活かした産別・単組役職員の知見を拡げる勉強会の開催や、スキルアップに資する専門的な課題ごとのセミナー等を開催する。なお、実施に当たってはWebも活用しながら、誰もが参加しやすい取り組みとしていく。
- 企業活動のグローバル化に伴い、労働組合としてもグローバルな視野での労働運動を推進できる人材が求められていることから、国際労働研修プログラムを通じた人材育成に努める。
<金属産業政策>
- 現在ものづくり産業は、国家間の戦争などにより激変し続けている国際情勢や脅かされる自由貿易、AIなどの技術革新により岐路に立たされている。こうした中でも賃上げをはじめとした労働条件の向上を継続し続けるためには、どんな困難にも打ち克つ強固な現場・強固な金属産業・強固な日本経済の形成を強靭な産業政策によって実現する必要がある。
- 産業の競争力強化に向け、「民間産業に働く者の観点」、「グローバル産業であり、かつわが国の基幹産業であるものづくり産業に働く者の観点」、「金属産業に働く者の観点」に立ち、金属産業政策を策定するとともに、実現に向けて積極的な要請活動などを展開する。
<金属共闘>
- 2025年闘争はJC共闘により、組合員の生活を守るとともに、日本経済の好循環に資する観点からも、労使の社会的責任を果たすことができたと考える。
- 金属労協はこれまでも賃金・労働条件の向上と企業の持続的発展の実現のために、産業を支える「人への投資」の重要性を訴え、JC共闘を進めてきた。
- 次年度以降の闘争においても、この基本的な考え方をベースとしつつ、金属産業の魅力の向上と日本の基幹産業である金属産業にふさわしい賃金水準の確立に向け、闘争のけん引役を果たすべく取り組む。
<地方活動の展開>
- 金属産業の持続的発展のためには、生活拠点が実際に存在し、組合員の生活の場でもある地域の活性化を促すことが重要であることから、引き続き、地方ブロックおよび都道府県単位での活動を支援していく。
<新しい金属労協のあるべき姿>
- 「新しい金属労協のあるべき姿」の具体化に向け、引き続き、連合との議論を行う中で前進を図っていく。
<財政>
- 新しい金属労協のあるべき姿を視野に入れつつも、連合との調整には一定程度期間を要することが見込まれることから、2026年度についても、活動の効率化、予算の効率的な執行、財政基金積立金からの一般会計繰り入れにより活動を継続する。
- 2027年度以降については、今定期大会で提起する施策に基づき金属労協を運営していくことになるが、引き続き組織改革推進会議を中心に、各種活動の効率化、さらなる経費削減などに関する検討ならびに実施に努める。
- 2025年インダストリオール世界大会における規約改定(為替変動に対するインダストリオール会費激変緩和措置)を実現するとともに、引き続きインダストリオール本部に対し、会費のあり方、効率的運営、効果的な運動推進などを求めていく。
3.運動をとりまく情勢
3.1 国内情勢
(1)経済情勢
 2024年度のわが国の実質GDP成長率は0.8%となった。足元では、内需は緩やかな成長を維持する一方、輸出の減少により外需が足踏みしている。2025年度の成長率予測は、1月時点の政府見通しは1.2%、4月時点の日銀見通しは0.5%、7月時点の民間調査機関の予測の平均は0.5%となっている。
2024年度のわが国の実質GDP成長率は0.8%となった。足元では、内需は緩やかな成長を維持する一方、輸出の減少により外需が足踏みしている。2025年度の成長率予測は、1月時点の政府見通しは1.2%、4月時点の日銀見通しは0.5%、7月時点の民間調査機関の予測の平均は0.5%となっている。
鉱工業出荷は横ばいで推移しており、数量ベースでは米国の関税政策の影響は明確に表れていない。設備投資の先行指標である機械受注統計(船舶・電力を除く民需)は持ち直しの動きが見られる。
経済活動の動向を敏感に観察できる人々に対するアンケート調査である「景気ウォッチャー調査」は、好不況の境目の50を下回って推移している。
輸出金額は、足元では米国向けで大幅な減少が見られる。アジア向けは増加する一方、中国向けは減少傾向が続いている。
消費者物価上昇率(総合)は、コメをはじめとした食料品価格の高騰とエネルギー価格の高止まりにより、2025年6月に3.3%となった。2025年度の上昇率見通し(生鮮を除く総合)は、7月時点の民間調査機関の予測平均で2.5%となっている。
厚生労働省の毎月勤労統計によると、2025年1月以降、実質賃金は4カ月連続でマイナスとなった。
日銀短観の雇用人員判断DIによると、企業規模に関わらず人手不足感が強まっており、中堅・中小企業ではより人手不足感が強くなっている。とりわけ、厚生労働省の一般職業紹介状況によると、生産工程の職業の人材確保が困難となっている。
金属産業の企業業績について、日銀短観によると、2025年度の売上高は多くの産業で増収予想となっている一方、経常利益は、多くの業種で減益予想となっている。
(2)政治情勢
2024年9月、自由民主党は当時の岸田文雄首相の任期満了に伴う総裁選挙を実施した。9人の候補者による総裁選挙の結果、石破茂氏が選出され、翌月首相に指名された。
2024年10月、第50回衆議院議員選挙が実施された。その結果、与党は過半数を割り込むこととなった。立憲民主党は前回から50議席増加して148議席となり、国民民主党は21議席を新たに獲得し28議席となった。
2025年2月、政府は「第7次エネルギー基本計画」を閣議決定した。本計画では、前計画からの情勢変化としてDXやGXの進展に伴う電力需要の増加を見込み、2040年の電源構成を再生可能エネルギーで4~5割、原子力で2割、火力で3~4割程度となる見通しを立てた。また、原子力の最大限の活用を推進する方針を固めた。
2025年3月、トランプ大統領は鉄鋼・アルミニウム製品に対して追加関税を課し、4月、6月には対象品目を追加している。4月には全世界に対して「相互関税」を発動する大統領令に署名し、7月までの交渉の結果、15%の関税率に引き下げられることで日米両国は合意した。
2025年5月、人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律(以下、AI法)が成立した。AI法はイノベーションを促進し、リスクに対応するために策定された。
同月、改正下請法と改正下請振興法が成立し、名称がそれぞれ「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」と「受託中小企業振興法」となった。
また同月、内閣府は経済財政運営と改革の基本方針2025(骨太の方針)を閣議決定した。昨年の骨太の方針を踏襲しつつ、地方創生2.0の推進や2020年代末までに最低賃金全国平均1,500円とすること、ソブリンAIやワット・ビット連携の促進などが新たに掲げられた。
2025年7月、第27回参議院議員選挙が実施された。結果、政権与党は衆参両院で過半数を割り込む形となり、国民民主党は大きく議席を伸ばした。また、参政党など新たな政治勢力の議席拡大が目立った。
3.2 国際情勢
長期化するロシアのウクライナ侵略、イスラエルとハマスの対立とガザ地区の人道危機、イスラエルとイランの対立と米国の介入、タイとカンボジアの軍事衝突、インドとパキスタンの軍事衝突など、国家間の対立が深まっている。気候変動への対応では、米国がパリ協定を離脱し、欧州でも環境規制の緩和を求める声が強まるなど、牽引役が不在となっている。また、不平等や格差の拡大を背景として各国で極右的な考えが広まり、SNSでは虚偽や誤解を招く情報が拡散されるなど、社会の分断が加速している。世界経済フォーラム「グローバルリスク報告書2025年版」で指摘されているように、われわれは冷戦以来、最も分断された時代を生きている。
(1)経済情勢
 世界経済の見通しについて、米国の関税政策より貿易と設備投資が伸び悩み、2025年の実質GDP成長率見通しは2.3%と前年と成長が鈍化すると見られている。
世界経済の見通しについて、米国の関税政策より貿易と設備投資が伸び悩み、2025年の実質GDP成長率見通しは2.3%と前年と成長が鈍化すると見られている。
(2)政治情勢
2022年2月以降、ロシアがウクライナに侵略を開始して3年が経過し、戦闘は長期化している。死者数について、ウクライナの民間人は12,600人以上、ウクライナ軍兵士は46,000人以上と発表されている。
2024年11月、米国の大統領選挙で共和党のトランプ元大統領が当選した。「相互関税」をはじめとする関税措置や「報復税」の検討など、経済は混乱している。外交面では、ロシアに対してウクライナ侵略の停戦を働きかけるも、いまだ停戦には至っておらず、戦闘の激しさは増している。6月には米国として初めてイラン領内に攻撃し、核施設の破壊を試みるなど、国際情勢は不安定化している。
2024年12月、韓国の尹大統領は、野党が国政を麻痺させているとして、44年ぶりに非常戒厳を宣言した。この問題を巡り尹大統領は弾劾訴追され、2025年4月に憲法裁判所が罷免を決定した。同年6月の大統領選挙で革新系の李氏が当選し、3年ぶりの政権交代となった。
4.運動方針
4.1 国際連帯・国内外での建設的労使関係構築に向けた活動
国際連帯活動
 (1)目的
(1)目的
- アジア地域における国際労働運動のリード役として金属労協がその運動をめざすべき方向へ導くべく、引き続き、インダストリオール台での発言力・影響力の維持・向上を図る。加えて、各国の労働・社会情勢に関する情報や、先進事例を収集し、国内情勢における課題解決にもつなげていく。さらに、海外友誼組織との国際連帯活動を通じて、組合間ネットワークの維持・強化ならびに国際労働情勢等の情報収集に努める。
- また、国際連帯活動の推進に資すべく、国内連帯、国内関係組織との定期的な交流・情報交換を進める。
 (2)課題・背景など
(2)課題・背景など
- 金属労協が加盟する国際産別組織インダストリオールは、2025年にオーストラリアで開催が予定されている第4回世界大会に向けて、①平等と労働者の権利を求める闘い、②労働組合の力の構築、③資本の責任を問う、④公正な移行を通した未来の形成、を取り組みの柱として準備を進めている。
- 関税政策を含め予測困難な米国の政権運営、米中対立による世界情勢の変化、依然として続くミャンマー国軍によるクーデター、ロシアのウクライナ侵攻、イスラエル・パレスチナ紛争など、世界各地で人道的危機や民主主義への脅威が発生し、労働基本権が侵害されている。さらには、DX・GX・AIといった技術革新・グリーン化政策への対応の要請など、世界的な市場・労働環境の変化が生じている。こうした中で、より産業横断的な公正な移行を中心とする政策の実現、グローバルでの労働基本権の確保、社会的不平等の解消、女性・若年層の参画向上の実現に向けた活動が求められる。金属労協としてもこうした活動への適切な対応による公正な労働基準の確保、その実現に向けた建設的労使関係の確立が国内外の労使において期待されている。
 (3)具体的な運動
(3)具体的な運動
- 2025年に開催されるインダストリオール世界大会に向けて、主要加盟組織との連携をさらに強化し、各種取り組みや議論へ主体的に参画する。リーダーシップにおいては、副会長・アジア太平洋地域共同議長、女性代理執行委員を引き続き務める。加えて、本部書記次長の派遣組織としての役割と責任を果たす。
- 国際的な産業課題については、国内活動と連携しつつ、インダストリオールの活動に積極的に対応し、JLCとも連携を図り、インダストリオールやその加盟組織に対する働きかけを行う。
- 「日韓金属労組定期協議」については2026年までの実施の枠組みにて、2025年11月以降の受け入れを調整する。また、2026年には、「日独金属労組定期協議」での受け入れ、再開を果たした「中国金属工会との交流」では派遣に向けて調整する。
- 男女共同参画では、インダストリオールを含めた国際的な動向の把握に努めるとともに、国際会議等への対応を図る。
- 青年活動に関しては、インダストリオールにおける取り組みを注視し、対応を検討する。
- JLCとの連携を通じて、インダストリオール活動への積極的な参画を進める。特にアジア加盟組織との強固な関係を築くために、定期的な意見交換やアジアの関係労組のリーダー招聘などの活動を実施する。
- 連合・GUF・JILAF・ILO駐日事務所や各省庁、駐日大使館といった関係組織との協議・連携の場をもつ。その他の組織・団体についても、活動領域に応じ参加、連携を行う(JP-MIRAI等)。
人権デュー・ディリジェンス
 (1)目的
(1)目的
- 特別なステークホルダーである労働組合の参画のもと、企業が人権デュー・ディリジェンスを適切に実施することにより、グローバル・バリューチェーン全体での労働基本権を含む人権侵害撲滅と企業の持続可能性確保をめざす。
 (2)課題・背景など
(2)課題・背景など
- 「人権」がクローズアップされている。海外の一部地域における人権抑圧だけでなく、企業の国内外におけるバリューチェーンでの人権侵害も焦点になっている。欧米を中心に義務化・法制化が進められている人権デュー・ディリジェンスについては、日本政府が「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」を策定したこともあり、大手を中心に取り組みが始まっている。労働組合は特別なステークホルダーとして、国内外で連携を取りながら、グローバル・バリューチェーン全体での労働基本権を含む人権侵害撲滅と企業の持続可能性確保に向けた参画が求められている。
- 多国籍企業労組ネットワークや、それを通じて構築された海外事業体における建設的な労使関係は、グローバルな人権デュー・ディリジェンスの取り組みの基盤となる。
- 同時に、適切に人権デュー・ディリジェンスを実施することは、企業における建設的な労使関係を築く上で欠かせない結社の自由・団結権、団体交渉権の確保につながる。
- 日本政府の「ガイドライン」には、法的拘束力はなく、また、労働組合を単にステークホルダーの一つと位置付けているなど課題がある。
- 人権デュー・ディリジェンスにおいて最低限守るべき人権の中でも、労働に関する基本的権利を定めたILO中核的労働基準の10条約について、日本は2条約が未批准である。これは日本の人権遵守体制・制度の未整備を示すものであり、国際社会の信頼を損ねることにもつながる。
 (3)具体的な運動
(3)具体的な運動
- 引き続き、金属労協「人権デュー・ディリジェンスにおける対応のポイント」を活用し、人権デュー・ディリジェンスを実施するためのプロセスや苦情処理・救済システムの設置状況を企業に確認するとともに、労働組合としてそれらに参画すべく取り組む。
- 未設置の場合には、設置を促し、プロセス等の設計段階から参画すべく取り組む。
- 産別・単組の取り組みの環境整備のため、政府や経営側、国際機関、NGO等に対して労働組合の参画の必要性を訴求する。
- バリューチェーン上の人権状況の掌握や、人権侵害が発生している場合の苦情処理・救済につなげる観点からも、多国籍企業労組ネットワークの構築等に取り組む。
- 政府ガイドラインの課題の是正や、年限を設定した上でのガイドライン実効性の検証、実効性に疑義がある場合の義務化・法制化等、政策的な対応も進める。
- ILO「中核的労働基準」の中で111号(雇用及び職業についての差別待遇に関する条約)、155号(職業上の安全及び健康に関する条約)について、政府に対し早期の批准・発効を求める。(155号条約については、2025年5月に批准を国会が承認。今後は発効に向けた手続きが進められる。)
多国籍企業労組ネットワーク構築
 (1)目的
(1)目的
- 海外事業体における建設的な労使関係の構築に向けて、海外労組と日本の労組とのネットワーク構築の推進と労使の理解促進を引き続き求める。特に、日系企業が多く進出するアジア各国において、信頼関係の構築や情報共有体制の強化を通じて、現地労使の相互理解に資する活動を継続・発展させる。
- また、こうしたネットワークの深化を、インダストリオールが推進するGFA(グローバル枠組み協定)の締結や、サプライチェーン上の人権課題への対応の基盤づくりとして位置付ける。
- 個別企業の労使紛争案件については、現地組織や地域事務所との連携を強化する。引き続きオンラインでの情報収集・意見交換活動も継続し、情報の動きに素早くかつ適切な対応を図る。
 (2)課題・背景など
(2)課題・背景など
- 海外事業体における労使による対立、経営側による労働基本権の侵害等が依然として報告されている。金属労協としても産別・単組と連携し、解決に至る活動を推進してきた。引き続き、個別の紛争案件への迅速かつ適切な対応とともに、めざすべき海外事業体における建設的な労使関係の構築に資する活動が求められている。
- 国際労働運動は、その性質上、実際に労使紛争や労働権侵害といった事象に直面しない限り、個々の組織にとって“自分事”として捉えることが難しい側面がある。こうした構造的な距離感が、産別・単組における国際活動の推進や、ネットワーク構築への積極的な関与が広がりにくい要因の一つとなっている。
 (3)具体的な運動
(3)具体的な運動
- タイ・インドネシアにおける労使ワークショップは、現地労使の信頼関係の醸成と相互理解の深化を目的に、引き続き開催に向けた調整を進める。特にこれまでの取り組みのフォローアップ(現地ニーズの再確認等)と、企業側の理解・参画を促すための新たな枠組みや手法を検討し、開催準備の段階から現地産別との連携強化を図る。また、日本側からのオンライン傍聴参加も積極的に募り、産別・単組の国際活動への関心喚起につなげる。
- 労使紛争の解決に向けた支援に関しては、タイ・インドネシアの組織とのネットワークを基盤に、オンラインを活用した情報収集と即応体制の整備を進める。産別・単組との連携のもと、問題の早期把握と迅速な対応を実現し、中核的労働基準の遵守を支援する。
国際人材育成
 (1)目的
(1)目的
- 女性・若年層も含めた幅広いメンバーが国際労働人材として広く活動できるよう、基礎的な素養を身に着けるべく教育活動を継続的に実施する。また、活動の助け・即戦力となる人材の育成に資する国際労働組合・運動情報を組織の資産とすべく、効率的な情報の整理と蓄積・活用をめざす。
 (2)課題・背景など
(2)課題・背景など
- 建設的な労使関係の構築を一層推進するにあたっては、金属労協・産別のみならず、単組の役員まで届く活動を展開し、国際労働運動を推進できる人材を継続的に維持ないし裾野を拡大していくことが基盤整備として求められる。
 (3)具体的な運動
(3)具体的な運動
- 国際労働運動を担う人材を育成することを狙いに、日系企業の進出が多い東南アジアを中心に現地の労使関係の大枠をつかめるプログラム(現地関係省庁、経営者団体、労働組合等を訪問・議論)を継続して実施する。
- 海外労組に関する情報、労使紛争の経緯等を収集したJCMPediaを継続整備し、産別の国際活動の支援に積極的に活用する。
日本の労使への建設的労使関係構築の理解促進
 (1)目的
(1)目的
- 労使双方が、中核的労働基準も含めた人権の確保や建設的労使関係構築の重要性に関する理解を深め、進出先の現地労使における日頃からの円滑なコミュニケーションの確保を図る。あわせて、現地労組とのネットワーク構築実現に向けたバックアップを推進する。
 (2)課題・背景など
(2)課題・背景など
- バリューチェーン全体にわたり、中核的労働基準も含めた人権の確保が企業に求められている。その実効性ある取り組み推進に向けて、人権デュー・ディリジェンスや建設的な労使関係構築の重要性に対する日本の労使の理解促進は、金属労協のめざす海外現地事業体における活動推進の基盤として期待される。
 (3)具体的な運動
(3)具体的な運動
- 「海外における建設的な労使関係の構築に向けた国内労使セミナー」については、時宜を得たテーマを設定し、オンライン開催を基本に継続的に開催する。
4.2 多様性の推進に向けた取り組み(新設)
 (1)目的
(1)目的
- 持続可能な労働組合運動を実現するためには、性別や世代などにかかわらず多様な構成員がその力を発揮できる、包摂的な運動体制の構築が不可欠である。
- 金属労協はこれまで、男女共同参画を中心に多様性推進に取り組み一定の前進を図ってきた。今後はその到達点を踏まえつつ、若年層の参画促進についても位置づけの整理から始め、意識づけと仕組みづくりの両面で取り組みを強化していく。
 (2)課題・背景など
(2)課題・背景など
- 女性参画については、第4次「男女共同参画推進中期目標・行動計画」に基づいた活動や研修会、ネットワークづくりなどを通じて着実に進展している。引き続きその取り組みを支え、組織全体での意識定着を進めていく。
- 一方、若年層の運動参画については、国際的にはインダストリオールをはじめとする多くの組織で運動が活発化している。各国とも取り組みとしてはまだ序盤であり道半ばではあるが、次世代のリーダーシップ育成と意思決定への関与をめざし、各国の組織が重点課題として取り組みを強化している。
- 日本においても、若年層の組合活動への関心を高めるため、これまで様々な取り組みが行われてきた。しかし、それらは主に組合活動への参加のきっかけ作りや、組合との接点の場の提供に主眼が置かれている。若年層の声を運動の中核に反映させ、意思決定の場に参画する仕組みは、まだ十分に構築されていない。まずは現状や課題に対する認識を組織内で共有した上で、若年層が責任ある立場で運動に関与できるよう、段階的に環境を整えていくことが求められる。
 (3)具体的な運動
(3)具体的な運動
(女性参画の継続的推進)
- 第4次「男女共同参画推進中期目標・行動計画」に基づき、女性役員の登用促進、ネットワーク強化、他産別との交流・学習機会を引き続き提供する。なお、当該中期目標・行動計画は2026年8月が期限であることから、2026年度中に次期目標・計画を定めることとする。
- 男女共同参画推進連絡会議の活性化や、他産別主催研修への参加調整などを通じて、運動の横断的な広がりを確保する。
(若年層の運動参画に向けた議論)
- 今後2年間、若年層の運動参画について、まずはその意義やあり方について、金属労協としての基本的な考え方を明確にする期間と位置づける。
- 若年層の運動に対する意識・実態・課題を丁寧に把握し、「どのような参画の形が望ましいのか」といった視点に立ち、組織としての問題意識を共有・整理していく。その上で、加盟組織との意見交換や対話を重ねながら、金属労協としての基本的な方針・考え方を取りまとめ、今後の段階的な取り組みの土台とする。
- インダストリオールの青年プログラム等を通じ、国際的な動向の把握に継続して取り組む。把握した動向は、金属労協内での議論に活かしていく。
- また、国際的な若年層の交流の場に各組織からの参画を促すことにより、国際労働運動に対する理解促進につなげる。
- 産別・単組における多様性推進に関する好事例を可視化ならびに共有し、各組織が自組織の取り組みを点検するための情報を提供する。
4.3 次世代の加盟産別・単組の活動を担う役員の育成とスキルアップを支援するための活動
 (1)目的
(1)目的
- 金属労協のネットワークを活かして、産別活動に資する時宜に応じたテーマのセミナー、勉強会を参加しやすく効果的な形態で開催し、産別・単組の役職員のスキルアップに貢献する。
- 労働リーダーシップコースでは、産別や単組の枠を超えた人材交流を通し、大きな時代の変革期に対応できる人材育成、産業社会の発展に寄与するため、基礎的教育を行う。
 (2)課題・背景など
(2)課題・背景など
- 人材育成は新しい金属労協において主体的に取り組む活動の一つである。
- 次世代リーダーの育成は、組織の発展・強化にとって最も重要な課題であり、産別・単組においても様々な教育活動が行われている。金属労協には、産別・単組ではカバーしきれないテーマを取り上げるなど、産別結集組織としての特色を活かした教育・研修を実施することが求められている。
- 各種研修会の開催については、主旨、対象者、内容を明確にしたうえで、開催方法(Web開催)などについて整理していく必要がある。
- 労働リーダーシップコースは多くの労働組合リーダーを輩出してきた。また、産別・単組の枠を超えて人と人とをつなぐ交流の場としても高く評価されている。一方で、近年は、受講組織が偏重傾向にあることから「受講組織のすそ野を広げること」が課題となっている。
- 女性受講率の向上は引き続き取り組むべき課題であり、また、次代のニーズに応じたプログラムの改善なども求められている。
 (3)具体的な運動
(3)具体的な運動
- 人材育成のあり方や具体的活動については、引き続き組織委員会で検討する。
(各種セミナー・研修会について)
- 産別のニーズを把握し、必要に応じて研修会・セミナーを企画、開催する。
- 産別・単組役員を対象とした、より専門性の高いセミナーの実施を検討する。
- 各産別で実施しているセミナー・研修会のうち、要望に応じて、金属労協としての開催を検討する。
- セミナー・研修会の開催にあたっては、都度、Web活用を検討し、参加しやすいしくみ作りに努める。
(労働リーダーシップコースについて)
- 労働リーダーシップコースは、当面の間、既存の運用を踏襲し、期間や基本的プログラム、募集人員の変更なく開催する。
- 労働リーダーシップコースの目的や教育方針を堅持しつつ、時代のニーズに応じたプログラムの改善や内容の充実を図る。
- 受講組織のすそ野を広げるため、産別・単組への周知・理解を深める取り組みを強化し、PR素材の制作等も検討する。
- 産別からの発信範囲拡大、浸透方法について情報を共有し、取り組みを推進する。
- 受講生からの意見等も取り入れ、受講しやすい環境整備に努める。
- 女性受講率の向上については、受講組織のすそ野を広げる取り組みの中で意識付けを提起していく。
4.4 強固な金属産業を構築する産業政策
 (1)目的
(1)目的
- ものづくり産業には、激変する国際情勢や脅かされる自由貿易、DX・GX、AIをはじめとした新技術への対応による産業の競争力強化が必要である。このような情勢に対応できるものづくり産業の基盤強化や産業の発展に資する強靭な産業政策を展開することで、強固な現場・強固な金属産業・強固な日本経済の構築をめざす。
- 技術変化への対応に際しては、社会的対話と労使協議を重ねる中で、新たに必要となるスキルの習得・向上に向け教育訓練を拡充し、急激な変化が雇用に悪影響を与えないための対策、いわゆる「公正な移行」を実現していく。
- 優越的地位の濫用規制と中小受託取引適正化法(旧下請法)の実効性強化、中小企業の生産性向上などにより、バリューチェーンにおける付加価値の創出・適正配分に寄与する。
 (2)課題・背景など
(2)課題・背景など
- 国際情勢が激変し、わが国における経済安全保障の重要性が高まっている。加えて、人材獲得競争の激化、DX・GX・AIなど新技術への対応など、金属産業は変化を迫られる渦中にある。
- 「産業政策提言」では、民間・ものづくり・金属産業に働く者の観点から、引き続き時々の課題に迅速に対応し、項目の重点化による機動性の確保によって政策の実現力を一層高める必要がある。
 (3)具体的な運動
(3)具体的な運動
- わが国金属産業の命運を決する課題とその解決に向けた施策を検討し、「産業政策提言」を策定する。その実現に向けて、省庁や政党等との意見交換や要請活動を展開する。
- 「産業政策提言」の策定に際しては、産別や単組からの幅広い情報提供、提案を募り、意見集約を図るため、産業政策中央討論集会を実施する。
- 政治顧問との連携を強化し、政策実現に向けて協力を進める。「政策レポート」の発行等を通じて組織内外の理解促進を図る。
- 当該年の要請項目の如何に関わらず、政策課題に関する各府省等の担当窓口と定期的な意見交換・情報交換の場を設ける。また、経済・業界団体、政党等の意見交換・情報交換の場を設ける。
4.5 労働政策-金属共闘、特定最低賃金の推進
金属共闘
 (1)目的
(1)目的
- 日本の基幹産業にふさわしい賃金水準の確立および賃金の底上げ・格差是正をめざし、生産性運動三原則に基づく、「成果の公正な分配」「実質賃金の維持・向上」「人への投資」を追求する。
- 心身の健康を維持し、家庭生活や地域活動、社会貢献、自己啓発など個人のための生活時間を確保して生活の豊かさを追求するとともに、人材の確保・定着、生産性の向上を図る観点からも働き方の見直しをすすめる。
- 同じ職場で働く仲間として、同一価値労働同一賃金を基本に、非正規雇用で働く労働者の賃金・労働諸条件の改善を実現する。
 (2)課題・背景など
(2)課題・背景など
- 国際情勢が激変し、グローバル経済の先行き不透明感が高まっている。積極的な賃上げを継続することで、内需主導の安定的・持続的な経済成長を実現していく必要性が一層高まっている。
- DX、GXなどの産業の大変革に積極的に対応し、金属産業の成長力を高め、競争力を強化するための人材の確保・定着が喫緊の課題となっている。産業・企業の魅力を高めるため、継続的な賃上げによる「人への投資」をさらに強化していく必要がある。
- 生産年齢人口の減少が続き、人材獲得競争が激化している。多様な人材が最大限能力を発揮することができる職場環境を整備することが必要となっている。
 (3)具体的な運動
(3)具体的な運動
- 生活の安定と向上、現場力・競争力の強化、経済の持続的成長を達成するため、継続的な賃上げによる「人への投資」を追求していく。
- 企業内最低賃金協定と特定最低賃金に対する組織内外の理解を促進するため、企業内および産業全体に果たす役割を整理し、教宣資料を作成する。
- 初任給や地域別最低賃金の動向等を踏まえ、企業内最低賃金協定の中期目標について検証し、必要に応じて見直しを行う。
- 生計費や賃金水準の動向等を踏まえ、「JCミニマム(35歳)」の水準について検証し、必要に応じて見直しを行う。
- 労働諸条件の改善に向けて、統一取り組み項目の設定など、共闘効果を高める取り組みを検討する。
- 闘争を取りまく環境と課題と各産別の闘争方針を共有し、JC共闘を強化するため、「闘争推進集会」を開催する。
- 経済情勢や経営側の主張に対する金属労協の考え方等を「交渉参考資料」として取りまとめる。
- 賃金の底上げ・格差是正、適正な労働時間の実現を前進させるため、個別賃金水準の実態調査と労働時間の実態調査を継続する。大手労組の主要な労働条件を共有するため、「労働諸条件一覧」についても、引き続き取りまとめる。
- JC共闘と連合の部門別共闘との一体化を模索し、連合本部との連携をさらに強化する。
- 2016年に策定した「第3次賃金・労働政策」について、積極的な賃上げを継続する中での中期的な課題の顕在化、人材獲得競争の激化と労働市場の流動化、賃金・処遇制度の多様化など、足元までの環境変化を踏まえ、関連する論点を整理したうえで改定する。
特定最低賃金
 (1)目的
(1)目的
- 特定最低賃金を通じて企業内最低賃金を波及させることによって、未組織労働者なども含めた金属産業で働く者全体の賃金の底上げ・格差是正を図る。
- 特定最低賃金を金属産業の労働の価値にふさわしい水準に引き上げることによって、産業の魅力を高め、人材を確保することで産業の競争力を高めるという好循環サイクルを構築する。
 (2)課題・背景など
(2)課題・背景など
- バリューチェーン全体の持続的な発展を図るため、特定最低賃金を通じて、産業全体の賃金の底上げ・格差是正と公正競争の確保を図る必要がある。
- 地域別最低賃金の積極的な引き上げや使用者側の廃止論により、地域別最低賃金と特定最低賃金の水準が接近・逆転し、金額改正ができない事態が生じている。
 (3)具体的な運動
(3)具体的な運動
- 都道府県別に設定されているすべての金属産業の特定最低賃金について、金額改正の取り組みを行う。新設についても積極的に取り組む。
- 地域別最低賃金との水準差を維持・拡大するため、地域別最低賃金の引き上げ額以上の特定最低賃金の引き上げを継続的に実現していく。
- 構成産別の中央最低賃金審議会委員と最低賃金担当者による「最低賃金担当者会議」を適宜開催し、産別間の情報共有を図るとともに、方針の立案や地域の取り組みを支援する資料を作成する。
- 特定最低賃金の課題と取り組み方針を共有するため、地域の最低賃金担当者の参加の下、「最低賃金連絡会議」を開催する。
- 重点的に取り組む必要がある地域では、地方連合会と連携して、産別本部と地域の最低賃金担当者と情報交換・意見交換を行う機会を設ける。
- 厚生労働省に対して、地方最低賃金審議会の運営の改善を働きかける。
- 特定最低賃金の意義・役割への理解を広げ、特定最低賃金強化の機運を醸成するため、経営者団体や有識者等に対する働きかけを強化する。
- 具体的な取り組みについては、「特定最低賃金の取り組み方針」を策定する。状況の変化に対応し、適宜「特定最低賃金の金額改正・新設に臨む確認事項」を示す。
- 特定最低賃金の中期的な課題について、継続的に検討を進める。
4.6 地方活動の展開
 (1)目的
(1)目的
- 地方ブロックおよび都道府県単位での活動の場をつくり、金属労協の方針の周知や理解促進、および意見交換・経験交流を活発化させ、地方連合会で金属部門として労働政策や産業政策の推進に力を発揮できるようにする。
- 生産拠点が実際に存在し、組合員の生活の場でもある地元の活性化を促すことにより、基幹産業たる金属産業の持続的な発展を図る。
- 地域再生・活性化のために、金属・ものづくり産業の職場を代表する金属労協加盟の産別・単組の声を政策決定に反映させる。
 (2)課題・背景など
(2)課題・背景など
- 第60回定期大会報告・組織財政検討プロジェクト答申として、金属労協の地方組織を将来的には地方連合会の産業別活動センターに移行していくという方向性が示された。
- 組織改革推進会議においても、組織財政検討プロジェクトの答申を踏まえ、連合との間で、金属労協として考える「部門別連絡会と部門共闘のあり方」および今後の「連合と金属労協の組織のあり方」を中心に意見交換を行ってきた。
- 地方連合会での金属部門に関する調査を行うとともに、今後のあり方について議論を進めてきたが、組織全体のあり方と合わせ、引き続き地方ブロックおいても議論を行う必要がある。
- 地方連合会の政策への盛り込みを主眼とする「地方における産業政策課題」を策定し、地方組織の利用に供してきた。
- 各地域での最低賃金や「地方における産業政策課題」に関する研修会については、Web開催も含めて提案し、実施地域も増えてきている。このようにわかりやすさ、取り組みやすさの強化を図ってきたが、都道府県ごとの取り組みには差が見られるため、理解促進活動を強化する必要がある。
- 地方政策の推進、永続的な地方活動の活性化に向け、地方ブロックおよび各都道府県の活動内容の情報共有を図る。
 (3)具体的な運動
(3)具体的な運動
- 地方ブロックおよび各都道府県の活動内容に関する情報交換と共有化を図るため、地方ブロック代表者会議を年2回開催する。
- 地方ブロック代表者会議が、出席者相互の、より闊達な意見交換や情報共有の場となるよう、会議の開催時間や開催頻度、議題などを検討する。
- ものづくり教室の取り組み事例を集約・情報提供するなど、継続的な実施や内容の充実に向けた地方組織へのサポートを行う。
- 「民間・ものづくり・金属」の立場から「地方における産業政策課題」を策定し、地方での政策活動に寄与するとともに、ものづくりの魅力を子どもたちに伝える「ものづくり教室」の開催など、労働組合としての活動の実施を促す。
- 「最低賃金」や「地方における産業政策課題」に関する研修会について、各地域での開催を促す。また、開催が困難な地域に向けては、金属労協主催でWebでの学習会開催を検討する。
4.7 情報発信
 (1)目的
(1)目的
- 金属労協の方針や活動を周知し、加盟産別・単組への金属労協の取り組みに関する理解を深める。
- インダストリオールはじめ諸外国労組の活動や、国際的な課題、さらには時宜に応じたテーマに関する取り組みや論考を紹介し、加盟産別・単組の活動に活かす。
- 春闘情報などを組織内外に発信し、金属労協の社会的役割を果たす。
 (2)課題・背景など
(2)課題・背景など
- 金属労協から主に産別・単組に向けた情報発信ツールとして機関紙を年4回、機関誌を年2回発行してきた。また、ホームページを活用して、春闘情報やインダストリオールニュースなどをタイムリーに発信している。
- デジタル技術の進化により、即時性、双方向性のある多様な情報発信ツールが活用される時代となり、紙媒体から電子メディアを中心とした情報発信への変更が求められている。
- 電子化にあたっては、金属労協全体の情報発信を整理し、総合的に発信媒体・ツールを検討していく必要がある。
- 2024-2025年度は広報担当者会議での意見も参考に、講読数(閲覧数)の維持等を課題とし、組織委員会で議論してきた。
 (3)具体的な運動
(3)具体的な運動
- 金属労協全体の情報発信を整理し、総合的に発信媒体・ツールを検討していく
- 電子化に特化した情報発信に向けて下記に取り組む
(機関紙について)
- 運動(活動)方針号・闘争方針号を2026-2027度中に電子化する。電子化にあたっては、レイアウトを見直し、見せ方等を工夫する。
- 大会報告号・新年号(協議委員会報告号)は当面、紙媒体とし、引き続き電子化に向け検討する。
(機関誌について)
- それぞれのコンテンツに対し、必要とする役員が、必要な時に閲覧するという実態を鑑み、当面は紙媒体とする。
- 2026-2027年度は電子化、発行回数・ページ数、コンテンツについて、引き続き検討する。
(ホームページの充実に向けて)
- コンテンツごとに閲覧対象者を整理し、ホームページ全体の充実を図る。
- リアルタイムに閲覧できる環境を整えるべく、更新情報の周知方法について検討する。
- リアルタイムな更新に努める。
(SNSについて)
- 持続可能な運営に向けた体制、コンテンツを整理し、必要性について慎重に検討する。
4.8 新しい金属労協のあるべき姿の実現に向けて
 (1)目的
(1)目的
- 「新しい金属労協のあるべき姿」の実現に向けた取り組みを引き続き推進する。
 (2)課題・背景など
(2)課題・背景など
- 2015年度から「組織財政検討プロジェクトチーム」を発足させ、支出削減を含む財政対策の検討を中心に具体的な対応策を提起し、対応できるものから随時、実施してきた。
- その後、「組織財政検討プロジェクトチーム」では組織と活動のあり方に焦点を当て、未来志向でこれからの金属労協の姿を議論し、第59回定期大会において「2020年組織財政検討プロジェクト答申」として「新しい金属労協のあるべき姿」に関する提起が行われた。
 (3)具体的な運動
(3)具体的な運動
- 連合は、2023年10月からの運動方針の中で、組織体制について検証し、必要に応じた見直しを提起した。金属労協は「新しい金属労協のあるべき姿」を念頭に置きつつ、「連合部門別共闘会議とJC共闘との連携強化」ならびに「連合の政策と金属労協の産業政策とをいかにして融合させていくのか」という観点で連合との話し合いを継続していく。
- 取り組みに当たっては、連合の組織検討プロセスを注視するとともに、担当部局との連携をさらに深めていく。
4.9 持続可能な財政運営に向けて
 (1)目的
(1)目的
- 健全な財政運営により、持続可能な組織とする。
- 金属労協に求められる役割に沿って、活動を効率的に実施できるような予算措置を講ずる。
 (2)課題・背景など
(2)課題・背景など
- 金属労協の財政は、2013年度以降財政基金積立金からの繰り入れで対応してきた。2020年度・21年度はコロナ禍による海外出張の制限などにより、単年度収支が黒字となったが、基調としての単年度収支均衡には至っていない。
- 金属労協の支出の約60%(2024年度決算)を占めるインダストリオール会費が、スイスの物価上昇に合わせた調整による増額や円安傾向などにより、財政に深刻な影響を与えている。
- 財政基金積立金は、2027年度予算策定時には枯渇する見込みとなり、今後の財政運営の抜本的な見直しに向けた施策が急務となった。
- 2024-2025年度は「組織改革推進会議」において、抜本的な財政改革について検討してきた。
- 更なる経費削減、予算精査、インダストリオール本部への登録人員の暫定的な減員要請、急激な為替変動に対する緩和措置等などの規約改正の提案等、さまざまな施策を検討・実施してきたが、現状の産別会費収入のみでは持続可能な財政運営は困難であるとの結論に至った。
 (3)具体的な運動
(3)具体的な運動
- 単年度収支均衡に向けて、引き続き支出削減・予算精査、効率化に努める。
- 2027年度よりインダストリオール加盟費不足分を、会費納入人員比により産別負担とする。
- 詳細は、独立議案で提案する。