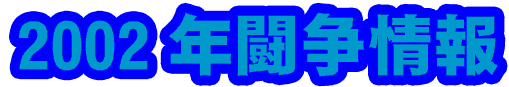 |
|
|
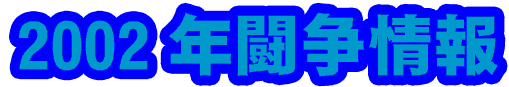 |
|
|
|
|
|
|
金属労協は昨年12月、第44回協議委員会において、2002年闘争に臨む金属労協の方針として「2002年闘争の推進」を決定、これに基づき、JC各産別はそれぞれ取り組みを進めつつあります。 2002年2月4日 |
| 1.戦後最悪の不況下にあるわが国経済 | ||
|
||
| 2.デフレの動向 | ||
| 3.所得に敏感に反応する消費 | ||
|
||
| 4.量的金融緩和の効果 | ||
|
|
① わが国経済は、2000年10月以降、景気後退が続いてきました。名目GDP成長率で見ると、99年度にはわずかながらプラス成長(0.2%)だったのが、2000年度には△0.3%のマイナス成長となり、2001年度に入ると前年比で4~6月期△1.8%、7~9月期△2.0%とマイナス幅がさらに拡大しています。△2.0%は統計開始以来2番目に大きなマイナス成長です。(図表1) ② 2002年度経済については、名目経済成長率が政府予測で△0.9%、民間調査機関平均で△1.92%となっており、2001年度よりはやや改善するものの、依然としてマイナス成長が続く見通しとなっています。日経連も2002年度の経済情勢について、
との判断を示しています。 なお実質成長率は、政府が0.0%、民間平均が△0.67%の見通しとなっており、政府予測では、実質マイナス成長が回避される状況となっています。(図表2) ③ 個人消費の名目成長率は、2000年度に△1.3%と統計開始以来はじめてのマイナス成長を記録しました。2000年7~9月期には前年比△3.0%という大きなマイナス幅でしたが、10~12月期には、雇用者報酬がプラス1.3%と3年ぶりの高い伸び率になったことを反映し、個人消費も△1.5%とマイナス幅が縮小、2001年1~3月期には△0.5%とさらに縮小しました。しかしながらその後は、4~6月期△1.1%、7~9月期△1.7%と再びマイナス幅が拡大しています。 ④ 設備投資は、2000年度に6.3%と3年ぶりのプラス成長に転じました。2001年度に入ってからも、4~6月期2.5%、7~9月期1.5%と引き続きプラス成長で推移していますが、成長率は鈍化しています。 ⑤ 鉱工業生産指数を見ると、生産指数、生産者出荷指数とも2001年2月以降、前年割れが続いており、12月にはそれぞれ△14.9%、△14.0%と大幅マイナスを記録しています。しかしながら一方で、前年比プラスで推移していた生産者在庫指数が、2001年11月には△0.5%と14カ月ぶりにマイナスに転じ、12月には△1.6%とさらにマイナス幅が拡大しています。景気の先行きを示す指標として、今後の動向が注目されるところです。(図表3) ① 2001年3月に景気後退に転じたアメリカ経済は、9月11日の同時多発テロによってさらに追い討ちをかけられることとなりました。しかしながら、 (注)アメリカのコンファレンスボード(経団連のような財界団体)が発表している消費者心理指標。現状と先行き指数の合成指標で、調査対象は約5,000世帯。アメリカではこのほか、ミシガン大学消費者心理指数(調査対象約500人)が有名。 ② こうしたことから、わが国内閣府は2002年1月、「アメリカは、景気後退局面にあるものの底入れの兆しがみられる」との判断を示しました(月例経済報告2002年1月)。日経連も、
として、内閣府とほぼ同様の判断をしています。 ③ このようなアメリカ経済の情勢や、1ドル=130円台という為替レートの状況を受けて、わが国の輸出について内閣府は、「IT関連需要の低迷などから大幅に減少していた電気機器や一般機械などの減少幅が縮小しており、下げ止まりの兆しがみられる」「アメリカ向け輸出は、自動車の増加により全体としても増加している」「アジア向け輸出は、このところ急速に減少幅が縮小している」と分析しています。 2.デフレの動向 ① 消費者物価上昇率は、2001年4~1月の平均で前年比△0.9%となっています。4月から10月までは△0.7%ないし△0.8%で推移していたのが、11月に前年比△1.0%、12月△1.2%、1月△1.5%と3カ月連続でマイナス幅が拡大しています。(図表4) ② 一方、国全体の物価水準を示すGDPデフレーターは、94年度以降、97年度を除いてずっとマイナスが続いていますが、とりわけ2000年度には△1.9%と統計開始以来最大のマイナス幅を記録しました。しかしながら2001年度に入ってからは、4~6月期△1.4%、7~9月期△1.5%となっており、2000年度に比べてわずかではあるもののマイナス幅が縮小しています。 ③ 2002年度予測としては、消費者物価上昇率が政府△0.6%、民間平均△0.94%、GDPデフレーターが政府△0.9%、民間平均△1.25%となっており、引き続きデフレ状態が続く状況となっています。 3.所得に敏感に反応する消費 総務省・家計調査において、全国勤労者世帯の名目消費支出の動向を見てみると、2001年4月から9月まで、6カ月間にわたって前年割れが続いてきましたが、10月には0.7%、11月には2.3%と2カ月連続で前年比プラスとなりました。7月に△4.5%と大幅なマイナスであった名目可処分所得が、8月△2.4%、9月△0.6%、10月△0.6%、11月0.3%とほぼ月を追って改善してきたことによるものであり、所得の改善が消費の改善に直結していることがわかります。平均消費性向も、前年に比べて10月に1.1ポイント、11月には1.6ポイント上昇しました。 ① 家計調査における一進一退の動きは、販売統計でも裏づけられています。経産省・商業販売統計における小売業販売額は、2001年10月に前年比△4.7%だったのが、11月には△2.8%とマイナス幅が縮小しました。しかしながら、12月には△5.7%と再び拡大しています。 ② 内閣府の景気ウオッチャー調査では、景気の現状判断(水準)D.I.を発表していますが、10月に21.9であったのが、11月23.6、12月24.6(対10月差+2.7)と改善傾向が続いています。なかでも家計動向関連D.I.では、10月23.7、11月26.1、12月27.9となっており、12月には10月に比べて4.2ポイントのプラスとなるなど改善幅が大きくなっており、同時多発テロ前の8月の水準(26.9)を超える状況となっています。(図表7) (注)博報堂生活総合研究所が首都圏440人を対象に行っているアンケート調査。毎月、対象者に来月の消費意欲を点数(100点満点)で示してもらう。個別指標の合成ではなく、全体的な消費意欲のイメージをとらえているところが優れている。 ① 2001年3月19日、日銀はいわゆる「ゼロ金利政策」に代表されるような、政策金利(無担保コールレート)の誘導を中心とするこれまでの金融政策運営を改め、 ② 日銀が銀行から国債を購入すると、その代金が日銀当座預金に入金されます。「家計・企業・銀行が保有する現金と日銀当座預金の総額」をマネタリーベースといいますが、銀行はマネタリーベースの一部である「銀行が保有する現金+日銀当座預金」を法定預金準備率で割った金額だけ貸出を行うことができるので、日銀当座預金を増加させると、銀行は貸出を増加さることができます。貸し出した資金は、誰かの預金として銀行に戻ってくるので、銀行は戻ってきた預金を(法定預金準備として現金や日銀当座預金で残しておかなければならない部分を除いて)再び貸し出すことができます(=預金の自己増殖メカニズム)。銀行から貸し出された資金は、実体経済においては何らかの需要となるので、マネタリーベースの拡大は、需要(名目GDP)の拡大につながるということになります。 ③ 99年1月から2000年10月にかけての景気回復が短命に終わった理由のひとつには、コンピューター2000年問題の発生に備えて99年末から2000年初に日銀が行ったマネタリーベースの大幅供給拡大が、景気回復を後押ししていたのにもかかわらず、2000年5月以降、日銀が逆にマネタリーベースを急激に絞り込んだ、ということがあげられます。2001年3月の量的金融緩和への転換は、こうした金融政策の失敗を修正したものといえます。 ④ しかしながら、3月19日の量的金融緩和では、 そして9月11日には、アメリカで同時多発テロが勃発し、経済活動に対する企業・消費者のマインドが急激に冷え込みましたので、2%の名目成長達成のためには、さらに多くのマネタリーベースが必要な状況となりました。(2001年7~9月期のデータから推計すると13%程度)(図表8) ⑤ こうしたことから、日銀は8月、9月、12月と3度にわたって追加の量的金融緩和を断行、12月19日の金融緩和では、日銀当座預金残高を「10~15兆円程度」とすることを決定しました。 ① 量的金融緩和によってマネタリーベースを拡大しても、企業の資金需要が冷え込んでいるために、銀行の貸出が増えないのではないか、という見方もありましたが、国内銀行の設備資金新規貸出金の増加率を見ると、2001年1~3月期には前年比で6.5%に止まっていたのが、4~6月期には12.0%に拡大しており、量的金融緩和による貸出増効果は明白となっています。ただし、7~9月期は同時多発テロの影響から5.2%に鈍化しており、追加の量的金融緩和が必要であったことを如実に示しています。(図表10) ② なおマネタリーベースの動きは、実体経済面ではタイムラグを持ちつつ、機械受注に比較的よく反映されます。内閣府・機械受注統計(受注額合計)を見ると、2001年6月以降、前年比マイナスが続いており、とりわけ10月には△21.6%の大幅マイナスとなっていましたが、11月には△10.0%とマイナス幅が半減、季節調整済み前月比では18.8%の大幅プラスになっています。(図表11) |
| 1.大不況を回避するための負担の分かち合い | |||||
|
|||||
| 2.賃上げに対する考え方 | |||||
|
|||||
| 3.賃上げと個人消費 | |||||
| 4.ワークシェアリング | |||||
| 5.多様な雇用形態 | |||||
|
|||||
| 6.ものづくり産業こそが日本の礎 | |||||
|
|
① 前述のとおり、わが国経済はまさに戦後最悪の不況下にあり、これがさらにデフレスパイラルによる大不況へと突き進んでいくことのないよう、経済活動の主体である政労使が、なすべき責任と役割を果たしていかなければなりません。 ② 政労使三者の果たすべき責任と役割として、まず政府は、早急にデフレ解消を図り、金融危機の発生を回避するための適切な金融政策運営を行っていくことが不可欠です。とりわけ、不良債権の最終処理の進展に伴って金融機関の損失処理の負担がかさんでくること、2002年4月に予定されているペイオフの凍結解除などにより、「2月危機」あるいは「3月危機」がマスコミにより喧伝されています。こうした風評を抑えるためにも、政府として、引き続き日銀が経済情勢に即応した適切な量的金融緩和政策を推進していくとともに、金融機関に対する公的資金の再注入を含む、柔軟かつ万全な金融政策運営を期していくことが不可欠です。 ③ また、失業率が5%を大きく超える(2001年12月5.56%)という危機的な雇用情勢に陥っていますが、金属労協がこれまで提案してきた雇用のセーフティーネットの三本柱、すなわち、 ① 日経連は、
と指摘していますが、まさに民間主導の内需拡大こそ、労使の果たすべき喫緊の課題です。 わが国経済に立ちはだかる当面の敵は、デフレ(継続的な物価下落)です。デフレは日経連が主張するように、
ものであると同時に、わが国にとって不可欠な構造改革の痛みを増し、その推進を妨げる要因ともなっています。 ② デフレは、基本的には中央銀行(日銀)から市場に供給される通貨が不足することによって発生する需要不足が根本的な原因ですから、量的金融緩和政策がまず第一段階の解決策となります。前述のとおり、量的金融緩和については、ようやく相当の水準まできていますので、これが効力を発揮するよう、今度は実体経済面での需要の後押しが重要となります。 ③ 現在のデフレは、グローバル経済化によるものであるから不可避である、との見方があります。グローバル化でデフレになるのならば、極端にいえば世界中でデフレになるはずですが、実際には、主要国でデフレになっているのは日本だけです。 ④ 一方、金属産業が供給する耐久消費財のうち、総務庁・家計調査(全国全世帯)において、購入数量が発表されている14品目に関し、消費者物価上昇率がマイナスに転ずる前の98年と直近の2000年について、この間の購入数量の変化と単価の変化の関係を見てみると、総じて購入数量の減少率が大きい耐久消費財ほど、単価の下落率が大きいという状況にあることが確認できます。個別の品目の価格動向を見ても、価格下落の原因が供給サイドにあるのではなく、需要サイド(需要過少)にあることは明らかです。(図表12) ⑤ デフレについて日経連は、
と分析していますが、問題なのは「需要過少」です。需要過少を解消するために、経営側として何をすべきかという点について、日経連は明確な姿勢、有効な対策を打ち出しているとはいえません。 ① 日経連が需要過少の解消策として主張しているのは、 ② 後者、すなわち雇用の維持・創出と雇用不安の解消は、需要過少の解消にとって、決定的に重要です。ところが一方で日経連は、
と主張、雇用の維持・創出のためのさまざまな施策も、
との考え方を示しており、 ○雇用の維持・創出と総額人件費の抑制を両立させる。 ○そのために、「雇用形態の多様化」を図る。 ことを強く打ち出しています。 ③ しかしながら、 ① 日経連は、
と指摘しています。 「負の相関関係」にあるならば、景気後退、いわんや現在のような経済規模が縮小している場合には、労働分配率は上昇して当然です。本来ならば、不況期には労働分配率が上昇することによって、個人消費が底支えされ、景気の底割れを防ぐことができる(経済のビルトインスタビライザー効果)のです。 ② GDPベースの労働分配率(雇用者1人あたり名目雇用者報酬/就業者1人あたり名目GDP)は、2001年4~9月期(季節調整値)で65.8%となっています。これは99年度の65.3%、2000年度の65.6%に比べれば若干上昇しているものの、90年代以降では、この両年以外では最も低い水準であり、労働分配率は90年代を通じて低下してきた、と判断することができます。長期的に見ても、1960年代以来、戦後最長の景気拡大であった「いざなぎ景気」の末期を除けば、最も低いレベルであり、まさに歴史的低水準となっています。(図表13) ③ 日経連はアメリカの労働分配率について、
と指摘しています。もし仮に、日経連がアメリカ的な景気変動に応じた雇用調整を望んでいるのだとすれば、いくら「雇用の維持・創出」を主張しても、まったく信用できないということになります。 いずれにしても、アメリカでは不況期に雇用調整を行うだけでなく、経済が拡大した時にはそれに見合った成果配分がきちんと行われているからこそ、好況時でも労働分配率が低下しないという側面があることを忘れてはなりません。 ④ GDPベースの労働分配率を国際比較してみると、製造業では日本の59.4%に対し、フランス63.0%、アメリカ64.5%、イタリア67.5%、ドイツ74.7%となっています(アメリカ97年、他は99年)。主要国のなかでは、わが国の労働分配率は飛び抜けて低く、わが国の人件費は割安であるといえます。 ⑤ 日経連が、雇用の維持・創出のためにあくまで総額人件費を増やすつもりはないというのならば、それは企業が、わが国の経済再生のための負担を分かち合うつもりはないといっているのと同じです。日経連のこのような姿勢は、厳しい経済環境のなかにあっても、日夜、業績の回復、生産性の向上、新分野の開拓に向けた血のにじむ努力を重ねている勤労者を踏みにじるものであり、まさに言語道断であります。 ① 日経連は2002年闘争の賃金交渉にあたり、
との方針を打ち出しています。すなわち今次闘争に際しては、 ○ベア見送り ○場合によっては定昇の凍結・見直し ○さらには緊急避難的なワークシェアリング という三種の対応を提案していることになります。 ② ベースアップは、個別企業労使が交渉のなかで論議を尽くして決定すべきものであり、経営者団体が「国際競争力の維持という観点からは論外」などと斬って捨てることができる筋合いのものではありません。経営者団体として、企業に対し交渉の拒絶を勧めるかのごとき物言いは、不見識極まりないといわざるをえません。 ③ また定昇についても、そもそも定昇は企業経営において年に一度実施することが織り込まれた制度であり、勤労者と企業の間で履行が約策された契約です。それを凍結するということがどういうことなのか、まったく理解に苦しみます。「経営の苦しい企業は電力料金を支払うな」と言っているのと一緒で、そんな理屈が通るわけがありません。 ④ 日経連は法定産業別最低賃金についても、「地域別最低賃金に屋上屋を架す産業別最低賃金も廃止すべきである」と主張しています。 ① いずれにしても、ベアは論外などという方針は、日経連が自ら主張する
という考え方とも、明らかに矛盾するものです。「横並び的賃金決定」を繰り返し非難する日経連が、むしろ自分から横並びベアゼロを主張することは、あまりにも節操がないといわなければなりません。 ② たとえば、99年における金属産業全体の労働分配率(GDPベース)は、65.2%ですが、輸送用機械製造業は54.9%と際立って低い状況にあります。前述のとおり、金属産業平均の労働分配率は、全産業平均や製造業平均を上回るのが普通ですが、わが国の輸送用機械製造業は、全産業平均、製造業平均を下回っています。ここ数年のうち労働分配率がもっとも高かった97年(62.1%)と比べると、この間、付加価値生産性(就業者1人あたり名目GDP)は12.5%も増加していますが、雇用者1人あたり名目雇用者報酬の増加率は、逆に△0.5%のマイナスとなっています。(図表15) ③ いまなすべきことは、まず第一に、経営側が企業内における雇用を維持するという決意を断固として示すことです。雇用安定宣言なり、労使共同宣言なりを締結することは、雇用不安の解消という点できわめて効果的であるといえます。 ① 日経連は、
などと主張しています。 しかしながら、わが国の賃金水準は新興工業国や発展途上国に比べれば高いものの、先進国のなかではむしろ中位にすぎず、とても世界のトップクラスとはいえません。 ② 日経連のデータでは、2000年における製造業・生産労働者の時間あたり賃金は、日本を100とするとアメリカ79、ドイツ90となっており、日本は両国を大きく上回っています。 ③ ILOの資料(1999KILM)によれば、オーストリア、ベルギー、デンマーク、フィンランド、ドイツ、ルクセンブルグ、オランダ、ノルウェー、スウェーデン、スイスなどが、日本よりも時間あたり人件費の高い国ですが、注目すべきは、これらの国々でも、製造業の企業が高い国際競争力を保持し、国内の生産基盤を維持し続けているということです。 ④ 現在の企業業績の不振には、金融環境、政府の失敗、中国の台頭といった外的要因ばかりでなく、収益確保のための負担を総額人件費削減のかたちで一方的に勤労者に押しつけてきたという点で、経営側として反省すべき点があるのではないかと考えられます。日本企業でも、業績好調で国際競争力の強い企業には、格付機関からの批判にも負けず長期安定雇用を重視し、賃金水準も産業内で相対的に優位にある企業が目につきます。
① 日経連は、
などと主張しています。 確かにエネルギー分野などにおいて、国内の価格が国際的に見て異常に高いものがあります。例えば経産省調べでは、産業用電力はドイツの2.1倍、アメリカの4.4 倍、産業用重油はドイツの1.9倍、フランスの1.6倍、家庭用天然ガスがドイツの3.0倍、フランスの3.3倍となっています。(図表17) そしてこうした高価格が、わが国ものづくり産業の国際競争力に打撃を与えていることは事実です。99年の通産省・工業統計表によれば、生産額に占める購入電力使用額は金属産業平均で1.1%となっており、なかでも鉄鋼業は3.6%、非鉄金属製造業は2.6%、金属製品製造業も1.4%に達しています。(図表18) ② エネルギー分野における異常な高価格の原因は、(今でも基本的には踏襲されている)総括原価方式に代表される高価格が設定できる料金制度、そして参入規制があるからです。こうした制度のために、金属産業の賃金水準をはるかに超える「生産性格差を反映しない人件費決定」が可能となったのであって、高賃金は原因ではなく、むしろ結果であるといえます。 ① 日経連は、
などと主張しています。求人充足率の低下とは、企業が求人を出しても就職しようという人がいない、採用できる能力の人がいない状態が多くなっていることを意味します。 ② 一方で日経連は、
とも指摘していますが、高付加価値分野への人材の移行とひとくちに言っても、一朝一夕にはできません。金属労協が提唱しているコミュニティ・スキルアップ・カレッジをはじめ、官民の枠、府省の枠を超えて教育訓練機関を総動員し、人手不足分野で活躍できる人材の育成、能力開発を進めていかなければなりません。 あわせて経営側としても、人手不足分野、高付加価値分野における賃金水準を引き上げ、そうした分野に関する能力開発の促進を図っていくべきであります。 ① 日経連は、
という認識を示しているものの、前述のとおり、消費拡大に対する有効な対策を打ち出していません。そして、
などと主張、賃上げの消費拡大効果を否定しています。 雇用環境が個人消費に大きな影響を与えることは確かですが、だからといって当面の所得環境、すなわち賃上げ・一時金が消費に与える影響を否定することは、明らかに誤りです。 たとえば、日経連は「名目」の数値である春季賃上げ率と「実質」消費との相関関係が希薄であると主張していますが、名目と実質の相関関係はナンセンスであり、名目同士、あるいは実質同士で比較すべきです。 例をあげると、仮に1%のデフレ下において、名目賃金水準が変わらず、その結果、名目消費水準も変わらなかった場合、実質消費は1%のプラスになります。日経連の考え方では、名目賃金はプラス・マイナスゼロ、実質消費はプラス1%で両者は関係ないということになりますが、実際には、名目賃金がゼロだったから名目消費もゼロで、そのために実質消費がプラス1%になったのです。名目賃金と名目消費との関係を見るべきであることは明らかです。 名目賃上げと名目消費との関係を見れば、ほぼ完全な相関関係にあることがわかります。総務省・家計調査の全国勤労者世帯において、最近5年間(97~2001年)の「世帯主の定期収入」と消費支出の名目増加率を比べてみると、その相関係数は実に0.95となっています。 ② 日経連は「実質消費支出増減率と雇用者数の増減率の推移」を比較し、「実質消費支出と雇用との間に強い相関関係があることが読み取れる」から、失業不安を取り除き、冷え込んだ消費マインドの改善をはかることが消費拡大に大きく寄与する、と主張しています。(手引きP.30) ① 日経連は、ワークシェアリングを
であると定義しています。 現在ワークシェアリングについては、連合・日経連・政府が三者で考え方を整理しているところですが、金属労協としても、雇用維持型・短期対応のワークシェアリングおよび雇用創出型・中長期のワークシェアリングについて、基本的な考え方を検討し、2月中には一定の整理を行う予定で準備を進めています。 ② しかしながら、雇用維持と称して労働時間短縮なしに賃金・労働条件の切り下げを行うことがワークシェアリングであるかのような混同が、一部で見られます。金属労協としては現時点において、とくに雇用維持型・短期対応のワークシェアリングについて、以下のような判断をしているところです。 ○日経連の定義でも示されているように、労働時間が短縮されなければワークシェアリングではない。とりわけ中小零細で未組織の企業においては、ワークシェアリングの名のもとに、安易な賃金・労働条件の切り下げが行われる懸念もあり、注意が必要である。 ③ 日経連はワークシェアリングにからみ、
と指摘しています。 同時に日経連は、「雇用のポートフォリオ」(後述)の考え方のなかで、
と主張していますが、一般職・技能職・販売職を安易に時間給制に変更することは容認できません。とくに月給制・年俸制、時間給制という区分は、歴史的に身分制度と密接に結びついてきました。わが国ではいま、所得・資産・教育などの点で格差の拡大、階層の固定化が懸念されるところとなっており、そのような流れを助長することのないよう、留意していかなければなりません。 ① 日経連は、
と主張し、中長期的には、 ワークシェアリング=雇用形態の多様化 と位置づけています。 日経連が95年5月に発表した「新時代の日本的経営」では、
という「雇用のポートフォリオ」の考え方を打ち出し、いわゆる幹部社員以外の専門職、一般職、技能職については、テンポラリー雇用とすることを主張していますが、ワークシェアリングの流れのなかで、専門職、一般職、技能職のテンポラリー化を一層加速しようとしている、といえます。 ② 雇用形態の多様化について日経連は、
と主張し、 ○勤労者の働き方の選択肢を増やす。 ○経営効率の向上と雇用コストの軽減。 を目的として掲げています。 ③ 今後「勤労者の働き方の選択肢」を増やすことは、きわめて重要です。ここで留意しなければならないことは、第一に、典型雇用を望む勤労者を、非典型雇用(テンポラリー雇用やパート・アルバイトなど)として雇用することになってはならない、ということです。あくまで「選択肢」を増やすのですから、典型雇用を望む者については、典型雇用で働けるようにしておかなければなりません。
と指摘しています。 しかしながら、同じ調査(厚労省・平成11年就業形態の多様化に関する総合実態調査報告)において、「正社員として働ける会社がなかったから」という回答も、契約社員の29.3%、派遣労働者の29.1%に達しており、契約社員として働いている理由の2番目、派遣労働者として働いている理由のトップにあがっていることもまた忘れてはなりません。 とりわけ若年層(15~19歳)の派遣労働者では、88.5%が「正社員として働ける会社がなかったから」を回答としてあげており、若年労働者のキャリア形成、生涯生活設計という点で、きわめて憂慮すべき事態であるといわざるをえません。 また、「正社員」で働いている人のうち、他の就業形態に変わりたいとする人は1.3%に止まっています。さらに、2001年8月の総務省・労働力調査特別調査によれば、失業者のうち派遣労働を望んでいる人は2.7%(女性3.7%)、失業者以外の非労働力人口(15歳以上で働いておらず、求職活動もしていない人)のうち、派遣労働ならば働くという人は0.2%とごくわずかです。 ④ なお、わが国では非典型雇用がすでに相当な割合に達していることも、非典型雇用の希望者の少ない理由になっている可能性があります。
① このような数値は、今後、経済情勢や非典型雇用に対する待遇・職場環境が改善すれば、変化することが十分考えられます。勤労者の選択肢を広げるためには、非典型雇用で働く勤労者が、公正・公平・安心感をもって働けるようにすることが重要です。 ② 完全失業率が急上昇するなかで、いわゆるオランダ・モデルが注目されています。日本とオランダでは国情の違い(たとえばオランダでは、製造業の比率が日本よりもかなり低い)もあり、オランダ・モデルをそのまま日本に移入できるとは考えられませんが、重要かつまた日本においても実現しなければならないのは、オランダでは典型雇用と非典型雇用において、「同一価値労働同一賃金」と解雇規制の同一化が実現されているとうことです。すなわち、オランダではパート労働というのは勤務時間の短い正社員である、ということになります。 ① わが国のものづくり産業をめぐる国際環境の厳しさとして、中国の存在があげられます。中国は2001年12月、いよいよWTOに加盟しましたが、低廉な生産コスト、巨大な将来市場に加え、生産技術や製品の品質が急速に向上してきていること、IT分野でのめざましい人材供給が見られることなどから、中国が21世紀における「世界の工場」として、巨大な存在感を示すようになってきています。 ② こうした状況のなかで、わが国企業の対中国直接投資は、減少傾向をたどってきました。製造業の直接投資額は、95年度に3,368億円を記録していましたが、その後ほぼ年を追って減少し、99年度には603億円と、95年度のわずか17.9%に止まる状況となっています。投資件数でも、95年度の675件に対し、99年度にはわずか59件に激減しています。2000年度には、それぞれ840億円、86件に若干回復したものの、これは電機産業の投資額が357億円、99年度の約5倍かつピークだった95年度(904億円)のほぼ4割の水準に回復していることによるものであり、電機産業以外の製造業では、投資額は2000年度も引き続き減少しています。(図表21) 2001年度については、大幅に拡大しているものと見られますが、一方で、わが国企業の対中国ビジネスについては、 ③ わが国の貿易収支の増加率は、2001年に輸出が前年比△5.1%、輸入が3.6%となっていますが、対中国貿易だけを取り出してみると、輸出が15.0%、輸入が18.3%となっています。対中国貿易は、日本の大幅な貿易赤字(2001年3.3兆円)ですが、ここ数年、輸出入の増加率が比較的拮抗する傾向が見られるようになっています。 ④ わが国金属産業における国内就業者数と、日系企業の海外従業員数とを比較してみると、国内就業者に対する海外従業員の比率は、91年に14.9%であったのが、2000年には28.3%と倍増していることがわかります。国内就業者の減少(△14.5%)と海外従業員の増加(62.2%)によるものですが、この傾向は金属産業の各業種にほぼ共通しています。 ⑤ 中国の賃金水準は、地域、産業、企業、職業などにより、ばらばらであると考えられますが、2000年における製造業の平均では、年収8,750元(約14万円)となっており、5年前(95年)の1.7倍となっています。とくに上海市では年収17,185元(約27.5万円)と全国平均のほぼ倍に達しています。今後、中国の為替レートが変動相場制に移行すれば、元高によるドル換算での賃金上昇という側面にも注意していく必要があります。(図表24) ① グローバル経済下にあって、金属産業は貿易立国たるわが国の基幹産業として、産業経済と国民生活の命運を握っている、といっても過言ではありません。
と主張していますが、この点では、われわれの考え方と合致しています。これまで蓄積してきた技術・技能、情報や知恵を継承・育成し、さらにITとの融合を図ることにより、世界市場をリードする製品を引き続き創出していかなければなりません。 ② しかしながら、同時に日経連が主張する「雇用のポートフォリオ」、すなわち長期雇用は一部幹部社員のみ、専門職、一般職、技能職は有期雇用とするやり方では、ものづくり産業における技術・技能、情報や知恵の継承・育成を行うことは到底不可能です。
ことは、この「ヒューマンな長期安定雇用」のもとでのみ、実現できるものです。 経営側も「ヒューマンな長期安定雇用」を基本とし、勤労者の選択の幅を広げるためのルールづくりを労使共同で進めていくよう、姿勢を転換すべきです。 ① 日経連は、
と主張しています。 経営者のモラルの低下が存在するとすれば、わが国産業経済の健全な発展にとって、きわめて憂慮すべきことといわなければなりません。また、産業・企業の業績や生産性を無視して、一律に「ベアは論外」、場合によっては定昇凍結も、というような姿勢では、業績回復、生産性向上に向けた従業員のモラール維持を図ることは到底不可能です。 ② 戦後最悪の大不況を打開し、日本経済の再生を図り、さらにわが国産業が世界市場のなかで冠たる地位を占めていくために、経営側は
との基本的な考え方に立脚し、
という主張を、具現化していかなければなりません。いまほど、
という日経連のスローガンが、求められている時はないといえます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
JAM型ワークシェアリングは、労働者が仕事を分ち合うことによって、労働者、企業、政府が雇用を維持する取り組みである。企業は、雇用を維持するとともに、労務費用の一部を負担し、政府は奨励金(仮称)を負担し、労働者は収入の一部を負担することによって仕事を分ち合うことになる。 1.1日あたりの労働時間短縮によるワークシェアリング 2.一時休業制度によるワークシェアリング |
|
|
| フランスの週労働35時間制 |
| ドイツ金属労組の時間短縮 |
| フォルクスワーゲン社のワークシェアリング |
| フォルクスワーゲン社の「5000×5000」モデル |
| オランダにおけるパートタイム労働 |
|
フランスでは、法定労働時間の短縮は、政府が週労働時間を39時間から35時間へ削減するとの発表を行った1997年以来雇用政策の中心となっていた。98年6月、企業もしくは産業分野レベルでの週35時間労働導入の交渉を労使に奨励するオブリ法が可決された。続いて2000年1月、新しい労働時間制度に関する詳細な条項を定めた第2次オブリ法が可決され、これらの法律により、21名以上規模の事業所には2000年2月から、20名以下規模の事業所には2002年1月から、週35時間労働が導入された。 ドイツのIGM(金属産業労組)の時短の取り組みは、84年2月より適用された産業別協約から始まった。この26カ月の協約では、85年4月よりそれまでの週40時間労働が、月例賃金の引き下げは行われずに38.5時間労働に短縮された。月例賃金補填のために時間あたり賃金が3.9%引き上げられ、これとは別に84年7月から3.3%、85年4月から2.0%、賃上げが行われた。これ以降も、時短によって月例賃金の減額は行われていない。 93年11月に合意された協約により、フォルクスワーゲン社は94年1月から2年間に限定し、週労働時間を36時間から28.8時間に7.2時間短縮した。これにより従業員102,000人のうち30,000人の削減が回避され、94年と95年の2年間については企業内の理由による解雇が回避された。 これは、フォルクスワーゲン社のミニバンを製造する新規のプロジェクトの立ち上げに際して、IGMがオート5000社との間で締結した協約を指す。この団体協約は4つの部分に分かれており、賃金・労働条件を定めた労働協約、資格制度合意、共同決定に関する合意およびフォルクスワーゲン経営協議会と共通の経営協議会設立に関する合意である。 労使は81年にパートタイムとフルタイム労働の平等処遇に関する全国枠組み協約に合意、産業別協約、企業別協約および個別の労働契約にこれを反映させてきている。また労使が参加している「労働財団」が、パートタイム労働の奨励を行っている。パートタイム労働の導入は、労働市場への女性参加の拡大、高齢労働者の就業促進、労働報酬の平等な分配、および失業の減少などを目的としている。 |