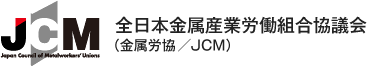�����J���͍�N12��2���J�Â̑�47�c�ψ���ɂ����āA2005�N�����ɗՂދ����J���̕��j�Ƃ��āu2005�N�����̐��i�v�����肵�A����Ɋ�Â��āA�i�b�e�Y�ʂ͂��ꂼ����g�݂�i�߂���܂��B
���{�o�ς́A����܂Ōi�C�������Ă��܂������A��������A�בւ̕s����ȓ����A�A�o�̐�s���s�������ȂǁA�i�C�̐�������܂邱�Ƃւ̌��O�ޗ����o�Ă��Ă��܂��B����A�����Y�Ƃ̊�ƋƐт͎Y�ƁE��Ƃɂ���ăo���c�L��������̂́A�j��ō��v�������܂���Ƃ��݂���ȂǁA�S�̂Ƃ��Ă͍D���ɐ��ڂ��Ă��܂��B
���{�̋����Y�Ƃ̋����͂́A���Y����ƌ����J������A�f�ނ╔�i�ɂ������֘A��ƂȂǂ���̂ƂȂ��������͂̋����ɂ���Ďx�����Ă��܂��B����Ƃ������Y�Ƃ����{�o�ς��x�����Y�ƂƂ��Ĕ��W���Ă������߂ɂ́A�Z�p�́E�J���́E����͂̈�w�̍��x����}��A�Ƒn�������߂Ȃ���Ǝ��̋Z�p�E�Z�\���p���E���W�����Ă����ƂƂ��ɁA�����Y�ƑS�̂��������Ă����Ȃ���Ȃ�܂���B
�������́A���������ϓ_����A���{�o�ς̐������ƋƐщ̐��ʂ��A�E����Ԃɉ����đ����J�������ɔ��f������ƂƂ��ɁA�����͂̌���ł���ΘJ�҂��\�͂����A��肪���������ē������Ƃ̂ł���A��Y�Ƃ�������Y�Ƃɂӂ��킵�����������̎������߂����āA�Y�ƊԁE�Y�Ɠ��̒����i�������Ɏ��g�ނ��ƂƂ��Ă��܂��B�����J�������̌��オ�A�E��g�����̊��͂����߂�ƂƂ��ɁA��Ƃ̐l�ފm�ۂɂ��Ȃ���A���ۋ����͂̋����ɂ��Ȃ���D�z�ݏo���Ȃ���Ȃ�܂���B
���́u2005�N�����~�j�����v�́A���c�ψ���ȍ~�̌o�ϓ�������{�o�c�A�u2005�N�Ōo�c�J������ψ���v�Ȃǂɂ�����o�c���̎咣�Ȃǂ܂��āA��A�E�P�g�ɂ�����c�̌��Ɍ�������b�����Ƃ��č쐬�������̂ł��B�܂��A���̃~�j�����́A���ۂɒc�̌��̂��߂̎����Â���ɂ�������A��A�E�P�g�̏��L�����邢�͒��������A�����������Ƃ������݂Ȃ����O���ɂ����č쐬���Ă��܂��B��Z�p�I�ȕ������܂܂�Ă��܂����A����ǂ̂����A���ꂼ��̏ɉ����Ă����p���������܂��悤�A���肢�\���グ�܂��B
�Q�O�O5�N�Q���Q��
�S���{�����Y�ƘJ���g�����c��
�@�@�@�i�h�l�e�|�i�b�j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����ǒ� ���@��@�v�@�� |
<�y�[�W�̃g�b�v��>
�|���{�o�c�A�u�o�c�J������ψ���v�ɑ��錩���|
2004 �N12 ��22 ��
�S���{�����Y�ƘJ���g�����c��
�i�h�l�e�|�i�b�j |
���{�o�c�A�́A12��14���A�u�o�c�J������ψ�����v�\���A�����J�g���ɗՂތo�c���̎p���𖾂炩�ɂ����B
�o�J�ϕł́A�u�J�g�ɂ��l�ޗ͂̈琬��������Ɣ��W�̌���v�Ƃ��Ă���B�������u����́v�̒ቺ�����O���A�u�l�ށv�u�m�I�n���v�̈ێ��E����̎��_�ɗ����Ă���ɂ�������炸�A�ٗp�A�����Ɋւ���o�c���̍l�����́A�ނ���u����́v�ቺ�����������˂Ȃ��ƌ��킴��Ȃ��B
�ٗp�̈���A�����ȘJ�������̊m���A����E�P���̏[���ȂǁA�����҂̍v���ɕA��肪�������߂邽�߂ɁA��Ǝ�����H���ׂ��ۑ�͑����B�u�l�v��P�Ȃ�o�c�����ƌ��邱�ƂȂ��A�u�l�v�����Y�Ƃ��Ċ������A����͂����߂�ׂ��A�ȉ��̏��_�ɂ��Č������������ƂƂ���B
�P�D�u����́v�̕����E����ɂ���
�o�J�ϕł́A�u�w�R�̉ߏ�x�i�ݔ��A���A�ٗp�j�������̕����ɐi�݂���v�Ƃ̔F���������Ă���B�������Ȃ���A���̌��ʁA�ٗp�͌������A�J�������̎����傫���ቺ�����B����́A�l���팸���ɂ���ĐE��v�����M���M���̏ƂȂ��Ă��邽�߂ɁA�J���̉ߖ�����A�R�~���j�P�[�V�����s���������N�����A����E�P���̋@��̂�Ƃ��r�����Ă���B����ɁA�o�c���F������ȏ�Ɍٗp�`�Ԃ����l�����A�E��ɂ���Ă͔�T�^�ٗp�҂��ߔ����߂Ă��邱�Ƃ�����A�Z�p�E�Z�\�̌p���E�琬���s�\���ɂȂ��Ă���B�����������Ƃ��A�E��ЊQ�̑����Ȃǂɂ������u����́v�̒ቺ�������炵�Ă��邱�Ƃ́A���{�o�c�A���w�E���Ă���ʂ�ł���B�P�Ɂu�w�����`�x�̊m���ƓO��v�u�g�D�ɑ���ӔC���A�g�D���x�������Ƃ��Ă̗ϗ��ς�O��v���邱�Ƃʼn����ł�����̂ł͂Ȃ��B
�����J���ł́A�����������Ԃ܂��A36������ʏ����̌������ɔ����v���m�ۂ��܂߂����g�݂̋�����A��T�^�ٗp�Ҏ���ɂ������Ă̘J�g���c�̏[����}�邱�ƂƂ����B����I�ɘJ�g���c���s���̐��𐮂��A�E��Ŕ������Ă�����_�A�J�����Ԃ⓭�����̂�����A�E��̒����ێ�����S�m�ۂȂǂɂ��Ę_�c��[�߂邱�Ƃ��A����͂̌���ɂ͕s���ł���B
�����ɁA��T�^�J���҂��܂߂�����͂����シ�邽�߂ɁA���������̊m�����}��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�u����́v���������A��Ƃ̋����͂����߂邽�߂ɂ́A�q���[�}���Ȓ�������ٗp����{�Ƃ��Ȃ���A�����I�Ȏ���ɗ������l�ވ琬��}���Ă������Ƃ��K�v�ł���B��Ǝ���A�ٗp�̈���Ƌ���E�P���̏[����}��A�����҂��\�͂����邱�Ƃ��ł�������\�z���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�Q�D��������̂����
�n���I�Z�p�A�m�I�n�����ێ��E���シ�邽�߂ɂ́A�u�w�͂���Ε����v���Ƃ��X�l�̒��������Ŏ����ł��邱�Ƃ����ł���A�����ɂ킽����肵�����������ʂ��邱�Ƃ��d�v�ł���B
�u�x�[�X�A�b�v�v�ɂ��ẮA����܂ł��e��ƘJ�g���A�������܂߂��o�Ϗ�A�Y�ƁE��Ƃ̓����A�������A�Љ�I�����������Ƃ̒������ԁE����ׂ��p�܂����A�^���Șb�������ɂ���āA�x�A�̗L�����܂߂���������A�z���̂���������肵�Ă����B�Y�ƊԁA�Y�Ɠ��̒����i�����g�傷�����ŁA��ƋƐт����Ă��錻�݁A��ƘJ�g�̎���I�Ȓ�������d���邱�Ƃ��A���{�o�ς̔��W�̂��߂ɂ��K�v�ƂȂ��Ă���B
���{�o�c�A�́A�u�s�ꉡ�f�I�ȉ����сv�u�S�]�ƈ��̒����J�[�u�̖��N�̈ꗥ�I��グ�v�Ƃ������R�ɂ���āA�x�[�X�A�b�v��ے肵�Ă��邪�A���̂��Ƃ��A���ʔz���̎Љ�����ے肵�Ă���̂ł���A�e�F���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
���l�ɁA����������x�ɂ��Ă��u�p�~���܂߂Đ��x�̔��{�I���v���}���ׂ��v�Ǝ咣���Ă��邪�A�ʊ�Ƃ̎d���⓭�����̎��Ԃ܂��Đ��x�������Ă������̂ł���A�N��E�Α��N�����d�����������������������ŗL���ɋ@�\���Ă���B�܂��A�N��Ƃ̐��v��̈Ⴂ��W���I�ȃX�L���p�X�͑��݂��Ă���A����ɉ��������x�I�����̎d�g�݂��s���ł���B
�Ȃ��A�o�J�ϕŁu��ƋK�͂��������Ȃ�ɂ�ĕt�����l�ɐ�߂�l����i�J�����z���j�̔䗦�͍����Ȃ��Ă���B��ƋK�́E��Ƒ̎��Ɍ���������������́A�o�c�̍����ɂ��������ł���v�Ƃ��Ă��邪�A��ƋK�݂͂̂ňꗥ�I�ɒ����̗}����}�邩�̂悤�Ȏ咣�����邱�Ƃ͔F�߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�����āA���z�l����̗}����ړI�ɁA���ʎ�`���������邱�Ƃ͗e�F�ł��Ȃ��B
�R�D�����I�ȘJ�������̐����E���P�ƘJ���@���ւ̑Ή�
�o�J�ϕł́A�J���@���́u��w�̋K�����v�E�ɘa�v���咣���Ă��邪�A�J������̋K���ɘa�́A�ٗp�̈���Ȃ��A�J�������̈����������A�K�w������������݂̂ł���B�܂��A��T�^�J���҂̐�����s����ɂ��A�j�[�g�⏭�q���̈���Ƃ��Ȃ��Ă��邱�Ƃɂ����ӂ��ׂ��ł���B���݂̘J���@���́A�o�ρE�Љ�⓭�����̕ω��ւ̑Ή����s�\���ł���A�ނ���A�ω��ɑΉ������Z�[�t�e�B�l�b�g���������Ă����K�v������B���肵���ٗp�̊g��Ɍ����āA�J�g���p�m���X���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�����J���ł́A���q�E����̐i�W�ȂǁA�o�ρE�Љ�̕ω��ɑΉ������A�Љ�I�ɋ��ʉ����ׂ������J�������̍\�z���߂����Ă���B�J�����Ԃ⓭�����A�d���Ɖƒ�̗����x���A60�Έȍ~�̏A�J�m�ۂȂǁA���܂��܂ȉۑ�ɂ��āA��ƘJ�g���炪���悵�ĘJ�����������m�����A����ɎЉ�S�̂ɔg�y�����Ă������Ƃ��K�v�ł���B
�S�D�J�����ԍs���ɑ���ᔻ�ɂ���
�o�J�ϕł́A�J�����ԂɊւ���ēs���ɂ��āA�ᔻ���s���Ă���B
�������Ȃ���A�ēs�����������ꂽ���R�ɂ́A�����s����w�i�Ƃ����l���팸�ɂ���Ē��ߘJ�������債�Ă��邱�Ƃ�A�s�����c�Ƃ����v����o�c�҂������ɑ��݂��邱�ƁA�ߘJ�����܂߂������^���w���X�̖�肪�[�������Ă��邱�ƂȂǂ̌�����B
���̂悤�ȏ̉��ł́A���{�o�c�A�̂����Љ�̈���тƂ��Ă̘J�g�̖������܂��ʂ������߂ɁA�s�����c�Ƃ̖o�ŁA�����ԘJ���̐�����}���Ă������Ƃ��K�v�ł���B�����������Ƃ́A��Ƃ肠�鐶�����Ԃ̊m�ۂɂ���Ďd���Ɛ����̒��a��}��A���ꂩ��̐V���ȃ��C�t�X�^�C�����\�z����ϓ_������d�v�ƂȂ��Ă���B
�T�D�i���̊g��A�J���҂̊K�w�����Ɏ��~�߂�
�u���l�Ȍٗp�`�Ԃ��œK�ɑg�ݍ��킹�A���ω��ւ̏_��ȑΏ��Ɗ�Ƃ̋����͂̋�������
�}�����v���̂ł���u�ٗp�̃|�[�g�t�H���I�v�́A�ΘJ�҂̐�����s����ɂ��A�J�������̊i���g��������炵�A�K�w�����𐄂��i�߂Ă���B�u�\�́E���ʁE�v���x�v�݂̂����������������x�́A�����̈����A�Љ�I�Ȍ����̎��_�������Ă���B
�����J���ł́A�u�i�b�~�j�}���^���̐��i�v�ɂ���Ē����̉��x����}��A�E������m�ɂ��Ȃ���d����������d�������u�傭����E��ʂ̒��������`���v�ɂ���āA�����Y�Ƃɂӂ��킵�����������̎�����}�邱�ƂƂ��Ă���B�����A�J�������́A�����Ŕ[�����̂��鐧�x�Ɛ����̊m�����s���ł���B
�܂��A���{�o�c�A���A�Y�ƕʍŒ�����ɂ��āA�u���㉮���˂��v�Ƃ��āu�p�~���ׂ��v�Ƃ���p���͗e�F�ł��Ȃ��B�Y�ƕʍŒ�����́A�n��ʍŒ�����Ƃ͓K�p�Ώۂ��قȂ邱�Ƃ͂��Ƃ��A�Y�ƘJ�g�̍��ӂɂ���āA�����Ȓ������������o�����Ƃ������O�Ɋ�Â����̂ł���A���̈Ӗ��Œn��ʍŒ�����Ƃ͈قȂ������S�������x�ł���B���������̊m�ہA�Y�Ɠ��̒����i�������̊ϓ_������d�v�Ȗ�����S���Ă���A����Ƃ��p���E���W��}��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
<�y�[�W�̃g�b�v��>
�P�D�ΘJ�҂ɑ���K���Ȑ��ʔz����
�����J���́A���{�o�ς̐������ƋƐщ̐��ʂ�E����Ԃɉ����đ����J�������ɔ��f������ƂƂ��ɁA�����͂̌���ł���ΘJ�҂��\�͂����A��肪���������ē������Ƃ̂ł���A��Y�Ƃ�������Y�Ƃɂӂ��킵�����������̎������߂����āA�Y�ƊԁE�Y�Ɠ��̒����i�������Ɏ��g��ł��܂��B
1990�N��ȍ~�A�����Ɏ���܂ŁA�����o�σx�[�X�̘J�����z���͒ቺ�X���𑱂��Ă���A2003�N�x�ɂ͓��v�J�n�ȗ��Œ�ƂȂ��Ă��܂��B�J�����z���ቺ�́A�ΘJ�҂̎Y�ݏo�����t�����l�ɔ�ׁA�ΘJ�҂ւ̐��ʔz�������ΓI�ɒ�ʂƂȂ��Ă��邱�Ƃ������܂��B�J�����z���͕s�����ɏ㏸���A�D�����ɒቺ����X��������܂����A�킪�������ň��̕s���Ɋׂ�A���ڂf�c�o�̃}�C�i�X�������Ԃ��A�ΘJ�҂ւ̔z���͂���ȏ�̃}�C�i�X�������Ă��܂����B�܂��z���\���̘c�݂��g�債�A�����E���Y�E����̊i���g��ɂ��K�w�̌Œ艻���i�s���Ă��܂��B
���{�o�c�A�́A2005�N�Ōo�c�J������ψ���i�ȉ��A�o�J�ϕj�ɂ����āA���ς�炸�A���{�S�̂̌o�Ϗ��炷��Β��グ�̗]�n�͂قƂ�ǂȂ��Ƃ����A�o�ς��ƋƐт͓̉����l�X�̓w�͂̐��ʂł����邩��A�Ɛт̉��݂����Ƃ́A�����l�̓w�͂ɑ��ĐϋɓI�ɕ�K�v������A�Z���I�Ȋ�ƋƐт̐��ʂ͈ꎞ���ւ̔��f���]�܂�邪�A�����ɂ��Ă��A�ʊ�Ƃɂ����Ċe�J�g�̐ӔC�̂��ƂŐ����������グ�邱�Ƃ͎��R�ł���A�Ǝw�E���Ă��܂��B
�����́A���������̍��۔�r�Ȃǂ���A���グ�̗]�n�͂قƂ�ǂȂ��Ƃ�����{�o�c�A�̔F���͌�������̂ł���A�ƍl���܂����A���Ȃ��Ƃ��������ɂ����āA�ΘJ�҂ւ̐��ʔz���̕K�v����ł��o�����_�͕]������Ƃ���ł��B�������A�Љ�S�̂ɂ����鐬�ʔz���̂�����A�Ƃ��ɓ��{�Љ�ɂ�����i���g��A�K�w�̌Œ艻�ɂ��Ă̖��ӎ����ł���_�ɂ��ẮA����߂Ė��ł��B
�ΘJ�҂��Y�ݏo�����t�����l�ɔ�ׂāA�ΘJ�҂ɑ���z�����ߏ��ł���A�K���Ȑ��ʔz��
���s���Ȃ���A�����i���̊g��A�O���哱�E�A�o�ˑ��A�~���ȂǁA�킪���o�ςɗl�X�Șc�݂������炵�A�Y�ƌo�ς̌��S�Ȕ��W�ƍ��������̈���E�����j�Q���A���q������ւ̑Ή����܂��܂�����ƂȂ��Ă����܂��B�����o�ς̊ϓ_�܂��A�e�Y�ƁE��Ƃ̎���ɑ����A�x�[�X�A�b�v�A�ꎞ���ɂ���āA�ΘJ�҂ւ̓K���Ȑ��ʔz�������߂Ă������Ƃ��d�v�ł��B
�Q�D�x�[�X�A�b�v�̈Ӌ`
�����J���ł́A����܂ŁA�o�ϐ����A���������A�ٗp��A�t�����l���Y���A�Y�Ɠ����A��ƋƐсA�����̎Љ�i�Љ�I�Ȓ�������A����������r�j�Ȃǂ𑍍����f������ŁA�Y�ƁE��Ƃ̎��Ԃ܂�������ׂ�����������ݒ肵�A���̎����̂��߂ɁA�J�g�̐^���Ș_�c�ɂ���āA�x�A�̗L����z���̂���������肵�Ă��܂����B
���{�o�c�A�́A�u�s�ꉡ�f�I�ȉ����сv�u�S�]�ƈ��̒����J�[�u�̖��N�̈ꗥ�I��グ�v�Ƃ����Ӗ��ł̃x�A��ے肵�Ă��܂����A���̂��Ƃ��A���ʔz���̎Љ�����ے肵�Ă���̂ł���A�e�F���邱�Ƃ͂ł��܂���B�x�A�́A��L�̂��܂��܂ȗv�f�f���āA�����\�������������Ƃł���A�����o�ς̓����f����x�A�̕����ɂ��ẮA�u�s�ꉡ�f�I�ȉ����сv���Ȃ킿�Љ�S�̂̓���I�ȃx�A�ƂȂ�͓̂��R�̂��Ƃł��B
�������Ȃ���A�x�[�X�A�b�v�̍\���v�f�͂��ꂾ���łȂ��A�����i�������A�Y�Ɠ������ƋƐт����f�����킯�ł�����A���S�Ɂu�s�ꉡ�f�I�ȉ����сv�ł͂��肦�܂���B�������N�̎��т����Ă��A�J�������������i�������A�Y�Ɠ������ƋƐтf�����x�[�X�A�b�v�����߂Ă���̂ɑ��A�ނ���o�c���̂ق��������A�u�x�A�[���Ƃ����s�ꉡ�f�I�ȉ����сv��}�낤�Ƃ��Ă��Ă��܂��B2005�N�����ɂ����ẮA���{�o�c�A�͊i�������̊ϓ_�Ȃǂ���x�[�X�A�b�v�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��A���邢�͎Y�Ɠ������ƋƐт̊ϓ_����x�[�X�A�b�v�̂ł�����ɂ����Ƃ́A�ϋɓI�Ƀx�[�X�A�b�v�����{����悤�w�����ׂ��ł���A�ʊ�Ƃ̌o�c��������������{�p���ɗ����Č��ɑΉ����ׂ��ł��B
�R�D�ቺ��������{�̐l�����
�����J���ł́A�����͂̌���ł���ΘJ�҂��\�͂��\���ɔ������A��肪���������ē������Ƃ̂ł���J�������肾�����Ƃ��K�v�ł���Ƃ����ϓ_�ɗ����āA���t�����l�ݏo�������Y�Ƃɂӂ��킵�������J�������m�����߂����Ă��܂��B
����A���{�o�c�A�́A�킪���̒����������u���ۓI�Ɍ��ăg�b�v���x���v�ł���Ƃ��āA����ȏ�̈����グ�͍���Ƃ��Ă��܂��B
�������Ȃ���A���{�o�c�A���咣�̍����Ƃ��Čf���Ă��鐔�l�́A�e���Œ�`�̈قȂ�f�[�^����ׂ����̂ł���A�������A�������^���z�ȊO�̐l������܂�ł��܂���B��`�𑵂��A��Ƃ̎Љ�ۏᕉ�S�╟���������܂߂��l����ō��۔�r����A�킪���̐����́A��i���̂Ȃ��Œ���ʂɗ�������ł��Ă���A���͂�u���ۓI�Ɍ��ăg�b�v���x���v�Ƃ͂����Ȃ��ɂ���܂��B
�u�����͐�i���Ԃł͂Ȃ��A�����ȂǐV���H�ƍ��Ƃ��Ă���̂��v�Ƃ�������������܂��B�������Ȃ���A�d�v�Ȃ̂͋ΘJ�҂��Y�ݏo�����t�����l�Ƃ̔�r�Ō����l����̑��ΓI�Ȑ����ł��B���Ȃ킿�u�t�����l������̐l����i���P�ʘJ���R�X�g�j�v�Ō���A�킪�������Y�Ƃł͂f�V�e���̂Ȃ��ōł������ł�����肩�A���Ƃ��ΗA���p�@�퐻���ƂȂǂł́A�؍��ɔ�ׂĂ��啝�Ɋ����ł���A�Ƃ������ʂɂȂ��Ă��܂��B
�S�D��������ٗp����b�Ƃ������ۋ����͂̋�����
�����J���ł́A�����Y�Ƃ̋����E���W�ɂ́A�����͂̌���ł���ΘJ�҂��\�͂��\���ɔ������A��肪���������ē������Ƃ̂ł���J���������������n��o�����Ƃ��K�v�ł���A�Ƃ̍l�����ɗ����āA�u�q���[�}���Ȓ�������ٗp�v�ɂ���ċΘJ�҂̌ٗp�Ɛ����̈����}�邱�Ƃ���{�ł���A�ƍl���Ă��܂��B
����A�o�J�ϕł́A�u����́v�͑����̐l�������Ԃɂ킽����H�I�Ȍo����ςݏd�ˁA�p���I�Ȓ~�ς�ʂ��ē�������̂ł���A�ٗp�ƘJ���������I�Ɉ��肳���Ă����A���S���āA���Ԃ������Ĕ\�́E�ӗ~�̌���Ɏ��g�ނ��Ƃ��ł���A�܂����{��Ƃ́A�]������u�l���ɂ���p���v���o�c�̍����ɐ����Ă������A���܂̂悤�Ȏ���ɂ����Ă��A�l�Ɛl�Ƃ̂Ȃ�����d���������{�I�o�c�̂悳���Ċm�F���ׂ��ł���A�ȂǂƎ咣���Ă���A���������l�����͂����Ɠ��l�ł��B�������Ȃ������A�������{�o�c�A���咣���Ă���u�ٗp�̃|�[�g�t�H���I�v�́A���������l�����Ƃ͑��e��Ȃ����̂ł��B
���E�e���ŁA�L���ٗp�̔䗦���g�債����܂����A�Ȃ��ł��킪���́A��i�����ōō������ƂȂ��Ă��܂��B�������p�[�g��h���œ��������Ƃ���ΘJ�҂̑��̃j�[�Y������܂����A����ŁA���Ј��Ƃ��ē������Ƃ��ł��Ȃ��������߂ɁA��ނ������L���ٗp�Ƃ��ē����Ă���ΘJ�҂��������Ƃ��ʼn߂��邱�Ƃ͂ł��܂���B
���̂Â���Y�ƁA�Ƃ�킯���E�Ő�[�̐V���i�����ЂŊJ�����Ă����ƁA���邢�͍��x�ȎC�荇�킹�Z�p�E�Z�\�A��肱�ݓ��̋Z�p�ɂ���āA���i���A���@�\���i�G�ɑg�ݍ��킹�Đ������Ă���悤�Ȋ�Ƃł́A�Z�\�E�A���E�ɂ��Ă��A��������ٗp����{�Ƃ��āA���x�n���̋Z�p�E�Z�\�A���邢�͌���̏���m�b�A�m�E�n�E�Ȃǂ�~�ς��Ă������Ƃ���ɕK�v�ł��B
�T�D�i�b�~�j�}���^���ɂ������̉��x��
���Ɨ��̍��~�܂��ٗp�`�Ԃ̑��l���ȂǁA�J���s���ٗp�\�����傫���ω����Ă���A���������ቺ������i���̈�w�̊g�傪���O�����ɂȂ��Ă��܂��B�t�G���������ɂ�鑊��g�y�͂���܂��Ă��邱�Ƃ�����A��Ɠ��ɂ��������������A���g�D�J���҂��܂߂��Љ�S�̂ɔg�y�����A�����Ȓ��������̊m���Ƌ����Y�Ƃɂ�������������̉��x����}�邱�Ƃ��d�v�ł��B�����J���ł́A���������ϓ_����A�i�b�~�j�}��(35��)�A�Œ��������A�@��Y�ƕʍŒ�����̎��g�݂ɂ���ċ����Y�ƑS�̂̒����̉��x����}���Ă����܂��B
�܂��A�@��Y�ƕʍŒ�����́A��I�J���҂ɓK�p�����Œ�����ł���A�S�Ă̘J���҂ɓK�p�����n��ʍŒ�����Ƃ́A�����E�@�\���قȂ鐧�x�ł��B���g�D�J���҂ɂ��K�p�����A�u�킪���B��Ƃ��������Ƃ̘g�����Y�ƕʘJ����������V�X�e���v�ł���A�u�Y�ƕʂɌ`�����������̉��x���v�Ɓu���������̊m�ہv�Ƃ��������E�@�\�����ׂ��A����Ƃ��p���E���W��}���Ă����Ȃ���Ȃ�܂���B
�U�D�������x�����Ƃ����鐬�ʎ�`�����Ɋւ���
�����J���́A�����鐬�ʎ�`�����Ɋւ��āA
���P�ɐl����}���Ɏ���u�������x������s���A�����[���ێ��A�Z�p�E�Z�\�̌p���E�琬���낤������B
�������E�������x����ɂ������ẮA�J���g�������x�v�E�^�p�E�����ȂNJe�i�K�ŐϋɓI�Ɋ֗^���A�d���̔\�́E���ʂ�K���ɔ��f������A�����Ŕ[�����̍������x�m�����d�v�ł���B
�Ȃǂ̍l�����咣���Ă��܂����B
����A�o�J�ϕɂ����Ă��A�]����̍������E�q�ϐ��m�ہA�ΘJ�҂̒����I�ȃe�[�}�ւ̎��g�݂⍢��ȉۑ�ւ̃`�������W�̕]���A���Ђ̐g�̏�ɂ��������x�̍\�z�ȂǁA��̓I�ȉ��P�̕�������������܂����B�������A����܂ŁA�o�J�ϕ̎咣�ɉ����Ă����鐬�ʎ�`�Ȃ�������x�։��肵����Ƃɂ����ẮA�E��̎��Ԃ��������x�̓����Ȃǂɂ���č������������������Ȃ�����܂���B���{�o�c�A�́A�ނ���A����̉��P�̕������ɂ��ĐӔC�������Đ��i����K�v������܂��B�Ƃ��ɁA�������x����������Ă��Ȃ�������Ƃɂ����ẮA�E��̎��Ԃ܂��Ȃ���A���x�̐v�A�^�p�A�����̊e�i�K�ŁA�J�g���͂������g�݂����グ��悤�ɂ��ׂ��ł��B
�V�D�����ԉ�����J������
�����J���ł́A�u��Q�������E�J������v�ɂ����āA�u�d���E�Љ�E�ƒ됶���̒��a�v��ł��o���A�N�ԑ����J������1,800���Ԃ̑��������ɂ��A��Ƃ肠�鐶�����Ԃ̊m�ۂ��咣���Ă��܂��B�������Ȃ���A�ߔN�A����O�J�����Ԃ̑����A�N���L���x�ɂ̎擾���̒ቺ�ɂ��A�����Y�Ƃ̘J�����Ԃ͔N�ԑ����J�����Ԃ�2,000���Ԃ���Ƃ����R�X�����ɗ��������Ă��܂��B36����̓��ʏ����̌������ւ̑Ή����܂߁A�v���z�u���܂߂��J�����ԒZ�k�̎��g�݂��������Ă����Ȃ���Ȃ�܂���B
���{�o�c�A�́A�o�J�ϕɂ����āA�J�����ԊǗ�������}������J���Ȃ̎{��������ᔻ����ƂƂ��ɁA�z���C�g�J���[�E�G�O�[���v�V�����̓������咣���Ă��܂��B�������Ȃ���A�J���@�ɂ��J�����Ԃ̋K���́A�����ԘJ����h�~���邱�Ƃɖ{���̎�|������A����ɂ���Đl�Ԃ炵���J�������Ɛ�����ۏႷ����̂ł��B���ߘJ���蓖�̎x�����ƁA�J�����ԊǗ��͕ʂ̖��ł���A�ΘJ�҂����N���ێ����A�ʏ�̌l�����A�ƒ됶���A�Љ���������邽�߂ɂ́A�J�����Ԃɂ͈��̘g���K�v�ł��B���ߘJ�����P��I�ɍs���A�J�����ԊǗ����s�O��ŁA�s�����c�Ƃ����݂������A�N�x�����S�擾�ł��Ȃ��悤�ȏ̂��Ƃł́A�z���C�g�J���[�E�G�O�[���v�V�����̓�����F�߂邱�Ƃ͂ł��܂���B
�W�D�d���Ɖƒ�̗����x���̂��߂̎�����琬�x�������i�@�A�玙�E���x�Ɩ@�ւ̑Ή�
2002�N�X���Ɍ����J���Ȃ��Ƃ�܂Ƃ߂��u���q����v���X�����v�ł́A�u�q��ĂƎd���̗����x���v���S�̏]���̎��g�݂ɉ����A�u�j�����܂߂��������̌������v���̎��_���܂߂āA�����I�Ȏ��g�݂��i�߂��邱�ƂɂȂ�܂����B����܂���2003�N�V���ɐ��������u������琬�x�������i�@�v�ł́A�e��Ƃɑ��āA�q��Ă͒j�������͂��čs���ׂ����̂Ƃ̎��_�ɗ����A�d���Ɖƒ�̗����x���̂��߂̐��x�����݂̂Ȃ炸�A���ߘJ���̍팸�ȂǓ������̌������Ɏ����鑽�l�ȘJ�������̐��������߂Ă��܂��B�u������琬�x�������i�@�v�ł́A301�l�ȏ���ٗp���鎖�Ǝ�ɑ��āA�u�s���v��v�̒�o���`���Â��Ă���A300�l�ȉ��̊�Ƃɂ��Ă��A���l�̓w�͋`��������Ƃ��Ă��܂��B���q����Ƃ��Ď������̂��鐧�x�Ƃ��邽�߂ɂ́A�u�s���v��v�̗��āA���{�ɘJ���g�����ϋɓI�ɎQ�����A�ΘJ�҂̈ӌ��f���Ă����K�v������܂��B
�܂��A2005�N�S���P������́A�u�����玙�E���x�Ɩ@�v���{�s����܂��B�d���Ɖƒ�̗�����}�邱�Ƃ̂ł���ϓ_����A�ΘJ�҂̃j�[�Y���Ƃ̎��Ԃ܂��A�@�����鐧�x������^�p�̉��P��}���Ă������Ƃ��߂����Ă����܂��B
�X�D����Ҍٗp����@�̉�����60�Έȍ~�̏A�J�m��
�����J���ł́A�N�����z�x���J�n�N��Ƃ̐ڑ��ɂ�鐶�v��̊m�ہA�Z�p�E�Z�\�̌p���E�琬�ɂ��Y�ƁE��Ɗ�Ղ̋����A�Ƃ��ɎЉ���x���A���������Ƃ�������Ґ�������������ϓ_����60�Έȍ~�̏A�J�m�ۂɎ��g��ł��܂����B60�Έȍ~�A�J�m�ۂ̂R�����Ƃ��āA�@�������Ƃ���]������̂́A�N�ł������邱�ƁA�A�N�����z�x���J�n�N��Ɛڑ����邱�ƁA�B60�Έȍ~�A�J������̂ɂ��ẮA���������g�D����}�邱�ƁA���f���āA���g�݂�i�߂Ă��܂��B
2006�N�S������A65�܂ł̌p���ٗp���x�̓����i2013�N�܂łɒi�K�I�����グ�j�𒌂Ƃ����������Ҍٗp����@���{�s����܂��B�J�g����ɂ���āA�p���ٗp���x�̑ΏۂƂȂ�J���҂Ɋւ�����߂邱�Ƃ��ł���Ƃ���Ă��܂����A�@�̎�|�܂��Ȃ���A60�Έȍ~�A�J�̂R�����Ɋ�Â������x�𑁊��ɓ������Ă������Ƃ��K�v�ł��B
10�D�i���̊g��ƌl����̓���
�ߔN�A�킪���ɂ����鏊���E���Y�E����̊i�����g�債�A���̂��Ƃ��ΘJ�҂̌ٗp�Ɛ����ɑ��鏫���s���������A���������S�̂̈���ƌ�����낤���������łȂ��A�킪���̊��͂����킹�A�Y�ƌo�ς̌��S�Ȕ��W��j�Q���邱�Ƃ����O����Ă��܂��B
�킪���̋��݁A�Ƃ�킯�����Y�Ƃ𒆐S�Ƃ�����̂Â���Y�Ƃ̋��݂́A����̗͂ɂ���킯�ł�����A������������̊��͂�r��������i���g��͑S���̌��ł��B
���̂Ƃ������͉�ƂȂ��Ă��܂����A�����K�w�ʂɌ���A���������w�Ŏ����E�����E����啝���ƂȂ��Ă������A��������w�ł́A�����Ȃ����قƂ�lj����Ɏ~�܂��Ă��܂��B�������w�ł́A����̐L�ї��������̐L�ї��������Ă��܂����A�����������ۂ́A����܂ʼn䖝�����Ă�������A�������̉��P�ɂ��A��C�ɉ��������ꂽ�ɂ��邱�Ƃ������Ă��܂��B�i���k���ɂ���āA�L���ΘJ�ґS�̂̎����E�����̑�����}��A�ٗp�Ɛ����ɑ��鏫���s���@���āA���̍L������I�ȏ���g����������Ă����Ȃ���Ȃ�܂���B
11�D�b�r�q�i��Ƃ̎Љ�I�ӔC�j�ƒ����E�J����������
�����J���́u�b�r�q���i�ɂ�����J���g���̖����Ɋւ���v�����肵�A��Ƃłb�r�q�����H����u��́v�ł������łȂ��A�ł��d�v�ȃX�e�[�N�z���_�[�ł���]�ƈ��̑�\����J���g�����A�b�r�q�̐��i�ɐϋɓI�ɎQ�悵�Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ��咣���Ă��܂��B
��̓I�ɂ́A�b�r�q�Ɋւ���Г��̐��Â����A�Г��̐��̌������ɘJ���g�����Q�悷��ƂƂ��ɁA�b�r�q�ψ���ȂǎГ����f�I�Ȉψ���ɘJ���g���̑�\���Q������A���j�^�����O�ɂ��Ă��J�g�A�g��}�邱�ƂȂǂ��s���ł��B
���������Ȃ��ŁA���{�o�c�A���o�J�ϕɂ����Ăb�r�q�Ɋւ��ĐG��Ă��邱�Ƃ́A�����]���ł��܂��B�R���v���C�A���X�i�@�ߏ���j�A�r�W�l�X�E�G�V�b�N�X�i��Ɨϗ��j����łȂ��A���ꂩ��̒����E�J�������̂���l�ɂ����Ă��A�b�r�q�̊ϓ_���s��������ł��B
���ǁA�ΘJ�҂Ɋւ��b�r�q�ł����Ƃ��d�v�Ȃ��Ƃ́A�J����@���͂��߂Ƃ���J���@�K�����炵�A�C�O�̎��Ƌ��_���܂߂āA��{�I�l���A���j�I�J��������炵�A�]�ƈ��ɑ��ēK���Ȑ��ʔz����}�邱�ƁA�˂ɒ����E�J�������A�E����̌�����߂����Ă������ƁA�ł���Ƃ����܂��B
12�D���߂̌o�Ϗ
�킪���o�ς́A2002�N�t�ȍ~�A�i�C�𑱂��Ă��܂������A2004�N�Ă�����A���R���̗A�����i�̍�����V��s���ɂ�鐶�N�H�i�̒l�オ��ɑΉ������A����ɂ�鎖����̋��Z�������߂Ȃǂ�w�i�ɁA��⌸������������Ƃ���ƂȂ��Ă��܂��B�������Ȃ���A�i�C�w�W�̗������݂͔�r�I�y���Ɏ~�܂��Ă���A���₩�ȉ����҂����Ƃ���ƂȂ��Ă��܂��B
���{�o�ό��ʂ��ɂ��ƁA���ڂf�c�o��������2004�N�x���ь����݂�0.8���A2005�N�x���ʂ���1.3���ƂȂ��Ă��܂��B
�����́A�A�������̍����������A������ƕ����㏸���͂Q�����x�Ő��ڂ��Ă��܂��B�������Ȃ���A���������͏���ҕ����ɂ͔g�y���Ă��炸�A����ҕ����㏸����2004�N10������12���܂ł́A���N�H�i�̒l�オ��ɂ���ăv���X�ƂȂ��Ă������̂́A2005�N�P���ɂ͍Ăу}�C�i�X�ɓ]���Ă��܂��B
2004�N12���̊��S���Ɨ���4.43���Ɖ��P�X���������Ă��܂����A�ˑR�Ƃ��č������ƂȂ��Ă��܂��B�܂��A���S���Ɨ��̉��P�͐��Ј��ȊO�̌ٗp�̑����ɂ����̂ƂȂ��Ă���A���Ј��̌ٗp�͌����X���������Ă��܂��B<�y�[�W�̃g�b�v��>
(1) ���v�J�n�ȗ��Œ�ƂȂ����J�����z��
���{�o�c�A��2003�N12���ɔ��\�����A2004�N�Ōo�J�ϕł́A�t�����l�Ɛl����̊W�ł���J�����z���̏㏸�Ɋւ��āA�������O�������Ă��܂����B�������Ȃ��獡���2005�N�łł́A�J�����z���ɂ��Ă͋K�͕ʔ�r�ȊO�ɐG����Ă��܂���B
���̗��R�Ƃ��ẮA
�@�J�����z�����A���{�o�c�A�Ƃ��Ă��ے�ł��Ȃ��قǁA�ቺ���Ă��Ă���B
�A�J�����z���̕��ꂽ��t�����l���Y�������P���A�l����ɔz������]�n���傫���Ȃ��Ă���B
�Ƃ������Ƃ��l�����܂��B
2005�N�P���ɓ��������{�o�c�A�����\�����u2005�N�ŏt�G�J�g���E�J�g���c�̎�����v�i��
���A������j�ł́A�u���~�܂肷��J�����z���v�Ƒ肷��y�[�W�i33�y�[�W�j������܂����A�{����ǂނƁA
��2000�N�ȍ~�͉��~���Ă���B
���o�u������ȑO�̐����ɂ܂ł͒ቺ���Ă��Ȃ��B
�Ǝw�E���Ă���A������A�J�����z���̒ቺ��F�߂�Ƃ���ƂȂ��Ă��܂��B
�u������v�ł́A�u�o�u������ȑO�i���o�u�����j�̐����ɂ܂ł͒ቺ���Ă��Ȃ��v�Əq�ׂĂ��܂����A�����o�σx�[�X�̘J�����z���i�ٗp�҂P�l�����薼�ڌٗp�ҕ�V���A�Ǝ҂P�l�����薼�ڂf�c�o�j������ƁA���̓o�u�������93�N�x�ɂ�67.2���������̂��A2003�N�x�ɂ�62.2���ɒቺ���Ă��܂��B�i�}�\�P�j
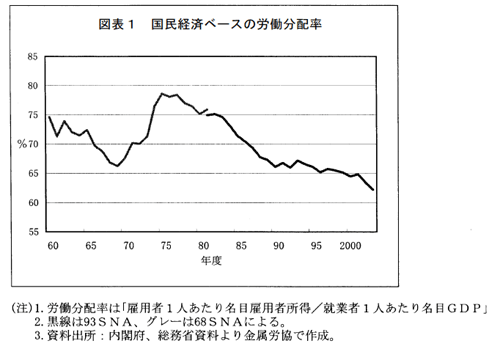
��q����悤�ɁA�J�����z���͕s�����ɏ㏸���A�D�����ɒቺ����X��������܂����A2003�N�x��62.2���Ƃ��������́A���Ă̍��x�����������A�����ăo�u���o�ς̎������Ⴂ�A�f�c�o���v�J�n�ȗ��Œ�̐����ł��B
�Ƃ�킯�ߔN�̓���������ƁA2002�N�x�ɂ͘J�����z���̕���ł���u�A�Ǝ҂P�l�����薼�ڂf�c�o�v�̐�������0.4���̃v���X�ƂȂ��Ă���̂ɑ��A���q�ł���u�ٗp�҂P�l�����薼�ڌٗp�ҕ�V�v�̑������́A�t��1.8���̃}�C�i�X�ƂȂ��Ă��܂��B2003�N�x�����l�ŁA�P�l������f�c�o��0.8���̃v���X�Ȃ̂ɁA�P�l������ٗp�ҕ�V��1.2���̃}�C�i�X�ł��B���ň��̑�s�����獡���̌i�C�Ɏ���98�N�x�ȍ~�̂U�N�ԂŁA�u�ٗp�҂P�l�����薼�ڌٗp�ҕ�V�v�̑��������A�u�A�Ǝ҂P�l�����薼�ڂf�c�o�v�̐��������������N�͂P��i2001�N�x�j��������܂���B�i�}�\�Q�j
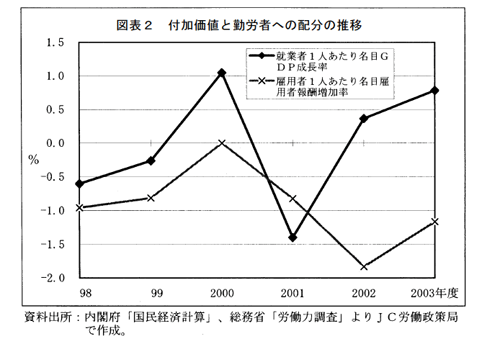
2004�N�x�ɓ����Ă�����A�A�Ǝ҂P�l�����薼�ڂf�c�o���������A�S�`�U�����A�V�`�X�����Ƃ��O�N��1.0���̃v���X�ƂȂ��Ă���̂ɑ��A�ٗp�҂P�l�����薼�ڌٗp�ҕ�V�̑������́A�S�`�U������0.5���A�V�`�X������0.8���ƃ}�C�i�X�𑱂��Ă��܂��B
�����o�σx�[�X�Ō����J�����z���̂Ƃ���ɂ���
���{�o�c�A�́A2003�N�Ōo�J�ϕł́A�u�ٗp�ҏ����i�}�}�j(�i�b���F�ٗp�ҕ�V�̂���)�����������v�Ƃ�����`�̘J�����z���̐��ڂ��O���t�Ŏ����iP.58�j�A�u��Ƃ̕t�����l�ɐ�߂�l����̊������J�����z�����㏸���āv����Ǝ咣���Ă��܂����B�iP.57�j
�����J���͂���ɑ��āA
�����{�o�c�A�������Ƃ��Ă���u�ٗp�ҕ�V�����������v�Ƃ����f�[�^�́A����Ɏ��c�Ǝ҂��Y�ݏo�����t�����l���܂�ł���̂ŁA��i���Ƃ��Ă͎��c�Ǝ҂̔䗦���傫���A�p�Ƃ��i�ށi���c�Ǝ҂��ٗp�҉�����j�ߒ��ɂ���킪���ł́A�㏸����X���������Ă���B�]���āA���̘J�����z�����㏸���Ă��邩��Ƃ����āA�u��ƌo�c���������Ă���v�Ƃ͂����Ȃ��B
���u�ٗp�ҕ�V�����������v�ł́A����Ɍ������p���܂܂�Ă��Ȃ��̂ł�����㏸�X���������ƂɂȂ�B���q�̌ٗp�ҕ�V�ɂ́A�ٗp�҂̌������p�i���q���̗{���j���܂܂�Ă���̂�����A����ɂ��������p���܂܂�Ă�����ׂ��B
�Ǝw�E���A�ΘJ�҂ւ̕t�����l�̔z���̓x������]�����邽�߂̎w�W�Ƃ��āA�]�����
�����c�Ǝ҂��ٗp�҉�����e�����Ȃ��B
������̕t�����l�Ɍ������p�i�Œ莑�{���Ձj���܂܂�Ă���B
�Ƃ����ӂ��̏������N���A����A
| �ٗp�҂P�l�����薼�ڌٗp�ҕ�V���A�Ǝ҂P�l�����薼�ڂf�c�o |
�Ƃ����J�����z����p���Ă��܂��B
�Ȃ����{�o�c�A�́A2004�N�Ōo�J�ϕA�Ȃ�тɍ����2005�N�łł��A�u�ٗp�ҕ�V�����������v�Ƃ����J�����z�����f�ڂ��Ă��܂���B |
<�y�[�W�̃g�b�v��>
(2) ��ƋK�͕ʂɌ������ʔz���̓���
���{�̋����Y�Ƃ̋����͂́A����ɂ����鐶�Y�Z�p�̍����A�Z�p�E�Z�\�̏W�ρA���i�J���́E�Z�p�J���͂̍����A�f�ށE���i�̕i���E�J���͂̍����ȂǁA���Y����ƊJ������A���[�J�[�Ƒf�ނ╔�i����������T�v���C���[����̂ƂȂ����A�u�����́v�̋����ɂ���Ďx�����Ă��܂��B�Z�p�́E�J���͂̈�w�̍��x����}��A���ۋ����͂����������ێ��E�������Ă������߂ɂ́A�Y�ƊԊi�������A�����Y�Ƃɂӂ��킵�������������`�����āA�ΘJ�҂̔\�͔�����}��ƂƂ��ɁA�Y�Ɠ��i���̐����ɂ��A�����Y�ƑS�̂Ƃ��Ă̎Љ�I�Ȓ��������`�����s���ł��B
�������Ȃ���A�o�J�ϕɂ����ē��{�o�c�A�́A�E��ƋK�͂��������Ȃ�ɂ�ĕt�����l�ɐ�߂�l����̔䗦�͍����Ȃ��Ă���B��ƋK�́E��Ƒ̎��Ɍ���������������́A�o�c�̍����ɂ��������ł���B�i�o�J�ϕ�P.52�j�ȂǂƎ咣�A�P���Ȋ�ƋK�͂ɂ����������̊i����e�F���A�ނ��낻��R�����Ă��܂��B
����������ƂƂ����Ă��͗l�X�ł�����A��ƋK�͂���������������͒Ⴍ�Ă悢�A�ȂǂƂ����l�����͌��ꓹ�f�ł��B�܂����ꂾ���łȂ��A���Ƃ���ʓI�ȌX���Ƃ��āA���Ƃɔ�ׂĒ�����Ƃ̘J�����z���������Ƃ��Ă��A���Ƃƒ�����Ƃł́A���������r�W�l�X���f�����Ⴄ�̂ł�����A������Ƃ̘J�����z����������ׂ����A�Ƃ��������ɂ͂Ȃ�܂���B�����Y�Ƃł����Ă��A�r�W�l�X���f�����Ⴆ�A�����y�U�ŘJ�����z���̍����_���邱�Ƃ͂ł��܂���B
�J�����z���̍����_����O�ɁA���㍂�ɐ�߂�t�����l�̔䗦���A�����Ƃɂ����Ċ�ƋK�͕ʂɌ��Ă݂܂��傤�B�����Ȃ̖@�l��Ɠ��v�i2003�N�x�j�ɂ��A���㍂�ɐ�߂�t�����l�̔䗦�́A����Ƃ�19.7���A������Ƃ�22.0���A����Ƃ�26.4���A����Ƃ�40.2���ƂȂ��Ă���A��ƋK�͂��������Ȃ�قǁA�����Ȃ�X���ɂ���܂��B��������������āA�K�͂���������Ƃ̂ق����ׂ��Ă���A�ƍl����l�͂��Ȃ��ł��傤�B�����ł͂Ȃ��āA���̂��Ƃ͊�Ɗ����ɂ����āA�t�����l�̔z����ł���A�]�ƈ�������Ƃ����u�l�v�̉ʂ����������傫���Ƃ������Ƃ������Ă��܂��B�i�}�\�R�j
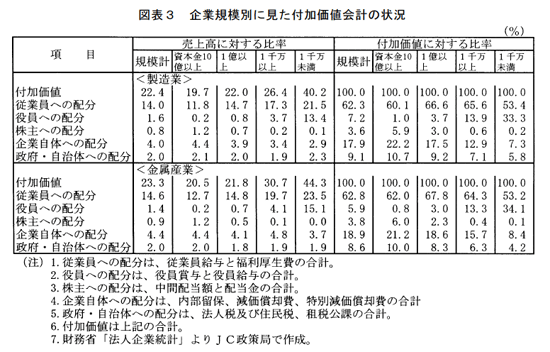
��̓I�ɕt�����l�̔z����̓��������ƁA�����Ƃ͂����肵�܂��B�t�����l�ɐ�߂�u�����v�ɑ���z���̔䗦�́A��ƋK�͂��������Ȃ�قǍ����Ȃ��Ă��܂��B����Ƃł�1.0���ɂ����܂��A������Ƃł�33.3���ɒB���Ă��܂��B�������ɁA������Ƃɂ�����J�����z���̍��������Ȃ̂Ȃ�A�����ɑ���z���̍��������ɂ��Ȃ���Ȃ�܂���B�������Ȃ��炱��́A�K�͂̏�������Ƃقnjo�c�҂̔\�͂�l���Y�Ɉˑ������o�c�ł��邽�߂ɁA�����ɑ��Č��߂̔z�������邱�Ƃ��A������x�������������Ă���̂ł��B
����A��Ƃ��ꎩ�̂ɑ���z���i�������ۂƌ������p�j�̔䗦�́A��ƋK�͂��傫���Ȃ�قǍ����Ȃ��Ă��܂��B����́A������Ƃł́A�o�c�҂̌l���Y����Ƃ̓������ۂƓ����������ʂ����Ă��邽�߂ɓ������ۂ����Ȃ��Ƃ������Ƃ̂ق��A����Ƃقǐݔ����������z�ɂȂ��Ă��邱�ƁA���Ȃ킿�A�ݔ��Ɉˑ������r�W�l�X���f���ɂȂ��Ă��邱�Ƃ����R�ł���ƍl�����܂��B
���������Ȃ��ŁA�]�ƈ��ɑ���z���̔䗦�́A����60.1���A�������66.6���A�����65.6���A�����53.4���ƂȂ��Ă���A����ƁA����Ƃł́A�ނ����ƋK�͂��������Ȃ�قǏ]�ƈ��ɑ���z���̔䗦���Ⴍ�Ȃ��Ă���̂������ł��B�u�l�v�Ɉˑ������r�W�l�X���f���ł���ɂ�������炸�A�]�ƈ��ɑ���z�����s�\���Ȏ��Ԃ���������ƂȂ��Ă��܂��B
�킪�������Y�Ƃ̋����͂��A���[�J�[�ƃT�v���C���[����̂ƂȂ��������͂ňێ�����Ă��邱�Ƃ��炷��A�Y�Ɠ��i���̐����ɂ��A�����Y�ƑS�̂Ƃ��Ă̊�Y�Ƃɂӂ��킵�������������`�����Ă����Ȃ���Ȃ�܂���B�i�}�\�S�j
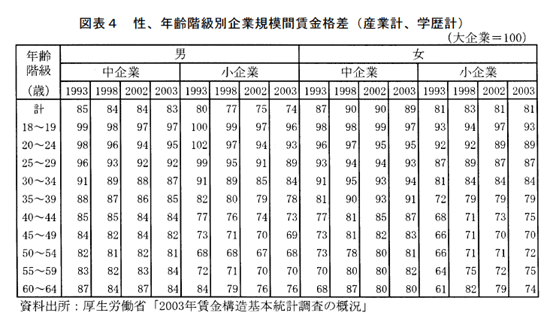
<�y�[�W�̃g�b�v��>
(3) �����o�ς̊ϓ_�����܂��A�ΘJ�҂ւ̓K���Ȑ��ʔz����
���{�o�c�A�́A���2004�N�Ōo�J�ϕɂ����āA
�E�l����̑��z���ς��Ȃ��Ƃ��Ă��A�t�����l����������A�J�����z���͏㏸����B�iP.43�j
�E�f�t�����ɂ����ẮA���̏��i��T�[�r�X�ɔ�ׂĒ��������������ω����Ȃ��Ƃ��������̉����d��������茰���ɕ\���A����̌ٗp�ɗ^����e�������O�����B�iP.45�j
�ȂǂƎ咣���Ă��܂����B�������Ȃ��猻���ɂ́A
�����A�R��暌��Ȃǂ̔j�]�ɏے�����邱�̐��ň��̑�s�����ɂ����āA�t�����l����������ȏ�ɁA�l������������B
��2002�N�t�ȍ~�̌i�C�ɂ���ĕt�����l���Y�������シ�����A�l����͌����𑱂����B
�Ƃ������Ƃ������܂��B
�J�����z���́A�{���Ȃ�Γ��{�o�c�A���咣����Ƃ���A�����̉����d�����ɂ���ĕs����
�ɂ͏㏸����͂��̂��̂ł��B
�������Ȃ���A���{�ł͏]������A
�����������グ�̌��N�s���Ă���Ƃ��낪�����B
������O�����̔䗦�������B
���ꎞ���̔䗦�������B
���Ƃɂ��A�l����̉����d�������R�����A�_��Ȃ��̂ł����B
�����čŋ߂ł́A
�������E�������x�̌������ɂ��A�l����̗}���E�����������s���Ă����B
�����Ј��ȊO�̌ٗp�̔䗦�����債�Ă���B
���Ƃɂ��A�l����̕ϓ�����܂��܂��i��ł��܂��B���{�ł́A���Ȃ��Ƃ������o�σx�[�X�Ō���A�u�����̉����d�����v�A�u�s�����̘J�����z���̏㏸�v�͌��z�ɂ����܂���B
�l��������d�����������Ă��āA�s�����ɘJ�����z�����㏸����Ƃ������Ƃł���A�s���ł��l�������قǗ������܂��A�l����o�ς̃r���g�E�C���E�X�^�r���C�U�[�i�������艻���u�j�̖�ڂ��ʂ����āA�i�C�ꊄ���h�����ʂ������܂��B
�c�O�Ȃ���킪���̐l����́A�s�����ɉ����d�����������Ă��炸�A�ϓ�����_��͂܂��܂��i��ł��܂��B�l����̕ϓ���́A�ʊ�Ƃ̌o�c�҂ɂƂ��ẮA�ڐ�̌o�c���y�ɂ��邱�ƂɂȂ邩������܂��A���̂��́A�ΘJ�Ґ����ƍ����o�ϑS�̂ɂ������Ă���̂��Ƃ������Ƃ�Y��Ă͂Ȃ�܂���B
���t�{��2004�N12���ɔ��\�����u���{�o��2004�v�ɂ��ƁA���{�ł́A��i���̕��ςɔ�ׂāA�i�C�g�����i�D���j�̊��Ԃ��Z���A�i�C��ފ��������A�Ǝw�E����Ă��܂��i�}�\�T�j�B
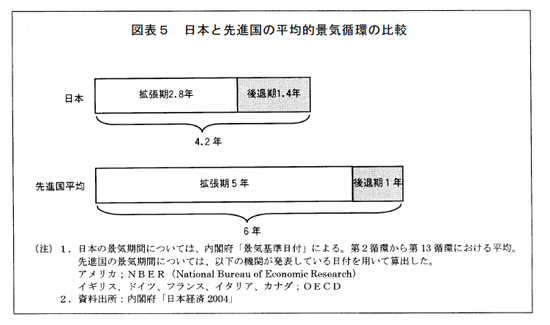
��ʂɁA�J���s�ꂪ�d���I�ł���ƌi�C�z�̊��Ԃ��Z���A�Ƃ̕��͂�����܂����A�s�����ł��J�����z�����ቺ������{�o�ς́A����ɂ͊Y�����܂���B�ނ���A�l����A�o�ς̃r���g�E�C���E�X�^�r���C�U�[�̖�ڂ��ʂ����Ă��Ȃ����Ƃ��e�����Ă���̂ł͂Ȃ����A�ƍl�����܂��B
������������̉��ŁA���ɁA�����E�J�������̗}����}��悤�Ȃ��Ƃ�����A�������ߏ��ł��邱�Ƃɂ��z���̕Њ��Ə����i���̊g��A��Ƃ̒��~���߂Ɖƌv���~�̗������݂ɂ������s���A�O���哱�E�A�o�ˑ��^�̐����A�����Ԏ��̊g��ȂǁA�킪���̌o�ύ\���ɘc�݂������邱�ƂɂȂ�܂��B�����Ȃ�A�Y�ƌo�ς̌��S�Ȕ��W�ƍ��������̈���E�����j�Q����ƂƂ��ɁA�q��Ă̔�p���ΘJ�҂����S���邱�Ƃ��ł����A���q�����܂��܂����i���A�Ђ��Ă͌��I�N�������̈�w�̈����������A������ւ̑Ή����܂��܂�����Ȃ��̂Ƃ��܂��B�����o�ς̊ϓ_�����܂��A�e�Y�ƁE��Ƃ̎���ɑ����A�x�[�X�A�b�v�A�ꎞ���ɂ���āA�ΘJ�҂ւ̓K���Ȑ��ʔz�����s���Ă������Ƃ��d�v�ł��B<�y�[�W�̃g�b�v��>
(4) ���{�o�c�A���o�ρE��ƋƐщ̋ΘJ�҂ւ̐��ʔz����e�F
�J�����z���̒ቺ�́A�ΘJ�҂��Y�ݏo�����t�����l�ɔ�ׁA�ΘJ�҂ɑ��鐬�ʔz�����\���ɍs���Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃ������Ă���킯�ł���A���̈Ӗ��͂���߂ďd�v�ł��B
���{�o�c�A���o�J�ϕł́A
�E��������͒������I�Ȍo�c��Y���̊m���錩�ʂ��̂��ƂɌ��肷�邱�Ƃ��s���ł���B�����ɁA�����͊ȒP�ɂ͉�����ꂸ�A���̏㏸���Œ��̑����ɒ��ڂȂ���킯�ŁA�P�N�x�̋Ɛт�Z���Ԃ̐��Y���̓��������Œ���������s�Ȃ��ׂ��ł͂Ȃ��B�iP.54�j
�E���������ۋ����Ɛ�s���s�����Ȍo�c���������܂��Ȃ��ł́A���ۓI�ɂ݂ăg�b�v���x���ɂ����������������ȏ�����グ�邱�Ƃ͍���ł���B�iP.54�j
�E�����o�σ��x���ɂ����ẮA���{�S�̂̍��R�X�g�\�������Ă������߂ɁA�o�c�R�X�g�ɂ����Ƃ��傫�Ȕ�d���߂������K���Ȑ����ɗ}�����邱�Ƃ��A���Y��������̊ϓ_������s���ł���B
�ʊ�Ƃ̒�������͌ʘJ�g���b�������Ō��߂邪�A���{�S�̂̌o�Ϗ��݂�Ȃ�A�����Ē��������グ�̗]�n�͂قƂ�ǂȂ����Ƃ����߂ċ������Ă��������B�iP.55�j
�ȂǂƎ咣�����A����ł́A
�E�o�ς��ƋƐт͓̉����l�X�̓w�͂̐��ʂł����邩��A�����t�G�J�g���ɂ����ẮA�Ɛт̉��݂����Ƃ́A�����l�̓w�͂ɑ��ĐϋɓI�ɕ�K�v�������낤�B�iP.6�j
�E�����ɂ��Ă��A�ʊ�Ƃɂ����Ċe�J�g�̐ӔC�̂��ƂŐ����������グ�邱�Ƃ́A���ꂼ��̔��f�ɂ����Ď��R�ł��邱�Ƃ͓��R�ł���B�iP.6�j
�Ǝw�E���Ă��܂��B2002�N�ȍ~�̌i�C�Ɗ�Ǝ��v�̉��P�̂Ȃ��ŁA���{�o�c�A�Ƃ��Ă��A2005�N�����ɂ�����A�ΘJ�҂ɑ��鐬�ʔz����e�F����������Ȃ��ɂ���A�Ƃ����܂��B<�y�[�W�̃g�b�v��>
(5) ��Ǝ��v�x�[�X�Ō����ΘJ�҂ւ̐��ʔz���̏�
2004�N12���ɔ��\���ꂽ����u�Z�ρv�ɂ����Ă��A�����Ɓi�S���E�K�͌v�j�̐l����́A98�N�x����2004�N�x�����݂܂ŁA�V�N�A���őO�N��������Đ��ڂ��Ă��܂��B���̂��ߔ��㍂�l����䗦���A98�N�x�ɂ�15.08���ł������̂��A2004�N�x�����݂ł�13.14���ƁA�U�N�Ԃ�1.94�|�C���g���ቺ���Ă��܂��B����ŁA���㍂�c�Ɨ��v���͓����V�N�Ԃ�2.86������4.95����2.09�|�C���g�㏸���Ă���A���傤�ǐl����̍팸�����A���̂܂܉c�Ɨ��v�ɂȂ��Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B
�܂��A�����Y�Ƃł́A���̊Ԃ̔��㍂�l����䗦�̒ቺ����16.20������13.81���ւ�2.39�|�C���g�ƂȂ��Ă���A�����ƑS�̂������Ă��܂��B����ɁA���㍂�c�Ɨ��v����2.10������4.87���ւ�2.77�|�C���g�㏸���Ă���A�l����̍팸�����闘�v���グ�Ă��邱�Ƃ��킩��܂��B�i�}�\�U�j
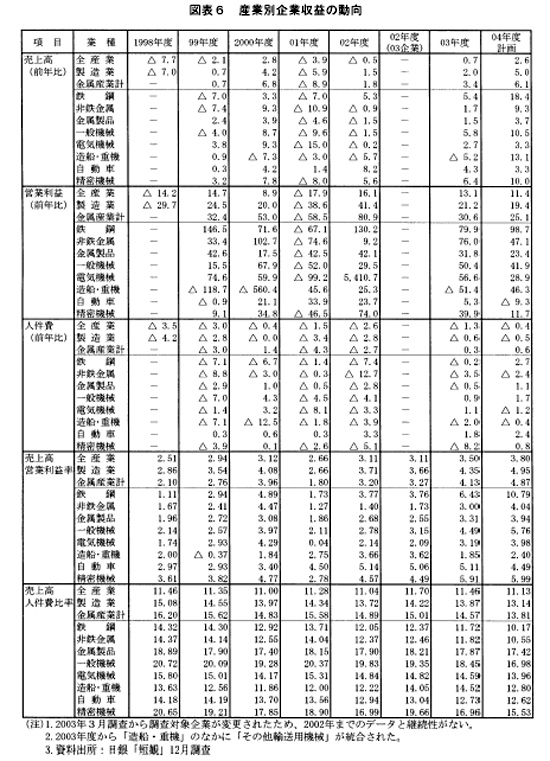
<�y�[�W�̃g�b�v��>
(6) ��ƋƐт��ꎞ���ɓK���ɔ��f����Ă��邩�ǂ����͌����K�v
�o�J�ϕł́A�ΘJ�҂ւ̐��ʔz���Ɋւ��āA
�E�Z���I�Ȋ�ƋƐт̐��ʂɂ��Ă͏ܗ^�E�ꎞ���ւ̔��f�����c����p�����]�܂��iP.55�j
�Ƃ��Ă��܂��B
�������Ȃ���A����16�N�ŘJ���o�ϔ����̕��͂ɂ��A90�N�㖖�܂ł́A�ꎞ���̑������Ɣ��㍂�o�험�v���Ƃ̊Ԃɂ���߂ċ����A���m�ȑ��֊W�������Ă��܂������A98�N�N���ꎞ�������������ɁA���֊W�����Ȃ�キ�Ȃ��Ă��܂��B�������A�������㍂�o�험�v���ɂ����Ă��A�ȑO���Ⴂ�ꎞ�������x�����Ă��Ȃ��A�Ƃ����ɂȂ��Ă��Ă��܂��B
���{�o�c�A�̓x�[�X�A�b�v�ł͂Ȃ��ꎞ���Ő��ʔz�����Ǝ咣���Ă��܂����A�e�Y�ƁE��ƘJ�g�ɂ�����Z���I�Ȋ�ƋƐт̐��ʂ��A�ꎞ���ɓK���ɔz������Ă��邩�ǂ����A�T�d�Ɍ����Ă������Ƃ��d�v�ł��B�i�}�\�V�j
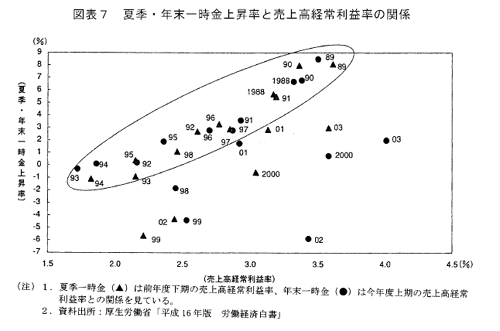
<�y�[�W�̃g�b�v��>
(1) ���{�o�c�A�̃x�A�ے�_
�����J���ł́A����܂ŁA�o�ϐ����A���������A�ٗp��A�t�����l���Y���A�Y�Ɠ����A��ƋƐсA�����̎Љ�i�Љ�I�Ȓ�������A����������r�j�Ȃǂ𑍍����f������ŁA�Y�ƁE��Ƃ̎��Ԃ܂�������ׂ�����������ݒ肵�A���̎����̂��߂ɁA�J�g�̐^���Ș_�c�ɂ���āA�x�A�̗L����z���̂���������肵�Ă��܂����B
����A2005�N�o�J�ϕł́A
�E���͂�s�ꉡ�f�I�ȉ����т́A������u�x�[�X�A�b�v�i�x�A�j�v�v�����߂���J�g���́A���̖������I�����B�iP.54�j
�E�ʊ�Ƃɂ����Ă��A�����Ǘ��̌ʉ����i�ނȂ��ł́A�S�]�ƈ��̒����J�[�u�̖��N�̈ꗥ�I��グ�Ƃ�����|�ł́u�x�[�X�A�b�v�i�x�A�j�v�ɂ��Ă��A���̋@�\����]�n�͖R�����Ƃ����悤�B�iP.55�j
�E�ʊ�ƃ��x���ɂ����ẮA�啝�Ȑ��Y���̌����l�ނ̊m�ۂȂǂ̂��߂ɒ����̈����グ���s�Ȃ���ꍇ�����낤���A�t�ɂ�ނ��A�������������ɔ����鎖�Ԃ��������邪�A����A�����́u��������v�Ə̂��ׂ��ƍl����B�iP.55�j
�Ǝ咣���A�u�x�[�X�A�b�v�v�Ƃ������t�A�����Ă��̍l�������̂�ے肵�悤�Ƃ��Ă��܂��B
���������x�[�X�A�b�v�Ƃ́A�O�q�̂悤�ɁA�o�ϐ����A���������A�ٗp��A�t�����l���Y���A�Y�Ɠ����A��ƋƐсA�����̎Љ�i�Љ�I�Ȓ�������A����������r�j�Ȃǂf���āA�����\�������ς����Ƃł��B
�o�J�ϕ̂����u�����Ǘ��̌ʉ��v�Ƃ͋�̓I�ɉ����w���̂��A���m�ɂ͂킩��܂��A�ꕔ�̒����R���T���^���g�Ȃǂ��咣����悤�ɁA�����\���̂��̂��Ȃ����Ă��܂��A�o�c�҂̈���I�Ȝ��ӂɂ���ċΘJ�Ҍl���Ƃɒ��������肷��A�Ƃ��������ɂ���̂łȂ�����́A�o�ς������ƃ[�������������A�����������i���S���オ��Ȃ��ȂǂƂ������Ƃ͍l�����܂���A�����\�̏��������͕s���ł���A�]���Ă�������{�o�c�A���x�[�X�A�b�v�̖��O��l������ے肵�悤�Ƃ��Ă��A�ے肵�����̂ł͂���܂���B�x�[�X�A�b�v�̑��݈Ӌ`�͕��ՓI�Ȃ��̂ł��B
�o�ϐ����╨���㏸�A�����̎Љ�I�ȑ���A�Y�Ɠ����Ȃǂ́A����ȏꍇ�������ẮA��{�I�ɂ́A�ΘJ�Ҍl�̐��ʂɂ���ĉe���������̂ł͂Ȃ��A�]���Ă����f����̂͒����\�̏��������ł���x�[�X�A�b�v�ɑ��Ȃ�܂���B�l�̐��ʂɕ邽�߂̒��グ�́A�����\��ɂ�����ړ��ł��B
��ƘJ�g�̔��f�ŁA����̐E���w�ɑ��āA�����\�̏�����������������ꍇ������܂����A����͂����܂ł��x�[�X�A�b�v�����̏d�_�I�Ȕz���ɂ������A�x�[�X�A�b�v�łȂ��킯�ł͂���܂���B
���{�o�c�A�̓x�[�X�A�b�v���u�s�ꉡ�f�I�ȉ����т́v���̂ł���A�Ǝ咣���Ă��܂����A�x�[�X�A�b�v�̂����A�o�ϐ����╨���㏸�A�J���s��ȂǍ����o�ς̓����f���������ɂ��ẮA�u�s�ꉡ�f�I�ȉ����сv�ł��邱�Ƃ͓��R�ł��B
���{�o�c�A���A
�E�����o�σ��x���ɂ����ẮA���{�S�̂̍��R�X�g�\�������Ă������߂ɁA�o�c�R�X�g�ɂ����Ƃ��傫�Ȕ�d���߂������K���Ȑ����ɗ}�����邱�Ƃ��A���Y��������̊ϓ_������s���ł���B
�ʊ�Ƃ̒�������͌ʘJ�g���b�������Ō��߂邪�A���{�S�̂̌o�Ϗ��݂�Ȃ�A�����Ē��������グ�̗]�n�͂قƂ�ǂȂ����Ƃ����߂ċ������Ă��������B�iP.55�j
�Ǝ咣���Ă���̂́A�ނ����������Ɂu�s�ꉡ�f�I�ȉ����сv�̕��������邱�Ƃ�F�߂Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B
�������Ȃ���A�x�[�X�A�b�v�̍\���v�f�͂��ꂾ���łȂ��A�����i�������A�Y�Ɠ������ƋƐт����f�����킯�ł�����A���S�Ɂu�s�ꉡ�f�I�ȉ����сv�ł͂��肦�܂���B�������N�̎��т����Ă��A�J�������������i�������A�Y�Ɠ������ƋƐтf�����x�[�X�A�b�v�����߂Ă���̂ɑ��A�ނ���o�c���̂ق��������A�u�x�A�[���Ƃ����s�ꉡ�f�I�ȉ����сv��}�낤�Ƃ��Ă��Ă��܂��B2005�N�����ɂ����ẮA���{�o�c�A�́A�i�������̊ϓ_�Ȃǂ���x�[�X�A�b�v�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��A���邢�͎Y�Ɠ������ƋƐт̊ϓ_����x�[�X�A�b�v�̂ł�����ɂ����Ƃ́A�ϋɓI�Ƀx�[�X�A�b�v�����{����悤�Ɏw�����ׂ��ł���A�ʊ�Ƃ̌o�c��������������{�p���ɗ����Č��ɑΉ����ׂ��ł��B<�y�[�W�̃g�b�v��>
(2) ����������x
����������x�́A�N��̏㏸�ɔ������v��̑�����A�Α��N���̑����ɂ��E�����s�\�͂̌���f���邽�߂̐��x�ł��B����܂ŁA�ʊ�Ƃ̎d���⓭�����̎��Ԃ܂��Đ��x�������A���x�̎��{�������̈���ƘJ���ӗ~�̌���ɂ��Ȃ����Ă��܂����B
���ꂼ��̎Y�Ƃ̓����ɂ���āA�\�͌`���������I�ɍs���A�]���ċΘJ�҂̍v���ɑ��Ă��A�����I�ɕ邱�Ƃ��L���ȏꍇ�ƁA��r�I�Z���Ԃɔ\�͌`�����s���A�Z���I�ɍv���ɕ邱�Ƃ��K�����ꍇ�Ƃ�����܂��B�O�҂̏ꍇ�ɂ́A����������x���\�͂̌`���Ɣ����ɂ���߂ėL���ł��邱�Ƃ͓��R�ł����A��҂̏ꍇ�ł��A�N��Ƃ̐��v��̈Ⴂ��A�W���I�ȃX�L���p�X�͑��݂��Ă���A����f���ċΘJ�҂Ɂu�J�������ɑ�����S���v�������炷��ŁA��������͕s���̂��̂Ƃ����܂��B
�o�J�ϕł́A����������x�ɂ��āA
�E���N������������I�ɏ�������Ƃ����菸���x���������̂܂܂Ɏc���Ă���Ƃ���A�p�~���܂߂Đ��x�̔��{�I�ȉ��v���}���ׂ��ł��낤�B�iP.54�j
�Ǝ咣���Ă��܂����A���c��ɂ�鏘���ɂ����ẮA
�E�f�W�^�������邱�Ƃ̂ł��Ȃ��A�A�i���O�I�ȋZ�p��m�E�n�E�A���Ƃ��Βm�I�n�����s�m�����ɑΉ�����m�E�n�E�Ƃ��������̂̉��l���}���ɍ��܂��Ă���B���������\�͂���Ă�͂������A�u����́v�̌���ł���B����́A�����̐l�������Ԃɂ킽����H�I�Ȍo����ςݏd�ˁA�p���I�Ȓ~�ς�ʂ��ē�������̂ł���A�����Ɛl�ނ��琬�����E��̕��y�Ƃ��Ē蒅������̂ł��낤�B�iP.4�j
�E�u����́v�͈꒩��[�ɐ�����̂ł͂Ȃ��B�ٗp�ƘJ���������I�Ɉ��肳���Ă����A���S���āA���Ԃ������Ĕ\�́E�ӗ~�̌���Ɏ��g�ނ��Ƃ��ł���B�iP.5�j
�Ǝ咣���Ă��܂��B�菸���x�́A�܂��Ɂu�����Ԃɂ킽����H�I�Ȍo���̐ςݏd�ˁv�u���S���āA���Ԃ������Ĕ\�́E�ӗ~�̌���Ɏ��g�ށv���Ƃ𑣐i���A�]�����鐧�x�ɂق��Ȃ�܂���B<�y�[�W�̃g�b�v��>
(3) �A�Ǝ҂P�l������̖��ڂf�c�o�������������o�Ϗ�̔z���̖ڈ�
�O�q�̂悤�ɁA�����o�σx�[�X�̘J�����z���́A
| �ٗp�҂P�l�����薼�ڌٗp�ҕ�V���A�Ǝ҂P�l�����薼�ڂf�c�o |
�ł�����A�����o�σx�[�X�ł́A�D���ł��s���ł��A�C���t���ł��f�t���ł��A�J�����z����
���ɕۂ悤�ȍl�����A
| �ٗp�҂P�l�����薼�ڌٗp�ҕ�V���������A�Ǝ҂P�l�����薼�ڂf�c�o������ |
���Ȃ킿�A�ٗp�҂P�l������̐l����̐L�ї����u�A�Ǝ҂P�l�����薼�ڂf�c�o�������v�Ɍ����������̂ɂ���Ƃ����A�t���Y��������i���t�����l���Y��������j���A�x�[�X�A�b�v�̂����̍����o�ςf���镔���̊�ƂȂ�܂��B�����āA����ɒ����i��������A�Y�Ɠ����A��ƋƐтf������Ƃ����̂��x�[�X�A�b�v�̊�{�I�ȍl�����ł��B
���{�o�c�A�̃x�A�ے�Ɛ��Y������������̒���
���{�o�c�A�́A1970�N�ȗ��A�u���Y��������v�����������ɂ�����o�c���̃}�N���I�Ȗڈ��Ƃ��Ă��܂������A����́A�P�l������̐l����̏㏸���i���F�菸�͊�{�I�ɂ͓��]�����Ȃ̂ŁA����Ɋ܂܂�Ȃ��j�A�����o�σx�[�X�ł����ƁA�ٗp�҂P�l�����薼�ڌٗp�ҕ�V���������A�������I�ɍ��S�̂̎��������o�ϐ��Y���㏸���A���Ȃ킿�u�A�Ǝ҂P�l����������f�c�o�������v�Ɍ����������̂ɂ���Ƃ����l�����ł��B
| �ٗp�҂P�l�����薼�ڌٗp�ҕ�V���������A�Ǝ҂P�l����������f�c�o������ |
�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
�����o�σx�[�X�̘J�����z����
| �ٗp�҂P�l�����薼�ڌٗp�ҕ�V���A�Ǝ҂P�l�����薼�ڂf�c�o |
�ł�����A���Y��������̉��ł́A���q�́u�A�Ǝ҂P�l����������f�c�o�������v�Ɍ������ĕ�
�����A����̕ω��́u�A�Ǝ҂P�l�����薼�ڂf�c�o�������v�ƂȂ�܂��B���̂��ߕ������㏸����
����i�C���t���j�ꍇ�ɂ́A
�ƂȂ��āA�J�����z�����ቺ���܂��B���Y��������́A�C���t���̎��ɂ́A�u�J�����z���ቺ�����v�Ƃ��č�p���܂��B
����A�������ቺ���Ă���i�f�t���j�ꍇ�ɂ́A���ڐ����������ł���A������������Ή�����قǁA���グ���������Ȃ�Ƃ������ƂɂȂ��Ă��܂��܂��B
�Ⴆ�ΐ��{�o�ό��ʂ���2004�N�x���ь����݂ł́A
�@�@�����f�c�o��������2.1��
�@�@�A�A�Ǝґ�������0.2��
�� �A�Ǝ҂P�l����������f�c�o��������1.9�� |
�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B���Y��������ɏ]���A2004�N�x�ɂ�1.9���̃x�A�i�菸�����j�Ƃ������ƂɂȂ�܂����A�����ɂ͂��������Ή��ɂ͂Ȃ�Ȃ��킯�ŁA�f�t���̉��ł́A���Y��������͌o�c���ɂƂ��ėp�����A�ނ���L�Q�Ƃ����킯�ł��B�ł�����A2004�N�ł̌o�J�ϕł́A����Ɉ�،��y�����A�e�ɒu���Ă��܂����B�������Ȃ���2005�N�łł́A
�E�����o�σ��x���ɂ����ẮA���{�S�̂̍��R�X�g�\�������Ă������߂ɁA�o�c�R�X�g�ɂ����Ƃ��傫�Ȕ�d���߂������K���Ȑ����ɗ}�����邱�Ƃ��A���Y��������̊ϓ_������s���ł���B�iP.55�j
�Ƃ��Č��y���Ă���A�u���Y��������v�������钛���������Ă��܂��B
�x�[�X�A�b�v�̔ے�Ɓu���Y��������v�̕����͋��ɁA�߂������f�t�����������A�����㏸�����}�C�i�X����v���X�ɓ]�������ꍇ�ɁA�����̏㏸�f�����x�[�X�A�b�v��j�~����_�����A���߂��Ă�����̂ƍl�����܂��B |
<�y�[�W�̃g�b�v��>
| �R�D�ቺ��������{�̐l����� |
(1) ��i���̂Ȃ��Œ���ʂɗ��������{�̐l�����
���{�o�c�A�͌o�J�ϕɂ����āA
�E���������ۋ����Ɛ�s���s�����Ȍo�c���������܂��Ȃ��ł́A���ۓI�ɂ݂ăg�b�v���x���ɂ����������������ȏ�����グ�邱�Ƃ͍���ł���B�iP.54�j
�Ǝ咣���Ă��܂��B�������Ȃ���A�A�����J�J���Ȃ̂Ƃ�܂Ƃ߂��Ƃ���ɂ��A2003�N�ɂ����鐻���ƁE���Y�J���҂̎��Ԃ�����l����́A���{��20.09�h���ƂȂ��Ă���A�f���}�[�N��32.18�h���A�m���E�F�[��31.55�h���A�h�C�c��29.91�h���̂قڂR���̂Q���x�̐����Ɏ~�܂��Ă��܂��B�A�����J��21.97�h���A�t�����X��21.13�h���A�C�M���X��20.37�h���Ɣ�ׂĂ��A�����������Ƃ���ƂȂ��Ă��܂��B�A�����J�J���Ȃ��W�v���Ă���A�����J�A���[���b�p�A�Ȃ�тɃA�W�A�V���H�ƍ��v31�J���̂Ȃ��ŁA13�ʂɂ������A�ƂĂ��u���ۓI�ɂ݂ăg�b�v���x���v�ȂǂƂ����������Ƃ͂������A�ނ����i���̂Ȃ��ł��A���ʂ����ʂɑ�����Ƃ���Ȃ���Ȃ�܂���B
�����Y�Ƃɂ��Č��Ă��A�Ƃ�킯�������i�����ƁA��ʋ@�B�����ƁA�d�C�@�B��
���ƂȂǂŁA�Ⴓ�̖ڗ��Ƃ���ƂȂ��Ă��܂��B�i�}�\�W�j

�o�J�ϕł́A�����̍��۔�r�̈ꗗ�\�iP.53�j���ꉞ�f�ڂ��Ă��܂����A���̕\�͒��L�Ɂu�e�����Ƃɓ��v�̎������قȂ邽�߁A�����Ȕ�r�͍���ł���v�Ƃ��Ă���悤�ɁA
���o�J�ϕŌf�ڂ��Ă���f�[�^�́A���{�́u���J�����Ԃ���������v�ƕēƂ́u�x���Ώێ��Ԃ���������v���r�������̂ŁA��`�̈قȂ�������ꏏ�ɕ��ׂĂ���B
���������^�ȊO�̖@����O�̕�����������܂�ł��炸�A�u�R�X�g�v�Ƃ��Ă̍��۔�r��A�K�ł͂Ȃ��B
�Ƃ������_������A����������āA�킪���̐l����R�X�g���������ǂ����͔��f�ł��܂���B
�u�x���Ώێ��Ԃ���������v�Ƃ����̂́A��G�c�ɂ����A����J�����ԂƏ���O�J�����Ԃ𑫂������̂ŁA��������J�����ԂƏ���O�J�����Ԃ̘a�ł���u���J�����ԁv�Ƃ̈Ⴂ�́A�u�x���Ώێ��ԁv�ɂ́u�L���x�ɂ̎擾���v���܂܂�Ă���A���l���傫���Ȃ�Ƃ������Ƃł��B�u���Ԃ���������v�͎x�����ꂽ������J�����ԂŊ����ĎZ�o����̂ŁA�u�x���Ώێ��Ԃ���������v�́A�u���J�����Ԃ���������v�ɔ�ׂĕ��ꂪ�傫���Ȃ�A���ʂƂ��Ē����͒Ⴍ�Z�o����Ă��܂��܂��B�h�C�c�̂悤�ȍ��͔N���L���x�ɂ������̂ŁA���̉e���͂���߂đ傫���Ȃ�܂��B
�x���Ώێ��Ԃ���������Ǝ��J�����Ԃ��������
�u�x���Ώێ��ԁv�Ƃ́A���{�I�ȕ\��������A�����ނ�
| ����J�����ԁ|�������Ύ��ԁ{���ߘJ������ |
�̂��Ƃł���B���Ă̐��Y�J���҂͎��ԋ�����{�ƂȂ��Ă��邪�A�x�������������z�́A
| {���ԋ��~�i����J�����ԁ|�������Ύ��ԁj}�{�i���������~���ߘJ�����ԁj�{�ꎞ�� |
�ƂȂ�B���̑��z���A
| �x���Ώێ��ԁ�����J�����ԁ|�������Ύ��ԁ{���ߘJ������ |
�Ŋ��������̂��u�x���Ώێ��Ԃ���������v�ł���B
����A�x�����z���A
| ���J�����ԁ�����J�����ԁ|�������Ύ��ԁ|�L���x�Ɏ擾���{���ߘJ������ |
�Ŋ���A�u���J�����Ԃ���������v�Ƃ������ƂɂȂ�B
���Ȃ킿�A�u�x���Ώێ��Ԃ���������v�́A�u���J�����Ԃ���������v�ɔ�ׂāA���ꂪ�u�L���x�Ɏ擾���v�����傫���Ȃ�̂ŁA���z���Ⴍ�Ȃ��Ă��܂��B |
�Ȃ��A���ẮA���{�o�c�A�͓��{�̒����������u��i�����̂Ȃ��ł��g�b�v���x���v�Ƃ��Ă��܂������A2004�N�Ōo�J�ϕł́A�u���E�̃g�b�v���x���v�ɉ��߂��܂����B����́A���{�̒����������A���o�ł����ΑO�����x���ł���A���o�E�S�̂ł́u�g�b�v���x���v�Ɉʒu����Ƃ��Ă��A���������Ŕ�ׂ�u�g�b�v���x���v�Ƃ͂����Ȃ����Ƃ�������F�߂����̂Ƃ����܂��B2005�N�łł́u���ۓI�ɂ݂ăg�b�v���x���v�Ƃ���Ɍꊴ���g�[���_�E�����Ă��܂��B�i�u������v�ł́u���E�̂Ȃ��Ńg�b�v���x���v�ƕ\�L�j
���{�o�c�A�������Ă�������̍��۔�r�̃f�[�^�Ɋ�Â��āA
�����J�����Ԃ�����ɑ�����B
�����������łȂ��A�@����O�̕�������������������Ԃ�����l����ő�����B
�Ƃ������H���s���ƁA���{��100�Ƃ��āA�A�����J��110.1�A�h�C�c��124.4�Ƃ������ƂɂȂ�A
�O�q�̃A�����J�J���Ȃ̃f�[�^�Ƃقړ��l�̌X���ɂȂ�܂��B�i�}�\�X�j
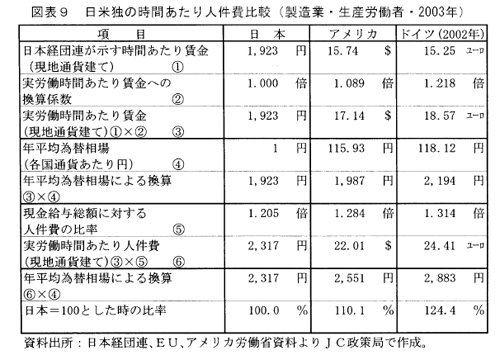
��ʓI�Ɂu���{�͕���������̊����������̂ł́v�Ƃ����v�����݂�����܂����A���{�͎�v��i���̂Ȃ��ŁA�Љ�ۏ�W�̔�p�Ȃǂ��Ⴂ���߂ɁA�����i�������^���z�j�ɑ�������ȊO�̐l����̔䗦����r�I�ɒႢ���Ƃɗ��ӂ��Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B�i�}�\10�j
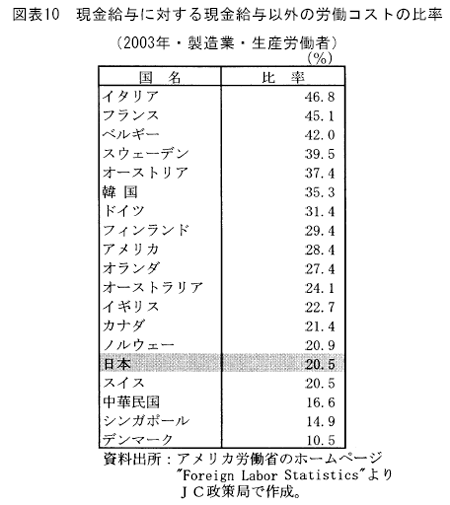
�Ȃ��o�J�ϕł́A
�E��������^�̈����グ�́A���z�l������قڎ����I��1.7�{�����グ�邱�ƂɂȂ�B�iP.52�j
�Ǝw�E���Ă��܂��B���{�ł́A����������ɑ��āA�ꎞ���⏊��O�����̔䗦�������ȏ�A���R�̂��Ƃł��B������O�̂��Ƃ��A�������ł��邩�̂悤�ɏ������Ă�̂́A�t�F�A�Ȏp���Ƃ͌�����Ƃ���ł��B
�����������グ��A��Ƃ̎Љ�ی������S�ɒ��˕Ԃ�͎̂����ł��B����A�Љ�ی������S�̊g��͕s���ł͂���܂����A���S�����\�Ȍ��舳�k����̂́A�Љ�ۏᐧ�x�̐��x�v�̖��ł���A�����}���ɂ��ׂ��ł͂���܂���B
�킪�������Ƃ̎��Ԃ�����l����A��i���̂Ȃ��Œ���ʂɂ܂ŗ�������ł��܂��������Ƃ��ẮA
1.�킪���̐l��������L�тĂ��Ȃ�����A�A�����J��[���b�p�����̐l����͏㏸�𑱂��Ă���B
2.���[���Ȃǃ��[���b�p�̈בփ��[�g���h���ō������Ă���A�h�����[�g����r�I���肵�Ă�����{�ɔ�ׂāA���[���b�p�̐l������������v�Z�����B
�Ƃ����Q�̗��R�ɂ����̂ł��B�i�}�\11�j
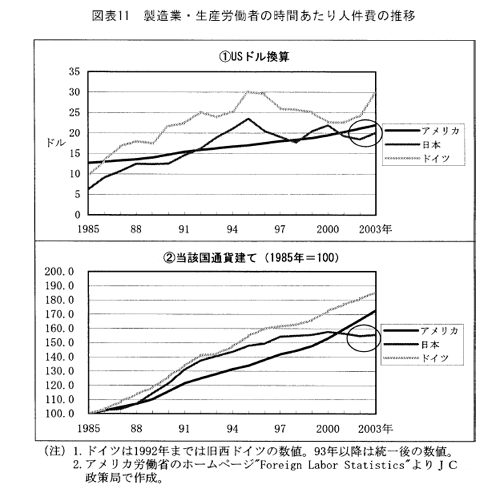
�������A���ۋ����͌����̈בփ��[�g�̂��Ƃōs���Ă���킯�ł�����A�u���[���b�p�̐l����́A�בփ��[�g�̂����ō��������邾�����v�Ƃ��������͒ʗp���܂���B<�y�[�W�̃g�b�v��>
(2) �킪���̐l������ƈבփ��[�g�̊W
85�N�X���̃v���U���ӂ́A�����P�h����230�~���x�ł������בփ��[�g���~�������ɗU��������̂ł������A����́A���Ă̐����Ƃ̘J���R�X�g�̊i�����בփ��[�g�ɂ���Ē�������A�Ƃ����A�����J���{�̖��m�Ȉӎv�ɂ����̂ł����B
�v���U���ӂɐ旧��85�N�R���A�A�����J�̎�v������Ѓf�[�^�E���\�[�V�Y�Ђ́A�x���c�F���E�ď㉺���@�����o�ψψ����̗v���Ɋ�Â��ă��|�[�g���o���܂������A���̃��|�[�g�́A
��1984�N�̓��{�̐����ƃR�X�g�̓A�����J��71���ł������B
���J���R�X�g�A���{�R�X�g�A�G�l���M�[�R�X�g�̂Ȃ��ŁA���Ă̐����R�X�g�̍��̍ő�̌���
�ƂȂ��Ă�����̂́A�J���R�X�g�ł���B�A�����J��100�Ƃ��Ĕ�r����ƁA���{��84�N��60�ł������B
�����ĂQ���Ԃ̐����R�X�g���I�ɋύt�����邽�߂ɂ́A�P�h����237�~�ł͂Ȃ��A�P�h����168�~���x�łȂ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ƃł���B
�Ǝ咣���Ă��܂��B
���Ȃ݂ɁA�A�����J��100�Ƃ��āA���{�R�X�g�͓��{��96�ŁA���Ă��قړ������A�G�l���M�[�͓��{��188�œ��{�̂ق������R�X�g�ƂȂ��Ă��܂����B86�N�̂킪���o�ϔ����ł́A�u�~���́A�A�o�֘A��Ƃ̒��������܂ޘJ���R�X�g���h�����Ăł݂Ĉ����グ�A��荑�ۓI�ɋϓ���������v���̂ł���Ǝw�E���Ă��܂��B�i�}�\12�j
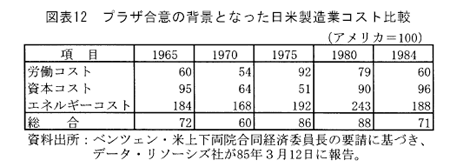
���ہA�~���̗���������87�N�ȍ~�́A�قڃA�����J�Ɠ��{�̘J���R�X�g���C�R�[���ɂȂ鐅���ŁA�בփ��[�g�͐��ڂ��Ă��܂��B95�N�ɂ͂�����u�t�v���U���Ӂv�ɂ���āA�~�������ւ̓]�����e�F����邱�ƂɂȂ�܂������A���̎��_�ł́A���ۂ̈בփ��[�g���v���U���ӂ̎��Ƃ͋t�ɁA���Ă̘J���R�X�g���C�R�[���ɂȂ�ב��������A�~���ɐU��Ă������Ƃ͒��ڂ����Ƃ���ł��B�i�}�\13�j
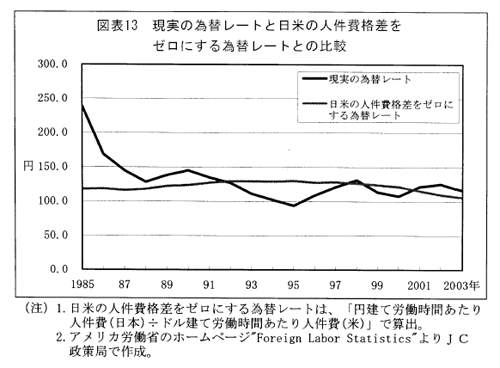
�בփ��[�g�́A1.�����I�ɂ͕��������̈Ⴂ�f���A2.�Z���I�ɂ͋������f����A�Ƃ����Ă��܂��B�������Ȃ���A�v���U���ӈȍ~�̉~���[�g�ɂ��ẮA���̌���v���́A�J���R�X�g�i���ł���Ɣ��f�ł��܂��B
90�N�㖖�ȍ~�A�A�����J�̖f�ՐԎ��͍Ăы}���Ɋg�債����܂����A�������͂��߂Ƃ���A�W�A�����̑䓪�ɂ��A�A�����J�̖f�ՐԎ��ɐ�߂�Γ��Ԏ��̔䗦�͏k�����Ă��Ă��܂��B�Ƃ͂����A�ˑR�Ƃ��ċ��z�Ȃ��̂ł��邱�Ƃ͕ς�肠��܂���i�}�\14�j���A�܂��A�A�����J�̃A�W�A��������̗A�����A���{����̗A���̑�ւł��镔�����傫�����Ƃ͔ے�ł��܂���B���������_���炷��A�Γ��Ԏ��̔䗦���k�������Ƃ͂����A�ב֕ϓ��v���͊�{�I�ɕω������ƌ��邱�Ƃ͂ł��܂���B���[���͑h���ő啝�ɏ㏸���Ă���A�����̐l�������A�ϓ����̊g��Ƃ������ƂŁA�������グ���s��������ƂȂ��Ă��܂��B2003�N�̎��_�̃f�[�^�ł́A�킪���̘J���R�X�g�́A�A�����J�ɔ�ׂĒႭ�Ȃ��Ă���A���̓_���炷��A�בւ͉~�������ɂȂ�₷���ł���Ƃ����܂��B���ہA2004�N�ɂ͑h���ʼn~�������ɐU��Ă��܂��B�~���[�g�̈����}�邽�߂ɂ́A�K���Ȑl������̊m�ۂɂ���āA
1.���ĘJ���R�X�g�̋ύt��}��B
2.�l����𒆐S�Ƃ��������g��ɂ��A�O���哱�E�A�o�ˑ��^�̌o�ϑ̎��ƂȂ�Ȃ��悤�ɂ��Ă����B
���Ƃ��d�v�Ƃ����܂��B
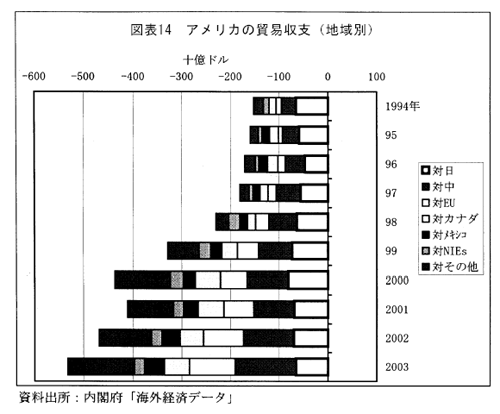
<�y�[�W�̃g�b�v��>
(3) �t�����l������l����i�P�ʘJ���R�X�g�j�̍��۔�r
�בփ��[�g�Ŕ�r�����l������d�v�ł����A�����Əd�v�Ȃ̂́A�P�P�ʂ̕t�����l���ǂ̂��炢�̐l����ʼn҂��o�������A�Ƃ����t�����l������l����P�ʘJ���R�X�g�ł��B
���{�o�c�A���A2003�N�Ōo�J�ϕɂ����āA
�E���ۋ����ɂ��炳���Y�Ƃɂ����ẮA���l����̐����̂�����Ƃ������ɉ����A�u���Y�P�ʓ�����
�̐l����v�Ƃ����������̕]�����d�v�ł���B�i���P�ʘJ����p�j�iP.39�j
�Ǝ咣���Ă��܂��B
2003�N�ŁA�Ȃ�т�2004�N�Ōo�J�ϕł́A��v���̒P�ʘJ���R�X�g���f�ڂ��Ă��܂����A����ɂ��ƁA�����Ƃɂ��ẮA���Ȃ��Ƃ��h�C�c�A�C�M���X�́A�P�ʘJ���R�X�g���킪�����������ƂȂ��Ă��܂��B2005�N�Ōo�J�ϕł́A�P�ʘJ���R�X�g�Ɋւ��Č��y����Ă��܂��A����́A�킪���̒P�ʘJ���R�X�g���A��i�e���̂Ȃ��ŁA����߂ĒႢ�����ƂȂ��Ă��܂������Ƃɂ����̂Ǝv���܂��B
�n�d�b�c�̎�������Z�o���������Y�Ƃ̒P�ʘJ���R�X�g�́A���{��100�Ƃ��āA�C�M���X138.0�A�h�C�c��130.0�A�A�����J��117.3�A�t�����X�A�C�^���A��104.1�ƂȂ��Ă���A��v���̂Ȃ��œ��{�̐l��������Ƃ������Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�i�}�\15�j
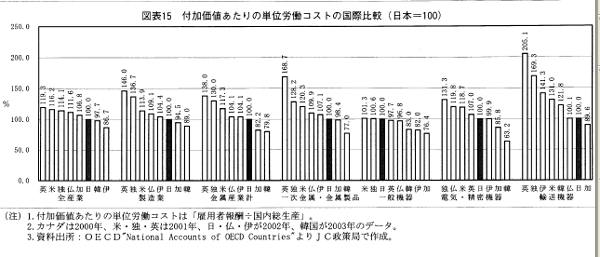
�����Y�Ƃ̊e�Ǝ�ɂ����Ă��قړ��l�̌X���ƂȂ��Ă���A�Ƃ�킯�A���@�퐻���Ƃł́A���{��100�Ƃ��āA�C�M���X205.1�A�h�C�c169.3�A�C�^���A141.3�A�A�����J131.0�A�؍�121.8�A�t�����X100.1�Ƃ킪���̒P�ʘJ���R�X�g�̊��������ۗ��Ƃ���ƂȂ��Ă��܂��B�Ȃ��ł��؍��ɔ�ׂĂ������ł��邱�Ƃ͒��ڂ����Ƃ���ł��B<�y�[�W�̃g�b�v��>
| �S�D��������ٗp����b�Ƃ������ۋ����͂̋����� |
(1) ��������ٗp����b�Ƃ������ۋ����͂̋�����
�o�J�ϕł́A
�E�f�W�^�������邱�Ƃ̂ł��Ȃ��A�A�i���O�I�ȋZ�p��m�E�n�E�A���Ƃ��Βm�I�n�����s�m�����ɑΉ�����m�E�n�E�Ƃ��������̂̉��l���}���ɍ��܂��Ă���B���������\�͂���Ă�͂������A�u����́v�̌���ł���B����́A�����̐l�������Ԃɂ킽����H�I�Ȍo����ςݏd�ˁA�p���I�Ȓ~�ς�ʂ��ē�������̂ł���A�����Ɛl�ނ��琬�����E��̕��y�Ƃ��Ē蒅������̂ł��낤�B�iP.4�j
�E�u����́v�͈꒩��[�ɐ�����̂ł͂Ȃ��B�ٗp�ƘJ���������I�Ɉ��肳���Ă����A���S���āA���Ԃ������Ĕ\�́E�ӗ~�̌���Ɏ��g�ނ��Ƃ��ł���B�iP.5�j
�E�u�������v�A�u�Ȋw�Z�p�n�������v�̌���ƂȂ�̂��A�l�ނ̂������I�ȗ́A�u�l�ޗ́v�̎��I�����̌���ł���B��Ƃɂ����ċ��߂���̂́A���ۋ����̂Ȃ��ŏ\���Ƀ��[�_�[�V�b�v�����A���l�n���̂��߂ɂ��Ă�͂��ő�����p�ł���l�ނł���B�������A��Ɗ������x���鑽���̐l�X�̐l�ޗ͂̒�グ���͂��邱�Ƃ��d�v�ł���B�iP.17�j
�E���{��Ƃ́A�]������u�l���ɂ���p���v���o�c�̍����ɐ����Ă������A���܂̂悤�Ȏ���ɂ����Ă��A�l�Ɛl�Ƃ̂Ȃ�����d���������{�I�o�c�̂悳���Ċm�F���ׂ��ł���B�iP.31�j
�E�l�ނ���������Ƃ́A�]�ƈ��ɐ���������^���A���͂����ƂƂ��ĔF�m�����B���̂��Ƃ����ʓI�ɁA��Ƃ������ꂽ�l�ނ��m�ۂ��邽�߂̑傫�ȗv���ƂȂ�B�iP.31�j
�E�]�ƈ��ɑ��ẮA�ٗp�ƘJ�������̈���ɓw�߁A�g�D�ɑ���ӔC���A�g�D���x�������Ƃ��Ă�
�ϗ��ς�O�ꂷ�邱�Ƃ��s���ł���B�iP.47�j
�E���{�̊�Ƃ̋����͂��x���Ă���̂͌���̏]�ƈ��ł���B������u���[�J���[�A�z���C�g�J���[���킸�A�]�ƈ��͐E��ł̌o����ʂ��ċZ�p�E�Z�\�����߂Ă����iP.47�j
�ȂǂƎw�E���A�]���ɂ������āA��������ٗp�̈Ӌ`���������Ă��܂��B���������l�����͂����ƑS���������̂ł��B
�������Ȃ��炱��́A���������{�o�c�A�����Ă���u�ٗp�̃|�[�g�t�H���I�v�̍l�����Ƃ͑��e��Ȃ����̂ł��B�i�}�\16�j
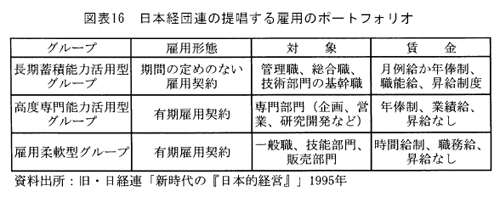
���{�o�c�A��2003�N�S���ɔ��\�����A�u�Y�Ɨ͋����̉ۑ�ƓW�]�|2010�N�ɂ�����킪���Y�ƎЉ�|�v�ł́A���Ԃ��哱����Y�Ɨ͋����̊�{�����Ƃ��āA
1.�Ő�[�Z�p�̊J���ƎY�Ɖ�
2.�V�����T�[�r�X�Ƃ̏o���E�g��
3.�����Y�Ƃ̌������E���t�����l��
���f���Ă��܂����A�Y�Ɨ͋����̂��߂̐l����}���Ȃǂ́A�ЂƂ��Ƃ��咣���Ă��܂���B�ނ���A���̂Ȃ��ł́A�u�ǎ��Ȍٗp�@��̊m�ہv�������Y�Ɨ͋����̖ړI�ł���Ƃ��Ă��܂��B
�u���E�I�Ȍ����J�����_����{�����ɂ����Č`���E���W�����A����𒆊j�Ƃ��ĐV���ȋZ�p�n�o�𐄐i���A���ʂƂ��Ă̋Z�p�E���i�����Ɖ�����v���Ƃɂ���āA�u�킪���̗D�ʐ����ێ��E�������Ă����v���Ƃ��߂����Ȃ�A���R�Ƃ�����ł��傤�B
���{�o�c�A�̂Ȃ��ɂ����Ă��A�K�������u�ٗp�̃|�[�g�t�H���I�v��ӓ|�ł͂Ȃ��A�u�ٗp�̃|�[�g�t�H���I�v���i�̍l�����ƁA��������ٗp����b�Ƃ��Ă킪���̋����͂��m�ۂ��A�������J���Ă������Ƃ���l�����Ƃ����݂��Ă���Ƃ����܂��B
�����Y�Ƃ��A����Ƃ����{�̊�Y�ƂƂ��Ĕ��W���Ă������߂ɂ́A���t�����l���i�̊J���E���Y�����Ƃ��Ȃ���C�O���Y���_�Ƃ̐��ݕ����ɂ���āA���ۓI�Ȗ������Ƃ�}��Ȃ���Ȃ�܂���B���̂Â���Y�ƁA�Ƃ�킯���E�Ő�[�̐V���i�����ЂŊJ�����Ă����ƁA���邢�͍��x�ȎC�荇�킹�Z�p�E�Z�\�A��肱�ݓ��̋Z�p�ɂ���āA���i���A���@�\���i�G�ɑg�ݍ��킹�Đ������Ă���悤�Ȋ�Ƃł́A�Z�\�E�A���E�ɂ��Ă��A��������ٗp����{�Ƃ��āA���x�n���̋Z�p�E�Z�\�A���邢�͌���̏���m�b�A�m�E�n�E�Ȃǂ�~�ς��Ă������Ƃ���ɕK�v�ł��B<�y�[�W�̃g�b�v��>
(2) ���l�Ȑl�ނ̊��p�Ƒ��l�Ȍٗp�`�ԂƂ̍���
���{�o�c�A�́A�o�J�ϕɂ����āA
�E���l�Ȕ��z�A���l�ς����l�X�̋��́E�������A�傫�Ȑ��ʂ������炷�B�iP.4�j
�E�u���l���v�Ƃ����ʂɂ����ẮA�����l�ɂ����l�ȃj�[�Y������ƂƂ��ɁA��Ƃ����l�Ȑl�ނ�K�v�Ƃ��Ă���B����炪�őP�ɑg�ݍ��킳��A���l�œK���͂̍����g�D������グ�Ă������Ƃ��K�v�ł���A������\�Ƃ��邳�܂��܂ȓ������̑I�������������A���ꂼ��ɍœK�Ȑl���������x���\�z���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�iP.5�j
�E���ЁA���ʁA�N��Ȃǂ��܂��܂ȃo�b�N�O���E���h�����l�ނɊ���̏����A���l�������ݏo���_�C�i�~�Y�����n���͂�U�����āA��Ƃ̊������E�ɉh�������炷�d�g�݂������Ă����K�v������B�iP.30�j
�E21���I�ɂ������Ƃ̐l���Ǘ��̎�ڕW�́A�u���l�����������K���͂̍����g�D�̌`���v�ł���A�������������o�c���ۑ�ƂȂ�B�ٗp�E�A�ƌ`�Ԃ̑��l���́A�ٗp�@��̑n�o�E�g��A�l����Ǘ��̌������Ƃ����ϓ_�����łȂ��A��Ƃ̑����E���W�̂��߁A�n��������g�D���y���������Ă������߂ɂ��d�v�ł���B�iP.31�j
�E1995�N�ɁA���o�A�́A�u�ٗp�̃|�[�g�t�H���I�v�i�ٗp�̍œK�Ґ��j��������A����͑��l�Ȍٗp�`�Ԃ��œK�ɑg�ݍ��킹�A���ω��ւ̏_��ȑΏ��Ɗ�Ƃ̋����͂̋������Ӑ}�������̂ł���B����ɁA�����ł́A�J���Ҕh������ȂǁA���ڌٗp�ȊO�̐l�ފ��p���������Ă���A�������܂߂��l�ފ��p�̍œK�|�[�g�t�H���I�̒Nj����d�v�ƂȂ��Ă���B�iP.32�j
�ȂǂƎ咣���Ă��܂��B
�u���l�Ȕ��z�A���l�ς����l�X�̋��́E�����v���d�v�Ȃ��Ƃ��A�ے肷��l�͂��Ȃ��ł��傤�B�������Ȃ���A���l�Ȑl�ނɊ��Ă��炤�Ƃ������ƂƁA�ٗp�`�Ԃ𑽗l������Ƃ������Ƃ́A�K���������т��Ȃ��͂��ł��B�u���l�Ȕ��z�A���l�ς����l�X�v�ɒ����ɂ킽���Ďd�������Ă�����Ă����A�u���l�������ݏo���_�C�i�~�Y�����n���͂�U�����āA��Ƃ̊������E�ɉh�������炷�v���Ƃ��ł��܂��B<�y�[�W�̃g�b�v��>
(3) ���{�ł́A���O���ɔ�ׂėL���ٗp�̔䗦������
�J���͒����E�ڍW�v�ɂ��2004�N�V�`�X�������ł́A�����������ٗp�҂ɑ���K�̐E���E�]�ƈ��i�p�[�g�E�A���o�C�g�A�h���E�_��E�����A���j�̔䗦�́A31.5���ƂȂ�A�O�N�������1.3�|�C���g�������Ă��܂��B
�J�������E���C�@�\�����s���Ă���u�f�[�^�u�b�N���ۘJ����r2005�v�ɂ��A2002�N�ɂ�����A�Ǝ҂ɐ�߂�p�[�g�^�C�}�[�̔䗦�́A���{��25.1���ƂȂ��Ă���̂ɑ��A�C�M���X23.0���A�h�C�c18.8���A�J�i�_18.7���A�t�����X13.7���A�A�����J13.4���A�C�^���A11.9���Ɏ~�܂��Ă���A���{���f�V�������ō����L�^���Ă��܂��B�j�q�������Ƃ��Č��Ă��A�p�[�g�^�C�}�[�̔䗦�͂f�V�ō��ƂȂ��Ă��܂��B�u�p�[�g�^�C�}�[�v�̒�`�ɂ��āA���{�͏T���J��35���Ԗ����A���̍��X�͏T����30���Ԗ����ƂȂ��Ă��܂����A���{�ł́A�p�[�g�^�C���̘J�����Ԃ����Ј��ɔ�ׂĕK�������Z���Ԃł͂Ȃ����Ƃ��炷��A�����Ȕ�r�ł͂���܂���B
�܂��A�����J�̃f�[�^�́A���ꂪ�A�Ǝ҂ł͂Ȃ��Čٗp�҂ł��̂ŁA���̍��X�������������߂ɏo�邱�ƂɂȂ�܂����A����ł����{���啝�ɒႭ�Ȃ��Ă��܂��B
2002�N�ɂ�����A�ٗp�҂ɐ�߂�e���|�����[�ٗp�҂̔䗦�́A���{��13.5���ɑ��A�t�����X14.1���A�J�i�_13.0���A�h�C�c12.0���A�C�^���A9.9���A�C�M���X6.1���A�A�����J4.0���i2001�N�j�ƂȂ��Ă���A�f�V�����Ńt�����X�Ɏ����ō��������ɂȂ��Ă��܂��B�Ȃ��A���̃f�[�^�ł́A���{�̒�`�́u���X�܂��͂P�N�����̌ٗp���Ԃ̎ҁv�ł���A�ꕔ�̔h���J���҂Ȃǂ������Ă��炸�A���̍��X�ɔ�ׁA�ނ����`�������Ȃ��Ă��܂��B�i�}�\17�j
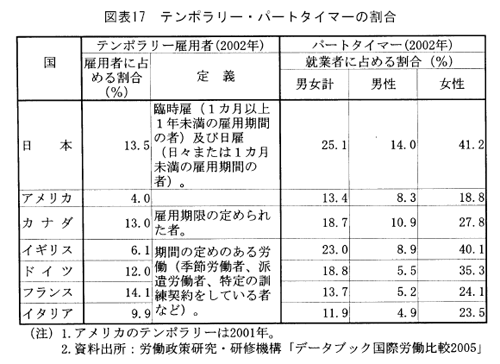
<�y�[�W�̃g�b�v��>
(4) �ΘJ�҂̃j�[�Y�ɂ������������̑I�����g���
���{�ɂ�����ٗp�`�Ԃ̑��l���́A�o�c�҂ɂ������̗}����ٗp�̏_���ړI�Ɋg�債�Ă��邽�߁A���Ј��E�Ј��Ԃ̒����E�J�������ɑ傫�Ȋi��������A�ΘJ�҂̃j�[�Y�ɍ������I�����̊g��Ƃ́A��������̂ɂȂ��Ă��܂��B
�ΘJ�҂̑��ɂ����Ј��Ƃ����������ł͂Ȃ��A�p�[�g��h���Ƃ������������ł̌ٗp�`�Ԃɑ�����̃j�[�Y������܂����A�h���J���ҁA�_��Ј��̂����̎��ɂS�����A���Ј��Ƃ��ē������Ƃ��ł��Ȃ��������߂ɔh���J���҂ɂȂ��Ă���A�Ƃ��������ɖڂ��Ԃ��Ă͂Ȃ�܂���i�}�\18�j�B�܂��A�R������Ј������̏A�ƌ`�Ԃɕς肽���ƍl���Ă���A���̂����W���ȏオ�u���Ј��v����]���Ă��܂��B
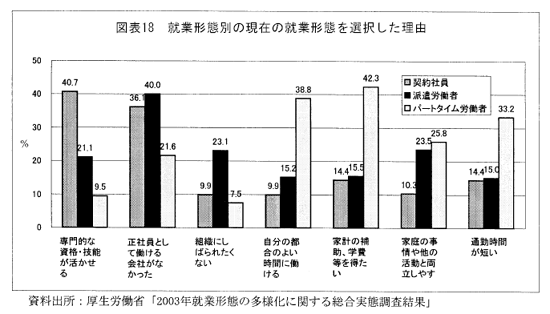
�����J���Ȃ́u2003�N�x�A�ƌ`�Ԃ̑��l���Ɋւ��鑍�����Ԓ������ʁv�ɂ��A��Ƃ��Ј����ٗp���闝�R�̑��ɂ����Ă���̂́A�u�����̐ߖ�̂��߁v�ł���A51.7���ɒB���Ă��܂��B�����ŁA�u�P���A�T�̒��̎d���̔ɊՂɑΉ����邽�߁v��28.0���A�u�i�C�ϓ��ɉ����Čٗp�ʂ����邽�߁v��26.5���ƂȂ��Ă��܂��B
�܂��A2002�N�̈�ʘJ���҂ɑ���p�[�g�^�C���J���҂̒��������́A�j����39.1���A������53.2���ƂȂ��Ă��܂��B1990�N�ɂ͒j����45.9���A������58.9���ł��������ƂƔ�r����ƁA�����i���͊g��X���ɂȂ��Ă���Ƃ����܂��B�i�}�\19�j
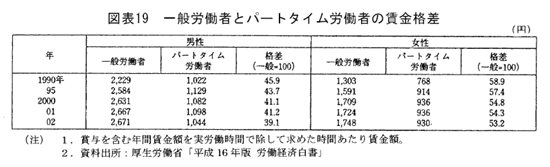
�o�J�ϕł́A
�E��Ƃ́A���l�ȉ��l�ς�l���������l���A���S���ē�������I���ł��A�����ɉ����ď��������d�g�݂������Ă����K�v������B�iP.32�j
�E�ߋ�10�N���x�́u�A�E���X�͊��v�Ɋw�Z�𑲋Ƃ�����N�҂ɂ��ẮA���Ȃ�̑f���������Ȃ���A��ނȂ��h���A�A���o�C�g�Ƃ��ďA�Ƃ�����Ȃ������l�������ƍl������B�iP.37�j
�Əq�ׂĂ��܂��B
�u�l���ɂ���p���v�iP.31�j���o�c�̍����ɐ�����̂ł���A�ΘJ�҂̃j�[�Y�ɂ������������̑I�����g���}�邱�Ƃ���ł��B���̂��߂ɂ́A�ٗp�̈����ϓ��ҋ��̎����ɂ���āA�ΘJ�҂̐����̈����}��A�ΘJ�҂���肪���������Ĕ\�͂����邱�Ƃ��ł��鏈�����������Ȃ���Ȃ�܂���B����ɁA�N��E���ʂɂ�����炸�������Ƃ̂ł�����������̂��߂ɁA�d���Ɖƒ�̗����x����A60�Έȍ~�̏A�J�m�ۂ̂��߂̐��x�[����}���Ă������Ƃ��K�v�ł��B<�y�[�W�̃g�b�v��>
(5) �h�����Ԃ̉����ȂǘJ���Ҕh���@�̋K���ɘa�͔F�߂��Ȃ�
�o�J�ϕł́A
�E�h�����Ԃ̉����ɂƂ��Ȃ��h����ɔh���J���҂̌ٗp�_��̐\�����`�����ۂ��Ă��邪�A�h���_����ԂⒼ�ڌٗp�ւ̐�ւ��Ȃǂ́A�{�������ҊԂ̌_�R�Ɉς˂�ׂ��ŁA���̂悤�ȕs���R�ȋK���͓P�p���ׂ��ł���B�iP.49�j
�E�����鎩�R���Ɩ��̔h�����Ԑ����i�R�N�j�A�����Ƃ̔h�����Ԑ����i�P�N�j�ɂ��Ă��A���}�Ɋ��ԉ������ׂ��ł���B�iP.49�j
�Ǝ咣���Ă��܂��B
�������Ȃ���A�J���Ҕh���́A�@����u�Վ��I�E�ꎞ�I�ȘJ���͎��������V�X�e���̂ЂƂv�Ƃ��Ĉʒu�Â����Ă���A���Ԃ����肵���������ł��邱�Ƃ�O���ɒu���K�v������܂��B
�h�����Ԃ�����ɉ�������̂ł���A�e���|�����[�ٗp�Ƃ��Ă̐��i�������A�P�Ȃ�ΘJ�҂̊K�w���ɂȂ��邱�ƂɂȂ�܂��B�@�̎�|�܂���A�h���\���Ԃ��Ĕh���J���҂��g�p����ꍇ�ɁA�ٗp�_��̐\�����݂��`�������邱�Ƃ͓��R�̂��ƂƂ����܂��B
���ۓI�Ɍ���A���ϔh�����Ԃ̓A�����J�Ŗ�Q�T�ԁA�C�M���X�Ŗ�X�T�ԁA�t�����X�Ŗ�2.15�T�ԁA�h�C�c�ł͂P�T�Ԉȏ�R�J�������̂��̂�51.4�����߂�i�J�������E���C�@�\�܂Ƃ߁j�Ƃ����ɂȂ��Ă���A�����̍��X�ł͓��{�ƈقȂ�A�u�J���͎��������V�X�e���v�Ƃ��Ă̐��i�����m�ƂȂ��Ă��邱�Ƃ��킩��܂��B
�h���J���҂̃R�X�g�����Ј������Ⴍ�A�ٗp�������e�Ղł��邽�߂ɁA���Ј�����h���J���҂ւ̑�ւ��i��ł��܂����A�J���Ҕh���@�̖ړI�̂ЂƂ́A�J���Ҕh���������ٗp�҂̑�ւƂȂ�A�����ٗp�V�X�e����N�H���Ȃ��悤�ɂ��邱�Ƃɂ��邱�Ƃ�Y��Ă͂Ȃ�܂���B
�h�����Ԃ̊g��Ȃǂ̘J���Ҕh���@�̋K���ɘa�͗e�F���邱�Ƃ͂ł��Ȃ����̂ł��B<�y�[�W�̃g�b�v��>
(6) �h���J���Ȃǔ�T�^�ٗp�҂̎���Ɋւ���J�g���c�̏[��
�ߔN�A�L���ٗp�҂̋}���ȑ����A�A�E�g�\�[�V���O���}�g�債�Ă���Ȃ��ŁA���ԂƂ��Ă͘J���Ҕh���ł���u�U�������v�ȂǁA���܂��܂Ȗ�肪�w�E����Ă��܂��B�h���J���Ɛ����́A�w�����ߌn����Ǘ��ӔC���قȂ���̂ł��i�}�\20�j�B
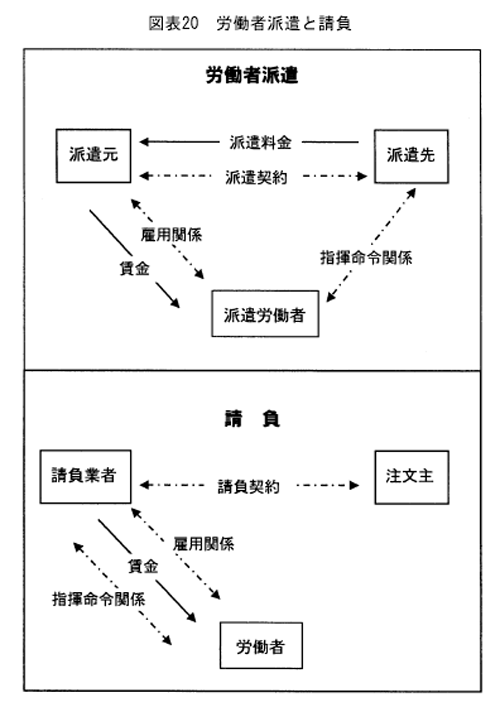
�J���Ҕh���@�����ɔ����A�����ɑ���ēw������������Ă��܂����A�@�̏���͂��Ƃ��A�����A�J�����ԁA���S�q���ȂǁA���L���J�������ɂ��āA�J�g���c���s���Ȃǂ̋�̓I�Ȏ��g�݂��s�����Ƃɂ���āA�Ј��̌����ȏ��������̊m���Ɍ������J���g���̊֗^�����߂Ă������Ƃ��K�v�ł��B
�܂��A�h���J���҂ɂ��ẮA�J���Ҕh���@�̉����ɂ���āA�P�N������ԁA�h���J���҂������ꍇ�A�J���g���ɑ���ӌ����悪��Ƃɋ`���Â����܂����B�P�N�ȓ��̔h���J���҂̎���⑼�̔Ј��̎�����܂߁A�E��̒����ێ��A�E��̈��S�m�ۂ̊ϓ_����A�Ј��̎��ꐔ��E��Ŕ������Ă������E��ւ̉e���Ȃǂɂ��āA����I�ɘJ�g���c���s���̐��𐮂��A�J�g���c���[�����Ă������Ƃ��d�v�ł��B<�y�[�W�̃g�b�v��>
(7) �t���[�^�[�A�j�[�g�ȂǁA��N�Ҍٗp���ւ̑Ή�
�o�J�ϕł́A��N�҂̌ٗp���ɂ��āA
�E��N�w�̌ٗp��肪�[�������������Ƃ��傫�Ȍ����̂P�́A��N�w�ɑ��鋁�l�̕s���ł���B�iP.36�j
�Ǝw�E������ŁA
�E��Ƃ���N�҂ɑ���L�Ӌ`�Ȍٗp�@��𑝂₷�iP.37�j
�E���͂�����Ί�I�Ȑl�ނ֓o�p���Ă����l�����x�����邱�Ƃ��K�v�iP.38�j
�Ƃ̍l�������q�ׂĂ��܂��B
�t���[�^�[��j�[�g�̑����Ȃǎ�N�҂̌ٗp���́A�Z�\�`�����ɍ��x�ȋZ�\��~�ςł��Ȃ����Ƃɂ���āA��N�Җ{�l���L�����A�`����}�邱�Ƃ��ł��Ȃ�����łȂ��A�ʊ�ƂɂƂ��Ă��Z�\�p���Ȃǂ̖ʂŖ�������邱�ƂɂȂ�܂��B����ɂ́A�����̂킪���o�ς��x����l�ނ̊m�ۂ�����ɂȂ�A�䂭�䂭�͌o�ώЉ�̊��͂⍑�ۋ����͂��ێ��ł��Ȃ��Ȃ鋰�������܂��B���ۋ�������������Ȃ��ŁA���t�����l���ɂ�鋣���͋�����}�邽�߂ɂ��A��Ƃ̏�����S���l�ނ̊m�ہE�琬��}�邱�Ƃ��d�v�ł���A���̂��Ƃ́A���{�o�ρE�Љ�̈���I�Ȕ��W�̂��߂ɂ��K�v�ƂȂ��Ă��܂��B
�J�������E���C�@�\���A2003�N11���Ɏ��{�����u�r�W�l�X�E���[�o�[�E���j�^�[�����v�ł́A�V���̗p�̗}���������N�������_�ɂ��āA��Ƃ̉��܂Ƃ߂Ă��܂��B���̂Ȃ��ł́A�u�N��\�������тɂȂ������Ɓv�ɂ���āu�߂������ɒ����w�̊�Ј����s������v���Ƃւ̌��O��A�u�Z�p��`�����ׂ��l�ނ̕s���v�u��y�����y�ւ̃m�E�n�E�̓`�B�̕��f�v�ȂǁA�Z�\�`����肪�ۑ�ɋ������Ă��܂��B
�܂��A2004�N�R���ɂt�e�i�������u�t���[�^�[�̒����\���Ƃ��̌o�ϓI�e���̎��Z�v�\���Ă��܂��B���̒����ɂ��A���Ј��̕��ϔN����387���~�A���U�������Q��1,500���~�ł���̂ɑ��āA�t���[�^�[�i���t�{�̒�`�ł́A15�`34�ŁA�p�[�g�E�A���o�C�g�i�h���܂ށj�܂��͓����ӎv�̂��閳�E�̐l�j�̕��ϔN����106���~�A���U������5,200���~�ƂȂ��Ă���A
�N���i����3.7�{�A���U�����i����4.2�{�ɋy��ł��܂��B�t���[�^�[�����Ј��ɂȂ�Ȃ����Ƃɂ��Љ�S�̂̌o�ϓI�����́A�Ŏ�1.2���~�����A����z8.8���~�����A���~3.8���~�����ƂȂ�A���ڂf�c�o�����ݓI��1.7�|�C���g�����������Ǝ��Z����Ă��܂��B
�o�J�ϕł́A�u�U�߂̃��X�g���v�ւ̓]������������Ă��܂����A��Ƃɂ����Ă��A�������I�Ȋϓ_����A������S���l�ނ̊m�ہE�琬�ɗ͂𒍂��ׂ��ł���Ƃ����܂��B<�y�[�W�̃g�b�v��>
| �T�D�i�b�~�j�}���^���ɂ������̉��x�� |
(1) �i�b�~�j�}���i35�j�ƍŒ��������
�����O�̋���������f�t���̒������A����ɔ����ٗp�`�Ԃ̑��l���Ȃǂ̘J���s��̕ω��Ȃǂɂ���āA���������̒ቺ�X����Y�ƊԁE�Y�Ɠ��̒����i���̊g�傪�i�s���Ă��܂��B�܂��A�d���̐��ʂ��d�������������x�ւ̉���ɂ���āA�l���Ƃ̒����̍��ق��ꕔ�Ŋg�債�Ă��Ă��܂��B
�t�G���������ɂ�鑊��g�y�͂���܂��Ă��邱�Ƃ�����A��Ɠ��ɂ������������𖢑g�D�J���҂��܂߂��Љ�S�̂ɔg�y�����A�����Ȓ��������̊m���Ƌ����Y�Ƃɂ�������������̉��x����}�邱�Ƃ��d�v�ł��B�����J���ł́A���������ϓ_����A�i�b�~�j�}��(35��)�A�Œ��������A�@��Y�ƕʍŒ�����̂R�𒌂Ƃ���i�b�~�j�}���^���𐄐i���Ă��܂��B�i�}�\21�j
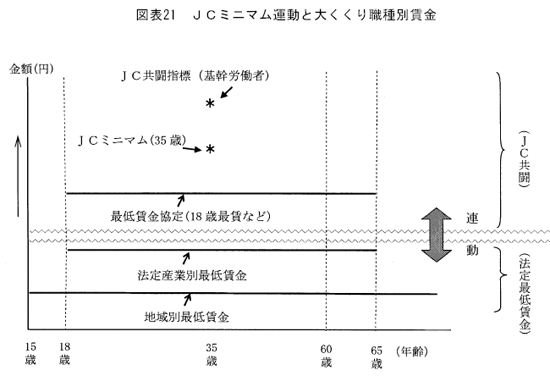
�u�i�b�~�j�}���i35�j�v�́A�����������v��̑��ʂ��l�����Ȃ�����������̉��x����}��ϓ_����A���v���������ԓ��𑍍��I�Ɋ��Ă���210,000�~�Ɛݒ肵�Ă��܂��B35�̋����Y�ƘJ���҂ł���A�Α��N���A�E���A�]���ɂ�����炸�A�����I�ɂ���ȉ����Ȃ����^���Ƃ��Ē��������m�ɉ��x�����Ă����܂��B�i�}�\22�j
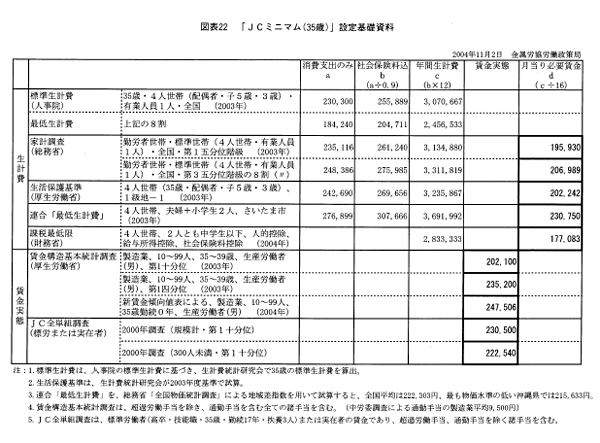
�܂��A��Ɠ��Œ��������ɂ��ẮA18�Œ������149,500�~�ł̒�����}���Ă����܂��B
��Ɠ��Œ��������́A��Ƃɂ���������̉��x���ł���ƂƂ��ɁA�@��Y�ƕʍŒ�����\���̂��߂̍��ӂ����A���̐����ɂ��e����^������̂ł��B�@��Y�ƕʍŒ�����̎��g�݂Ƃ̘A�����������A���g�D�J���҂��܂߂������Y�Ƃœ����ΘJ�ґS�̂̒����̉��x����}�邱�Ƃ��d�v�ł��B<�y�[�W�̃g�b�v��>
(2) �@��Y�ƕʍŒ�����̈Ӌ`�Ɩ���
�o�J�ϕł́A
�E�Œ�������x�ɂ��ẮA���ׂĂ̘J���҂�ΏۂƂ���n��ʍŒ�������x���ݒ肳��Ă�����ӂ݁A����ɉ��㉮���˂��`�Őݒ肳��Ă���Y�ƕʍŒ�����͔p�~���ׂ��ł���B�iP.49�j
�Ǝ咣���Ă��܂��B
�������Ȃ���A�n��ʍŒ�������S�Ă̘J���҂ɓK�p���������̃i�V���i���~�j�}���ł���̂ɑ��āA�Y�ƕʍŒ�����́A�Y�Ƃ�E�킲�ƂɔN���Ɩ��Ȃǂ̓K�p�͈͂��߂�������u��I�J���ҁv�̍Œ�����ł���A�����Ƌ@�\���قȂ��Ă���A���Ƃ��u���㉮�v�Ƃ����悤�Ȕᔻ�͓I�͂���ł��B
���{�̒����\��������ƁA�d���̎��⓭�����Ȃǂ̈Ⴂ�f���āA�Y�Ƃ�E��ɂ��������ꂪ�`������Ă��܂��B�n��ʍŒ�����̑S�J���҂ɑ���e�����i�Œ�����̈����グ�ɂ���Ē��ڒ����������グ����J���҂̊����j�͂킸���P�����x�A����������ɑ��鐅����35�����x�ɉ߂����A�n��ʍŒ�����݂̂ł́A�����̎Y�ƂɂƂ��Ē����̉��x���Ƃ��Ă̋@�\���R�����ɂ���܂��B�Y�ƕʍŒ�����͓��{�̒��������ɓK�������������̂�������̉��x���Ƃ��ďd�v�Ȗ������ʂ����Ă���A�Y�ƁE��Ƃ��Ƃ̒����i�����g�傷����ƂŁA���������̉��x����}��ϓ_��A����ɁA�Y�Ɠ��ɂ�������������̊m�ۂɂ��������Ȃ��V�X�e���ƂȂ��Ă��܂��B
�܂��ߔN�A�ٗp�̗�������ٗp�`�Ԃ̑��l���ȂǁA�J���s�ꂪ�ω��������ŁA�d����E���v�f�Ƃ�����������̌X�������܂��Ă���A�Y�ƁE�E�킲�Ƃ̍Œ�����̏d�v�������܂��Ă��܂��B�Y�ƕʍŒ�����́A���g�D�J���҂ɂ��K�p�����A�u�킪���B��Ƃ��������Ƃ̘g�����Y�ƕʘJ����������V�X�e���v�ł���A�u�Y�ƕʂɌ`�����������̉��x���v�Ɓu���������̊m�ہv�Ƃ��������E�@�\�����ׂ��A����Ƃ��p���E���W��}���Ă����Ȃ���Ȃ�܂���B�i�}�\23�j�A�i�}�\24�j
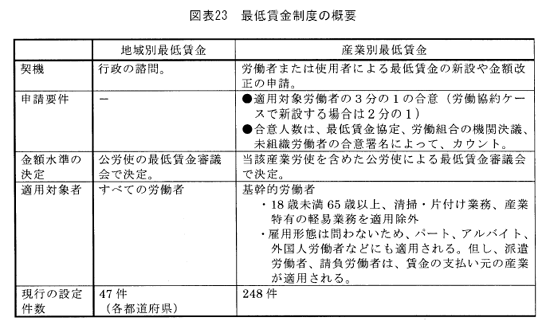
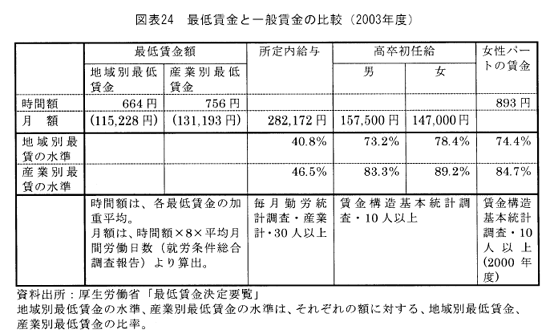
<�y�[�W�̃g�b�v��>
| �U�D�������x�����Ƃ����鐬�ʎ�`�����Ɋւ��� |
�����J���́A�����鐬�ʎ�`�����Ɋւ��āA�u��Q�������E�J������v�ɂ����āA
�����ʎ�`�̖��̂��ƂɁA�P�ɐl����}���Ɏ���u�������x������s���A�g�����̊�ƌo�c��l������ւ̐M������ቺ�����A�����[���ێ��A�Z�p�E�Z�\�̌p���E�琬���낤������B
�������E�������x����ɂ������ẮA�l�ވ琬��}��Ȃ���A�d���̔\�́E���ʂ�K���ɔ��f������A�����Ŕ[�����̍������x�m�����d�v�ł���B
���n���x�̍����Z�p�E�Z�\�̈ێ��E���オ��{�ƂȂ�Z�\�n�E��̏ꍇ�A�����鐬�ʎ�`�����͂Ȃ��܂Ȃ��B
�����ʎ�`����������ꍇ�́A�ΏۂƂȂ�]�ƈ��͈̔́A�����`�ԁA�����̌n�ɂ����鐬�ʔ��f�v�f�̈ʒu�Â��Ȃǂm�ɂ��A�E�����͂ɂ��d���͈̔͂Ɨʂm�ɂ��邱�Ƃ��d�v�ł���B
���J���g�������x�v�E�^�p�E�����ȂNJe�i�K�ŐϋɓI�Ɋ֗^���A�������E�[�����̍������x�ɂ��Ă����K�v������B
�Ǝ咣���Ă��܂��B
����A�o�J�ϕł́A
�E��s����̋M�d�Ȍo�����������A�J�g�̏\���Ȉӎv�a�ʁA�b��������i�߁A�e��Ƃ̎���ɓK�������x�̓����E�^�p���d�v�ł���B�iP.45�j
�Ǝw�E������ŁA
�E�\�́E���ʁE�v���x�ɉ������������x��K�ɉ^�p���邽�߂ɂ́A���ӂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��_���������B�iP.43�j
�E���x�̐v�ɂ������ẮA�]����̍������A�q�ϐ��ɉ������K�Ȋi����ݒ肷�邱�Ƃ��d�v�ł���B�i���̂��ɂ����Ƃ���ɖ����Ɋi����������A�����܂��Ȋ�ɂ��]���ő傫�Ȋi���������肷�邱�Ƃ͔[���������ɂ����B�iP.44�j
�E�]����̍����ڕW�Ǘ����x�̉^�p�ɂ������ẮA�����I�ȃe�[�}�ւ̎��g�݁A����ȉۑ�ւ̃`�������W�A�ڗ����Ȃ����d�v�Ȏd���A��i�̈琬�Ȃǂ��\���ɍl�������ׂ��ł���B�iP.45�j
�E�o�c�g�b�v���炪���x��ς��邱�Ƃ̈Ӌ`��F�����ċ����g�����Ɗ֗^�������ƁA���Ђ̐g�̏�ɂ��������x���\�z���邱�ƁA���x�̋Z�p�I�ȕ�����������������̂ł͂Ȃ��A�]�ƈ��̃��`�x�[�V�����ɗ^����e���ɔz�����āA�ǂ�����ΑS�ГI�Ɏ����������܂邩�ɂ��Đ^���ɍl���邱�ƁA���厖�ł���B�iP.45
�j
�Ƃ̍l�����������Ă��܂��B
�o�J�ϕŒ�Ă��Ă���悤�ȋ�̓I�ȉ��P��́A�����鐬�ʎ�`���������Ă���ꍇ�����łȂ��A�]���^�̂�����N���^�����ł����Ă��s���ȕ��ՓI�Ȃ��̂ł��B���Ƃ��ƁA�N���^�����Ɛ��ʎ�`�����̈Ⴂ�́A�O�҂��N����S�A��҂��\�́E���ʁE�v���x��]������A�Ƃ������́A�O�҂��]�ƈ��̐��U�ɂ킽��v���U�ɂ킽������ŕ悤�Ƃ���̂ɑ��A��҂͒Z���Ԃōv���ƒ����Ƃ��}�b�`�����悤�Ƃ�����̂ł���Ƃ������Ƃł��B
�������A�Z���Ԃ��Ƃ����Ⴂ�͂���ɂ���A�]�ƈ��̍v���x�����ɑ����ĕ�Ƃ������Ƃł͓����ł���A�]���āA�K�ȕ]���A�\�͊J���A�����̖��m���Ƃ����̂́A�ǂ���̎d�g�݂ɂ��Ă��K�v�Ȃ킯�ł��B
�������x�́A���x�v�A�^�p��m�ɂ��A�d���Ɣ\�͂̌��オ�K���ɕ]������鐧�x���\�z���A�����Ŕ[�����̍��������E�������x���\�z���邱�Ƃ���{�ł��B���̂��߂ɂ́A�J���g�������x�v��^�p�ɐϋɓI�Ɋ֗^���A����ɓ���̃`�F�b�N�@�\����ы����@�\�̏[����}���Ă����Ȃ���Ȃ�܂���B
�܂��A�\�́E���ʁE�v���x���d�������������x������ꍇ�ɂ����Ă��A�������d���̑Ή��ł���ƂƂ��ɁA�ΘJ�҂̐��v���d�����̂ł�����Ƃ������i���ς����̂ł͂���܂���B�d���̔\�͔��������邽�߂ɂ́A���v��̈���I�Ȋm�ۂɂ���āA���������肵�Ă��邱�Ƃ��O��ł���A�ΘJ�҂ɂƂ��ĕK�v�Ȑ��v��Œ���m�ۂ��ꂽ���x�Ƃ��邱�Ƃ��K�v�s���ł��B<�y�[�W�̃g�b�v��>
(1) �����Ƃ̒��a���߂����N�ԑ����J������1,800���Ԃ̎���
�����J���ł́A�u��Q�������E�J������v�ɂ����āu�d���E�Љ�E�ƒ됶���̒��a�v��ł��o���A��Ƃ肠�鐶�����Ԃ̊m�ۂ��߂����Ă��܂��B�܂��A���̂��߂ɁA�N�ԑ����J������1,800���Ԃ̑���������A���܂��܂Ȓ����x�ɁE�x�Ɛ��x�̓����ɂ���āA��Ƃ肠�鐶�����Ԃ̊m�ۂ��咣���Ă��܂��B
�����J���ȘJ�������R�c��́A2006�N�R�����Ɋ��������u���Z���i�@�v�̉����Ɍ����āA�u����̘J�����ԑ�ɂ��āv�̌��c���s���܂����B����̉����́A�������̑��l�����i�W����Ȃ��ŁA�S�J���҈ꗥ�̖ڕW���f����@������A�ΘJ�҂̎���ɉ����āA�d���Ɛ����̒��a��}��V���ȓ������̎����𐄐i������̂ł��B�����@�̓K�p��2006�N�S���ȍ~�ƂȂ�܂����A�@�����̎�|�܂��A�g�����̃j�[�Y���Ƃ̎��Ԃɑ������J�����Ԑ��x��^�p�̂�����A�x�Ɛ��x�̏[���ȂǁA�J�����Ԃ⓭�����Ɋւ�镝�L���ۑ�ɂ��ĘJ�g���c���[�������A�������̉��P��}���Ă������Ƃ��K�v�ł��B
�Ȃ�����A�����J����b�ɂ��w�j����߂��邱�ƂɂȂ�܂����A�w�j�ł́A1.�J�����ԓ��̐ݒ�̉��P�Ɋւ����{�I�ȍl�����A2.�����ԘJ���҂̌��N�ێ��Ɏ�����J�����ԓ��̐ݒ�̉��P�Ɋւ��鎖���A3.�玙�E���A�n�抈���A���Ȍ[�������s���J���҂̎���ɉ������J�����ԓ��̐ݒ�̉��P�Ɋւ��鎖���A4.�N���L���x�Ɏ擾���i�̂��߂̎����A�ȂǁA�X�̘J�g����̓I�Ȏ��g�݂�i�߂��ŎQ�l�ƂȂ鎖�����f���邱�ƂɂȂ��Ă��܂��B�܂��A�e�͓I�ȘJ�����Ԑ��x�̊��p�ɂ�菊��J�����ԓ��ł̋Ɩ��̊������߂������Ƃ�A�Z���ԋΖ����x�̓����A�N���L���x�ɂ̌v��I�t�^���x�̐ϋɊ��p�Ȃǂɂ��Ă��A������Ƃ��ċ������Ă��܂��B
�܂��A������琬�x�������i�@�ł́A���Ǝ傪�s���v�������E���{���A�s���v��ɒ�߂��ڕW��B���������ƂȂǂ̈��̊�������ꍇ�Ɏ��Ǝ��F�肷��u�F�萧�x�v��݂��Ă��܂��B���̂Ȃ��ł́A�j�����܂߂��������̌������̊ϓ_����A1.����O�J���̍팸�̂��߂̑[�u�A2.�N���L���x�ɂ̎擾�̑��i�̂��߂̑[�u�A3.���̑��������̌������Ɏ����鑽�l�ȘJ�������̐����̂��߂̑[�u�A�̂����ꂩ�����{���Ă��邱�Ƃ��F������̂ЂƂƂȂ��Ă��܂��B
�܂��A�A���́u2004�����A���P�[�g�v�ɂ����Ă��A�u�����̕��S�����y�����邽�߂ɕK�v�Ȃ��Ɓv�̑�P�́A�u���ԊO�J���팸�v�ł����50.8�������Ă��܂��B�o�J�ϕɂ����Ă��A�u�]�ƈ��̓����₷���ɔz�������q��Ďx���ɁA�ϋɓI�Ȏ��g�݂����߂��悤�v�Əq�ׂ��Ă��܂����A���l�ȓ������̑I�����̒ƂƂ��ɁA�����J�����Ԃ̒Z�k���d�v�ȉۑ�ƂȂ��Ă��܂��B�i�}�\25�j
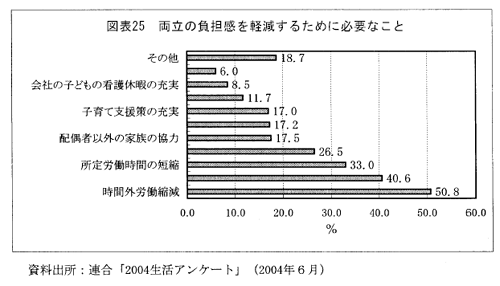
�����ԘJ�������A�����Y�Ƃœ������ׂĂ̋ΘJ�҂ɂ��ĔN�ԑ����J������1,800���ԑ�𑁊��Ɏ���������g�݂��d�v�ƂȂ��Ă��܂��B�����ɁA��Ƃ肠�鐶�����Ԃ̊m�ۂɂ���Ďd���Ɛ����̒��a��}��A���ꂩ��̐V���ȃ��C�t�X�^�C�����\�z����ϓ_������A���g�݂�i�߂Ă����܂��B<�y�[�W�̃g�b�v��>
(2) ���{�̘J�����Ԃ̌���
��L�A�u����̘J�����ԑ�ɂ��āv�ł́A���{�̔N�ԑ����J�����Ԃ������ނ�1,850����
���x�ƂȂ��Ă���̂́A�p�[�g�^�C���J���҂̑����ɂ����̂ł���Ǝw�E���Ă��܂��B�i�}�\26�j
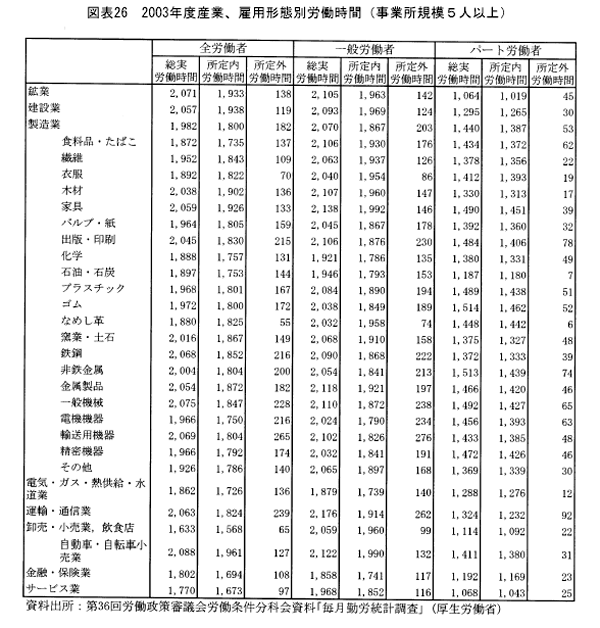
�t���^�C���J���҂̘J�����Ԃ́A2003�N�x��2,016���ԂƂȂ�A2000�N�Ɣ�r�����17���ԑ������܂����B�����Y�Ƃ̃t���^�C���J���҂ɂ����Ă��A�S�|�Ƃ�2,090���ԁA��S���������Ƃ�2,054���ԁA�������i�����Ƃ�2,118���ԁA��ʋ@�B�����Ƃ�2,110���ԁA�d�C�@�B�����Ƃ�2,024���ԁA�A���p�@�B�����Ƃ�2,102���ԁA�����@�B�����Ƃ�2,032���ԂƂȂ��Ă���A������̎Y�Ƃɂ����Ă��A2,000���Ԃ�傫�������Ă��܂��B
����ɑ��āA�����J���Ȃ̐��v�ɂ��2002�N�̔N�ԑ����J�����ԁi�����Ƃ��Đ����ƁA���Y�J���ҁj�́A���{��1,954���ԁA�A�����J��1,952���ԁA�C�M���X��1,888���ԁA�h�C�c��1,525���ԁi1999�N�j�A�t�����X��1,539���ԂƂȂ��Ă��܂��i�}�\27�j
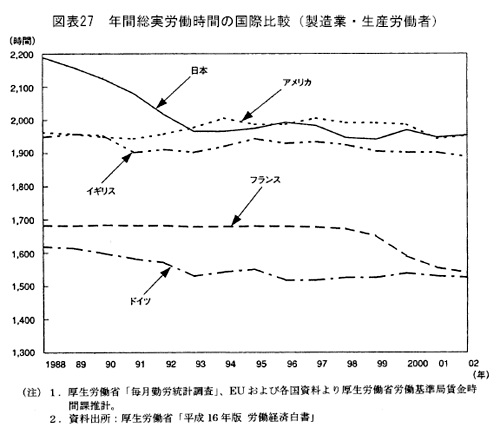
�����J�������Γ��v���琄�v����2003�N�̋����Y�Ɛ��Y�J���҂̔N�ԑ����J�����Ԃ�2,048���ԂƂȂ��Ă���A���̍�������ɑ傫�������Ă���A�N�ԑ����J������1,800���ԑ�ւ̑��}�ȉ��P���K�v�ƂȂ��Ă��܂��B
�N�ԑ����J�����Ԃ̑����X���́A����O�J�����Ԃ̑����A�N���L���x�ɂ̎擾���̒ቺ���傫�ȗv���ƂȂ��Ă��܂��B�����Ƃ̏���O�J�����Ԃ́A���Y�����ƘA�����ĕϓ����܂����A2002�N�ȍ~�̌i�C�ɂ����ẮA���Y�����̐L�шȏ�ɏ���O�J�����Ԃ̑������������ƂȂ��Ă��܂��i�}�\28�j�B�܂��A�N���L���x�ɂ̎擾���͔N�X�ቺ�X�������ǂ�A�S�Y�ƃx�[�X�ł́A2001�N�ȍ~�A50���������Ƃ�����ԂɂȂ��Ă��܂��B�i�}�\29�j
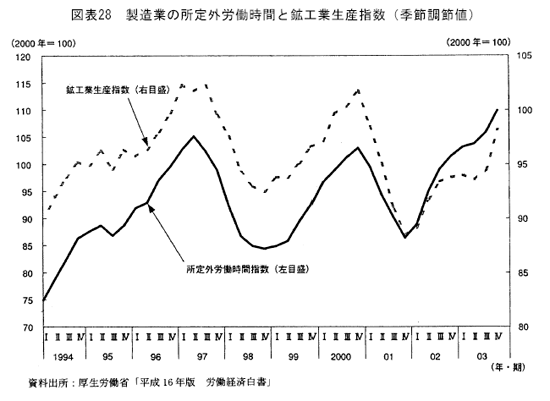
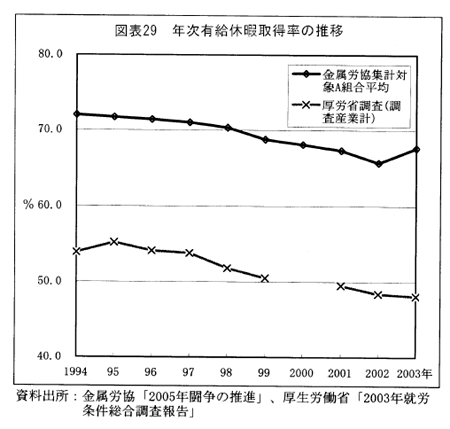
(3) �ߏd�J���ɂ�錒�N��Q�̖h�~�̊ϓ_����̘J�����ԒZ�k
�����Y�Ƃɂ����Ă��A��Ɗԋ����̌����ɂ���āA�]�T�̂Ȃ��v���z�u�ƂȂ��Ă��邱�Ƃ���A���ߘJ�����������A�N���L���x�ɂ̎擾�����ቺ�X���ƂȂ��Ă��܂��B36����̓��ʏ����̌������ɔ����A�v���z�u���܂߂��J�����ԒZ�k�̎��g�݂��������Ă����Ȃ���Ȃ�܂���B
�����J���Ȃ̒����ɂ��A�d���ɋ����s����X�g���X�������Ă���J���҂͂U������ȂǘJ���҂ւ̕��S�͊g�傷��X���ɂ���܂��B�]�E�S�������ǂ����Ƃ���2003�N�x�ɘJ�ДF�肳�ꂽ������310�����A���̂����ߘJ���̘J�ДF���157���ƂȂ��Ă��܂��B�܂��A���_��Q�ɂ��J�ДF���108���ł���A���̂���40�����ߘJ���̔F����Ă��܂��B
���������܂��A�����J���Ȃł́A2002�N�Q���ɂ́u�ߏd�J���ɂ�錒�N��Q�h�~�̂��߂̑�����v�̎��{�����肵�A36����̌��x���Ԃ̏�����͂��邽�߁A2004�N�S���P���ȍ~�ɒ�������鋦��ɂ����ẮA���ʏ����ɂ�����u���ʂ̎���v�����i������邱�ƂɂȂ�܂����B�܂�2004�N12���ɂ́A�u����̘J�����S�q����ɂ��āv�����c����A�J���҂̌��N�m�ۂ�ߏd�J���ɂ�錒�N��Q�h�~�����^���w���X��𐄐i���邽�߁A�J�����S�q���@����������邱�ƂɂȂ��Ă��܂��B<�y�[�W�̃g�b�v��>
(4) �s�����c�Ƃ̖o��
�o�J�ϕł́A�J�����Ԃ��߂���J���ēs���ɑ���ᔻ��W�J���Ă��܂����A�ēs������������Ă����w�i�ɂ́A�s�����c�Ƃ̖������w�i�ɂ���A�o�c�Ҏ���݂𐳂��A�@�ߏ����}�邱�Ƃ��挈�ł��B2001�N4���Ɂu�J�����Ԃ̓K���Ȕc���̂��߂Ɏg�p�҂��u���ׂ��[�u�Ɋւ����v��������Ă���A�J�g���c�ɂ���ĘJ�����ԊǗ���K���ɍs�����߂̃��[������i�߂邱�Ƃ����킹�ĕK�v�ƂȂ��Ă��܂��B
�A����2004�N�U���ɑg�����Q���l��ΏۂɎ��{�����u�����A���P�[�g�v�ɂ��A35.3�����s�����c�Ƃ����Ă���Ɠ����Ă��܂��B�s�����c�Ƃ̕��ώ��Ԃ͌�7.6���ԁA���ߘJ���ɐ�߂�s�����c�Ƃ̊����͕��ς�18.2���ƂȂ��Ă��܂��B
�܂��A�A�����������Ԋ�Ƃ̌ٗp�҂�Ώۂ�2004�N10���Ɏ��{�����u�ΘJ�҂̎d���ƕ�炵�ɂ��ẴA���P�[�g�v�̒������ʂɂ��A�s�����c�Ƃ�����Ƃ̉�36.8���ƂȂ��Ă��܂��B���ߘJ�����Ԃ̌�����@�Ƃ̊W�ł́A�u���炩���ߒ�߂�ꂽ����̎��Ԃɂ��v�i68.6���j�A�u���Ȑ\�����̓^�C���J�[�h�����Ƃɏ�i������������v�i56.0���j�Ȃǂ̊Ǘ����@�ŁA�����s�����c�Ƃ������Ȃ��Ă��܂��B
���������̂��Ƃł́A�J�����ԊǗ��̓O��ɂ���āA�����ɕs�����c�Ƃ�o�ł��Ȃ���Ȃ�܂���B<�y�[�W�̃g�b�v��>
(5) �z���C�g�J���[�E�G�O�[���v�V�����ƘJ�����ԊǗ�
���{�o�c�A�́A�o�J�ϕɂ����āA
�E���l�Ȑl�X���n���I�Ȑ��ʂ��߂����ē����E��ł́A��l�ЂƂ肪�����ɂƂ��ē����₷�����������������邱�Ƃ��]�܂����B��Ƃ̐l���Ǘ����͂��߁A�@���x��s���̂�����Ȃǂ��܂߂āA�������̎��R�x�����߂邽�߂̎��g�݂��K�v�s���ƂȂ�B�iP.5�j
�E�d���̐��ʂ��K�������J�����Ԃɔ�Ⴕ�Ȃ������������債�Ă��錻�݂ł́A�J�����Ԗ@���̔�
�{�I�������]�܂��B���Ȃ킿�A���s�̍ٗʘJ�����͋K���ɘa�̕����ő啝�Ɍ������ׂ��ł��邵�A�J�����ԊǗ��ɂȂ��܂Ȃ������I�ȓ������������Ă��邱�ƂɑΉ�����ׂ��A�z���C�g�J���[�ɂ��āA���̌���ꂽ�J���҈ȊO�ɂ��Ă͌����Ƃ��ĘJ�����ԋK���̓K�p���O�Ƃ��鐧�x�i�z���C�g�J���[�E�G�O�[���v�V�������j�����ׂ��ł���B�iP.49�j
�E�z���C�g�J���[���������Y�����������邽�߂ɂ́A���������V�������z�ɂ��ƂÂ��J�����ԊǗ��̊ɘa���ꂽ�g�g�݂�ϋɓI�ɓ������Ă����ׂ��ł���B�iP.49�j
�E�H��@�̎���̈����������J����@�Ȃǂ̊W�@�߂��A�����̊��ɂӂ��킵�����̂ɔ��{�I�ɉ��v�������̑������̂ƂȂ邱�Ƃ��������҂������B�iP.51�j
�ȂǂƎ咣���Ă��܂��B
�������Ȃ���A�J���@�ɂ��J�����Ԃ̋K���́A�����ԘJ����h�~���邱�Ƃɖ{���̎�|��
����A����ɂ���Đl�Ԃ炵���J�������Ɛ�����ۏႷ����̂ł��B���ߘJ���蓖�̎x�����ƁA�J�����ԊǗ��͕ʂ̖��ł���A�ΘJ�҂����N���ێ����A�ʏ�̌l�����A�ƒ됶���A�Љ���������邽�߂ɂ́A�J�����Ԃɂ͈��̘g���K�v�ł��B�܂��A��ƂƂ��ċΘJ�҂̃G���v���C���r���e�B�����߂�Ȃ�A���R�A�G���v���C���r���e�B��g�ɂ��邽�߂̎��Ԃ��A�ΘJ�҂ɒ��Ȃ���Ȃ�܂���B���ߘJ�����P��I�ɍs���A�J�����ԊǗ����s�O��ŁA�s�����c�Ƃ����݂������A�N�x�����S�擾�ł��Ȃ��悤�ȏ̂��Ƃł́A�z���C�g�J���[�E�G�O�[���v�V�����̓�����F�߂邱�Ƃ͂ł��܂���B
�}���ɍL������鍑�ۘJ���K�i�r�`8000�ł́A�T�̘J�����Ԃ�����O�J�����܂߂�60���Ԃɐ������Ă���A������ĘJ�������邱�Ƃ͂ł��܂���B�r�`8000�̘J�����ԋK���́A�J�����Ԗ@�����G�O�[���v�g�i���O�j�����l�B�ɂ��Ă��A�G�O�[���v�g����܂���B�ٗʘJ�����ł��낤���G�O�[���v�g�ł��낤���A���悻�]�ƈ��̘J�����Ԃ́A��������ƊǗ�����A�ʏ�̘J�����Ԃ���J���͈��̎��Ԃɐ��������ƂƂ��ɁA�N���L���x�ɂ�100���擾��������O�ƂȂ�Ȃ���Ȃ�܂���B<�y�[�W�̃g�b�v��>
(6) �C�O�ɂ�����J�����Ԃ̓���
�P.�h�C�c�A�t�����X�ɂ�����J�����ԉ����̓���
�h�C�c�A�t�����X�ɂ�����J�����ԉ����̓���������Ă��܂����A�����������X�̘J�����Ԃ͏T35���ԁA�N��1,500���ԑ�ł���A���{�Ƃ͑傫���قȂ��Ă��錻����݂�A���{�̘J�����Ԃ�ɘ_���邱�Ƃ͂ł��܂���B
�Ȃ��A�V�[�����X�Ђł́A�J���g�����T40���ԘJ����e�F�����⊮�����������܂������A����́A�T35���Ԑ��������Ƃ��Ē�߂��Y�ƕʘJ����������������ŁA���Ə������肵�A�ٗp�ێ��Ȃǂ̏�������������I�Ȃ��̂ƂȂ��Ă��܂��B
�܂��A�_�C�����[�N���C�X���[�Ђɂ����Ă��A��͍H��ŏT40���Ԑ�����������܂������A���ƕ���ł͘J�����ԉ����͓K�p����܂���B����ɁA����̎d���ɏ]������J���҂ƐE���̋��^�̌n��������{�J������i�d�q�`�j�����ɔ����A�����i���̐����ɂ������㏸����������邱�ƂɂȂ�܂��i2006�N��2.79���ɑ����j�B�������Ȃ���A2002�N�ɒ������ꂽ�J������ɐ��荞�܂ꂽ�A2002�N�U������4.0���A2003�N�U������3.1���̒��グ�͎��{����邱�Ƃɗ��ӂ��K�v�ł��B�����ɁA16���l�̏]�ƈ��ɑ��āA2012�N�܂ł̌ٗp�ۏႪ��茈�߂��Ă��܂��B�i�}�\30�j
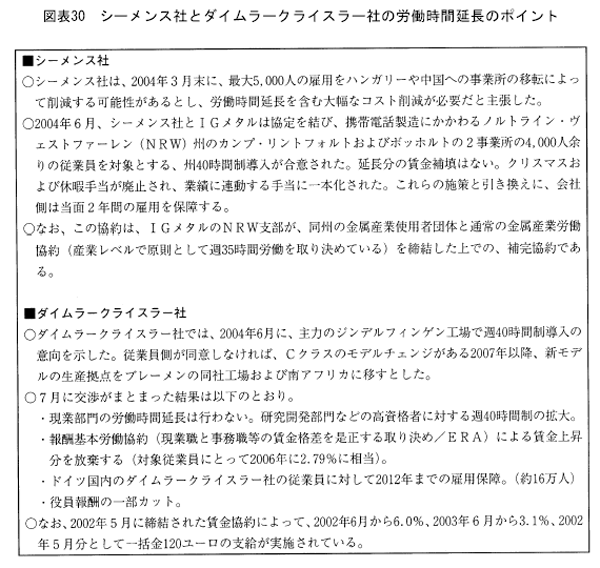
�Q.�A�����J�ɂ�����z���C�g�J���[�E�G�O�[���v�V�����̓���
�O�q�̂悤�ɓ��{�o�c�A�́A���L���z���C�g�J���[�J���҂�K�p���O�Ƃ���z���C�g�J���[�E�G�O�[���v�V�����̓������咣���Ă��܂��B���̖��ɂ��ẮA�A�����J�Ɠ��{�̘J�����Ԗ@���̑���A�J�����Ԃ̎��Ԃ̈Ⴂ�ɗ��ӂ���K�v������܂��B
�A�����J�ł́A�����J����@�i�e�k�r�`�j�ɂ���āA�T40���Ԃ���J���ɑ��āA������1.5�{�ȏ�̎��ԊO�������x�������Ƃ��`���Â��Ă��܂��B�z���C�g�J���[�E�G�O�[���v�V�����́A�Ǘ��I�J���ҁA�^�c�I�J���ҁA���I�J���ҁA�O�Z�[���X�J���ҁA�R���s���[�^�[�֘A�J���҂����v���������ꍇ�ɁA���̋K�肩��K�p���O�i�G�O�[���v�g�j���鐧�x�ł��B�E���̐�����A�������g�Ŏ��Ԃ��Ǘ����邱�ƂɂȂ�܂��B
���̐��x�́A2004�N�W���ɉ�������܂����B��ȉ����́A1.�Œ��܂��͕�V�����̈����グ�i�T155�h���ȏと�T455�h���ȏ�j�A2.�Q��ނ��������f�v���̈�{���A3.���z��V�v���̐V�݁A�Ȃǂł��B
���Ǘ��I�J���ҁiExecutive Employees�j�̏ꍇ�ɂ́A1.��v�ȐE�����A��Ђ܂��͂��̕��E�ۂ̊Ǘ��ł��邱�ƁA2.���I�ɂQ�l�ȏ�̘J���҂��w�����߂��邱�ƁA3.���̘J���҂��̗p�������͉��ق��錠����L���Ă��邩�A�̗p�E���فE���i�⑼�̘J���҂̐g���̕ύX�ɂ��āA���̎҂̐��E�����ɏd������Ă��邱�ƁB
���^�c�I�J���ҁiAdministrative Employees�j�̏ꍇ�ɂ́A1.��v�ȋƖ����A��Ђ܂��͌ڋq�̌o�c���j�⎖�Ɖ^�c�S�ʂɒ��ڂɊ֘A����I�t�B�X�Ɩ��܂��͔���̓I�Ɩ��̐��s�ł��邱�ƁA2.��v�ȋƖ��̂Ȃ��ɁA�d�v�Ȏ����Ɋւ��čٗʌ��ƓƗ����f���s�����Ƃ��܂܂�邱�ƁB
�Ȃǂ̗v�������Ȃ���Ȃ�܂���B
�܂��A�N��100,000�h���ȏ�ŁA�Ǘ��I�A�^�c�I�A���I�J���҂̂����ꂩ�̗v���̓��̂P�ȏ����I�ɍs���I�t�B�X�Ɩ��܂��͔���̘J���҂ł���A�K�p���O�̑ΏۂƂȂ�܂��B
����A�P�������̍T���͔F�߂��A���J��������J�����Ԃɂ�����炸�\�ߒ�߂�ꂽ�������x�������x�[�X�̎x�����������Ƃ��邱�Ƃ͈ێ�����܂����B
���{�����ɂ���āA�G�O�[���v�g�̑Ώێ҂��g�傷�邱�ƂƂȂ�܂������A�����ɂ���ăm���G�O�[���v�g����G�O�[���v�g�ƂȂ����҂̂����A���ۂɏ���O���������Ă����i����
�킿�c�Ƃ�x���o�����Ă����j�ٗp�҂͔䗦�Ƃ��Ă͑����Ȃ��ƌ����܂��B�����̏]�ƈ����P��I�ɏ���O�J�����s���Ă���킪���Ƃ́A���{�I�ɏ��Ⴄ���Ƃɗ��ӂ��Ȃ���Ȃ�܂���B<�y�[�W�̃g�b�v��>
| �W�D�d���Ɖƒ�̗����x���̂��߂̎�����琬�x�������i�@�A�玙�E���x�Ɩ@�ւ̑Ή� |
2002�N�X���Ɍ����J���Ȃ��Ƃ�܂Ƃ߂��u���q����v���X�����v�ł́A�u�q��ĂƎd���̗����x���v���S�̏]���̎��g�݂ɉ����A�u�j�����܂߂��������̌������v���̎��_���܂߂āA�����I�Ȏ��g�݂��i�߂��邱�ƂɂȂ�܂����B
����܂���2003�N�V���ɐ��������u������琬�x�������i�@�v�ł́A�e��Ƃɑ��āA�q��Ă͒j�������͂��čs���ׂ����̂Ƃ̎��_�ɗ����A�d���Ɖƒ�̗����x���̂��߂̐��x�����݂̂Ȃ炸�A���ߘJ���̍팸�ȂǓ������̌������Ɏ����鑽�l�ȘJ�������̐��������߂Ă��܂��B301�l�ȏ���ٗp���鎖�Ǝ�ɑ��ẮA2005�N�S���ȍ~�A�u�s���v��v�̒�o���`���Â��Ă���A300�l�ȉ��̊�Ƃɂ��Ă��A���l�̓w�͋`��������܂��B
�o�J�ϕɂ����ẮA
�E��Ƃɂ����Ă��A�q��Ďx���̎��g�݂́A�l�ނ̊m�ۂ�]�ƈ��̓������̌���A���l�ȓ������̎����Ȃǂ�ʂ��āA�]�ƈ��̈ӗ~�����Y���A�Ɛт̉��P�ɂȂ���\���������B�iP.23�j
�Əq�ׂĂ��܂��B
�u�s���v��v�̓��e�ɂ��ẮA�u�s���v�����w�j�v��������Ă�����̂́A���ꂼ���Ƃ̎���ɉ����č��肷�邱�ƂɂȂ��Ă��܂��B���q����Ƃ��Ď������̂��鐧�x�Ƃ��邽�߂ɂ́A�u�s���v��v�̗��āA���{�ɘJ���g�����Q�����A�ΘJ�҂̈ӌ���I�m�ɔ��f���A�d���Ɖƒ�̗������}���鐧�x���m������ƂƂ��ɁA�܂����x�����p���₷���E��Ƃ��Ă������Ƃ��d�v�ł��B�i�}�\31�j
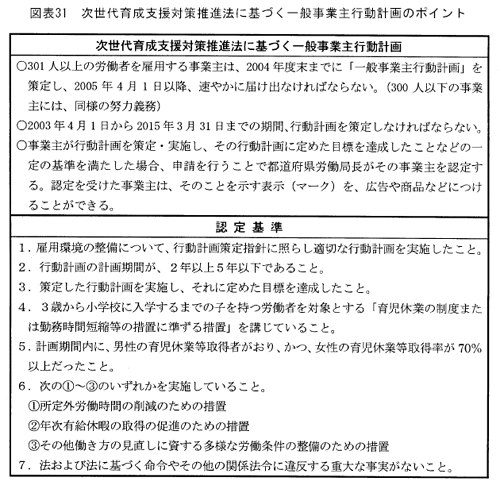
2004�N12���P���ɂ́u�����玙�E���x�Ɩ@�v���������A�玙�x�Ɗ��Ԃ̉�������x�Ƃ̎擾�����̊ɘa�A�q�̊Ō�x�ɐ��x�̑n�݂Ȃǂ����荞�܂�A2005�N�S���P������{�s����܂��B�d���Ɖƒ�̗�����}�邱�Ƃ̂ł���ϓ_����A�ΘJ�҂̃j�[�Y���Ƃ̎��Ԃ܂��A�@�����鐧�x������^�p�̉��P��}���Ă������Ƃ��߂����Ă����܂��B�i�}�\32�j
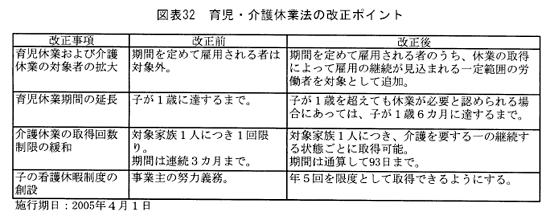
<�y�[�W�̃g�b�v��>
| �X�D����Ҍٗp����@�̉�����60�Έȍ~�̏A�J�m�� |
�����J���ł́A60�Έȍ~�̏A�J�m�ۂ̂R�����Ƃ��āA�@�������Ƃ���]������̂́A�N�ł����邱�ƁA�A�N�����z�x���J�n�N��Ɛڑ����邱�ƁA�B60�Έȍ~�A�J������̂ɂ��ẮA���������g�D����}�邱�ƁA���f���Ď��g�݂�i�߂Ă��܂����B���̌��ʌ��݁A�����J���P����3,600�g���̂����A1,758�g���ŎY�ʕ��j�ɉ��������x�������}���Ă��܂��B
2006�N�S������A65�܂ł̌p���ٗp���x�̓����i2013�N�܂łɒi�K�I�����グ�j�𒌂Ƃ����������Ҍٗp����@���{�s����܂��B���q�E����̐i�W�ɑΉ����āA����҂��Љ�̎x����Ƃ��Ċ���ł��鐧�x�̍\�z��A�N�����z�x���J�n�N������グ����Ȃ��ł̐����̈����Љ�ۏᐧ�x�̎x����̊m�ۂ����邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Ă��܂��B�J�g����ɂ���āA�p���ٗp���x�̑ΏۂƂȂ�J���҂Ɋւ�����߂邱�Ƃ��ł���Ƃ���Ă��܂����A�@�̎�|�܂��Ȃ���A60�Έȍ~�A�J�m�ۂ̂R�����Ɋ�Â������x�𑁊��ɓ������Ă������Ƃ��K�v�ł��B�\���ȘJ�g���c��}��A�d�����e��J�������ɂ��Ă��A�ΘJ�҂̊�]�d�����[�����̍������x�Ƃ��邱�Ƃ��d�v�ł��B�i�}�\33�j
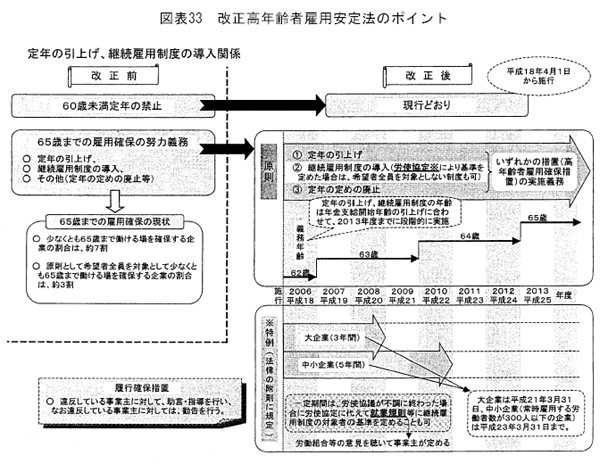
�N�����z�x���J�n�N��Ƃ̐ڑ��ɂ�鐶�v��̊m�ہA�Z�p�E�Z�\�̌p���E�琬�ɂ��Y�ƁE��Ɗ�Ղ̋����A�Ƃ��ɎЉ���x���A���������Ƃ�������Ґ�������������ϓ_����A�����ɑS�P�g�ł̓�����}���Ă����Ȃ���Ȃ�܂���B<�y�[�W�̃g�b�v��>
(1) ����͊ɂ₩�ȉ
�����ȁE�ƌv�����ɂ���āA�S���E�ΘJ�Ґ��т̉ƌv���x�̏N���ƂɌ��Ă݂�ƁA�O�N����̑����Ă����������A���������A����x�o�Ƃ��A2003�N�x�����i2003�N10���`2004�N�R���j�ɑO�N��v���X�ɓ]���܂����B
2003�N�x�����ɑ����āA2004�N�x����i2004�N�S�`�X���j���A����x�o�̐L�ї������������̐L�ї������������߁A���Ϗ�����͑O�N�ɔ�ׂĂ��ꂼ��0.5�|�C���g�A0.7�|�C���g�㏸���܂����B���Ϗ�������̂́A2002�N�x�������㏸�������Ă��܂����A�]���͉����������������Ă���Ȃ��ŁA����x�o�̌���������������Ȃ����Ƃɂ��㏸�������̂��A�����������������A����x�o������������đ������Ă��邱�Ƃ��A�傫�ȕω��Ƃ����܂��B
�Ƃ�킯�ϋv���ɑ���x�o�́A2003�N�x�������v���X�������Ă���A����x�o�ɐ�߂銄�����A2004�N�x����ɂ�4.7���ɒB���āA2000�N�x�����ȗ��̍������ƂȂ��Ă��܂��B
�������Ȃ���A���߂�2004�N10�`12����������ƁA�������A���������A����x�o�Ƃ��O�N����������Ă���A�傫�Ȍ��O�ޗ��ƂȂ��Ă��܂��B�������A�ϋv���x�o�ɂ��ẮA�v���X8.8���Ƒ啝�ȐL�тƂȂ��Ă���A�����ȏ���ӗ~�����ĂƂ邱�Ƃ��ł��܂��B�i�}�\34�j
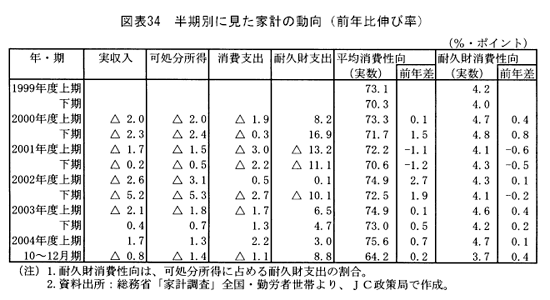
<�y�[�W�̃g�b�v��>
(2) ���������w�𒆐S�Ƃ����������̉��P
2004�N�ɂ�����S���E�ΘJ�Ґ��т̉ƌv���x�̎��т��A�N���K���ܕ��ʕʂɌ���ƁA���������A���������́A��T�ܕ��ʁi�N��445���~���x�܂Łj�A��U�ܕ��ʁi�N��445�`586���~���x�j�̐��тł́A�O�N�ɔ�����Ɏ~�܂��Ă���̂ɑ��A���������w�Ƃ������V�ܕ��ʁi�N��586�`738���~���x�j�A��W�ܕ��ʁi�N��738�`950���~���x�j�̐��тł́A�啝�ɑ������Ă���B
������x�o�́A���������̑������̍�����W�ܕ��ʂ̑��������ł��傫�����A�����������قƂ�lj����̑�T�ܕ��ʁA��U�ܕ��ʂł�����x�o�͐L�тĂ���A���̓_�ł������ȏ���ӗ~��������B������w�̏����������P����A����ɏ���̊g�傪���҂����Ƃ���ƂȂ��Ă���B�i�}�\35�j
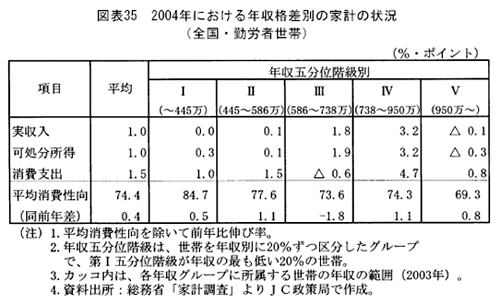
��ʓI�ɁA���Ϗ�����ɂ́A�����̍����w�قǁA�܂�������������قǒቺ����X��������܂����A����́A�������w�ɂ����Ă����Ϗ�������㏸���Ă���A�����������ۂ́A����܂ʼn䖝�����Ă�������A�������̉��P�ɂ��A��C�ɉ��������ꂽ�ɂ��邱�Ƃ������Ă���A�ƍl�����܂��B�i���k���ɂ���āA�L���ΘJ�ґS�̂̎����E�����̑�����}��A�ٗp�Ɛ����ɑ��鏫���s���@���āA���̍L������I�ȏ���g����������Ă����Ȃ���Ȃ�܂���B<�y�[�W�̃g�b�v��>
(3) ��Ƃ̒��~���߂͓��{�o�ς̘c�݂��g�傷��
�����o�ς̊ϓ_���猩��ƁA�킪���ł͍����A��Ƃ̒��~���߂Ƃ����ٗ�̏ƂȂ��Ă��܂��B�����ɂ킽��s���ɂ���āA��Ƃ��������T���A�������ۂɓw�߂��Ƃ�������Ȏ���͂���܂����A���ǂ́A�ƌv�����Ƃɏ����ړ]���s��ꂽ�Ƃ������Ƃł���A���������́A�����Ԏ��̑���ƗA�o�ˑ��Ƃ����o�ς̘c�݂������炵�Ă��܂��B
�ʏ�̏ꍇ�A�ƌv�͒��~���߁i�����������~�������j�A��Ƃ͓������߁i���~���������������j�ɂȂ�̂����ʂł��B�Ƃ��낪�ߔN�A��Ƃ����~���߂ƂȂ��Ă��܂��܂����B98�N�x�ɂf�c�o�̓��v�J�n�ȗ����߂āA����Z�@�l��Ƃ����~���߂Ɋׂ�A1999�A2000�N�x�͂��낤���ē������߂ɖ߂������̂́A2001�N�x�ɂ͍Ăђ��~���߂ɓ]���A2002�N�x�ɂ͉ƌv�̒��~���߁i11.2���~�j������A17.4���~�Ƃ������~���߂��L�^���Ă��܂��B�i�}�\36�j
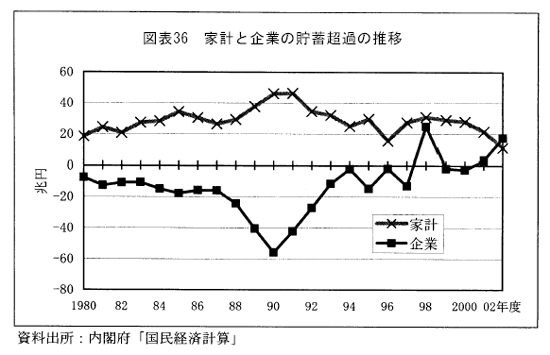
�}�\37�i�o�ς̃t���[�z�j�́A��ʓI�ȃ}�N���o�ϊw�̋��ȏ��ɍڂ��Ă���o�ς̃t���[�z�̐}�ł��B��Ƃ͒�����z���̂������ŁA�ƌv�ɏ������x�����܂��B�ƌv�͏���������⒙�~�ɂ܂킵�܂��B�ƌv�̒��~�����{�s���ʂ��Ċ�Ƃɂ킽��A��Ƃ͂��̎����œ������ăr�W�l�X���s���A�Y�ݏo�����t�����l���A�Ăђ�����z���̂������ʼnƌv�ɏ����Ƃ��Ďx�����܂��B
�����������ꂪ�ʏ�̃t���[�z�ł���킯�ł����A��Ƃ����~���߂ɂȂ��Ă��܂��Ă���
�Ƃ������Ƃ́A���̎����̗��ꂪ���܂��@�\���Ă��Ȃ��A�Ƃ������Ƃ��Ӗ����܂��B
�����o�σx�[�X�ł́A
| �ƌv�̒��~���߁|��Ƃ̓������߁������Ԏ��{�f�Ս��� |
�Ƃ����������藧���ƂɂȂ��Ă��܂��B
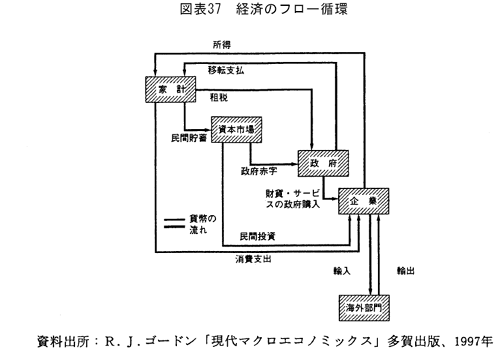
����ł́A���ӂ̉ƌv���~���߂������Ă�����̂́A��Ƃւ̏����ړ]�ɂ����̂ł���A��Ƃ̓������߂̃}�C�i�X�i�����~���߁j�����債�Ă��邽�߂ɍ��ӂ��g�債�A�]���āA�E�ӂ̍����Ԏ��E�f�Ս������g�傷��Ƃ����c�݂������Ă��܂��B
��Ƃɂ�铊���͉��Ă��܂����A����ƂƂ��Ɋ�Ƃ���ƌv�ɑ��鏊���ړ]�𑣐i���A�����ď�����g�傷�邱�Ƃɂ��A�����Ԏ��̏k���Ɠ����哱�^�o�ς��������Ă����Ȃ���Ȃ�܂���B<�y�[�W�̃g�b�v��>
| 11�D�b�r�q�i��Ƃ̎Љ�I�ӔC�j�ƒ����E�J���������� |
(1) ��Ƃɂ�����b�r�q���i�ƘJ���g��
�����J����2004�N�R���A�u�b�r�q�i��Ƃ̎Љ�I�ӔC�j���i�ɂ�����J���g���̖����Ɋւ���v�����肵�A��Ƃłb�r�q�����H����u��́v�ł������łȂ��A��Ƃ̍ł��d�v�ȃX�e�[�N�z���_�[�̂ЂƂł���]�ƈ��̑�\����J���g�����A�b�r�q�̐��i�ɐϋɓI�ɎQ�悵�Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ��咣���Ă��܂��B
���{�o�c�A�́A�o�J�ϕ̂Ȃ��ŁA
�E�b�r�q�́A�P�Ȃ�Љ�v���̂��߂̊�t��C�x���g�Ȃǂ̃X�|���T�[�ɂȂ邱�Ƃł͂Ȃ��A��Ƃ̗��Q�W�҂ɑ���w�̔z�������Ȃ���o�c���s�Ȃ����Ƃł���B�iP.57�j
�Ƃ��Ă��܂��B�t�����Ɍ������o�c���̕��j�������o�J�ϕ̂Ȃ��ŁA�b�r�q�Ɋւ��ĐG��Ă��邱�Ǝ��̂́A�����]���ł��܂��B�R���v���C�A���X�i�@�ߏ���j�A�r�W�l�X�E�G�V�b�N�X�i��Ɨϗ��j����łȂ��A���ꂩ��̒����E�J�������̂���l�ɂ����Ă��A�b�r�q�̊ϓ_���s��������ł��B
�b�r�q�i��Ƃ̎Љ�I�ӔC�j�́u�Љ�v�Ƃ́A�u�ȁv�ɑ���T�O�ł��B�b�r�q�Ƃ́A��Ƃ����ȁi���Ёj�̗��v�݂̂�Nj�����̂ł͂Ȃ��A��ƂɊW����Љ�S�̗̂��v��Nj����Ă������Ƃ��A���ǂ͎��Ђ̗��v�i�����A��Ƃ̉i���I���W�������炷�Ƃ������Ƃɂق��Ȃ�܂���B
���̒�`������ɋ�̉�����A
�P.���ЁA���邢�͊���Ƃ��A�o�c�҂Ƃ��A�������̃X�e�[�N�z���_�[�i���Q�W�ҁj�̗��v���m�ۂ��邱�Ƃ���ړI�Ƃ��āA��Ɗ������s���̂ł͂Ȃ��A����ҁA�]�ƈ��A�n��A����ȂǁA���ׂẴX�e�[�N�z���_�[�̗��v��}��iWin-Win�̊W�����j�悤�A�w�߂邱�ƁB
�Q.��L���������邽�߂̎Г��̐��i�}�l�W�����g�E�V�X�e���j�����A�X�e�[�N�z���_�[������������߂�ꂽ�ꍇ�ɁA���₩�ɓ�������悤�ɂ��Ă����i�A�J�E���^�r���e�B�j���ƁB
�R.���������H���邱�Ƃɂ��A��Ƃ̃T�X�e�i�r���e�B�i�����\���j���m�ۂ��邱�ƁB���Ȃ킿�A�b�r�q�̎��H�Ȃ����āA��Ƃ̉i���I�ȑ����Ɣ��W�͂��肦�Ȃ��Ƃ������ƁB
�ł���Ƃ����܂��B
��Ƃ̂b�r�q�̎��g�݂ɂ����āA�]�ƈ��͂b�r�q�����H����u��́v�ł������łȂ��A�b�r�q�ɂ���ė��v��ׂ��q�́i�X�e�[�N�z���_�[�j�ł�����܂��B�J���g���́A��Ƃɂ���������Ƃ��d�v�ȃX�e�[�N�z���_�[�̂ЂƂł���]�ƈ��̑�\�Ƃ��āA��Ƃɂ�����b�r�q���i�ɐϋɓI�ɎQ�悵�Ă����Ȃ���Ȃ�܂���B
��̓I�ɂ́A�����J�����ł��o�����u�b�r�q���i�ɂ�����J���g���̖����Ɋւ���v�ɑ���A���Ƃ��Έȉ��̂悤�Ȗ������ʂ����Ă����Ȃ���Ȃ�܂���B
��P�̃X�e�b�v�F��Ƃɂ�����b�r�q�̎��g�݂ɂ��āA�J�g���c��ɂ����ĕK�����グ��B�J���g���Ƃ��ēƎ��Ƀ`�F�b�N������i�߁A�K�v�ȏꍇ�ɂ͘J�g���c��ȂǂŖ���N���s���B
��Q�̃X�e�b�v�F�b�r�q�Ɋւ���Г��̐��Â����A�Г��̐��̌������ɘJ���g�����Q�悷��ƂƂ��ɁA�b�r�q�ψ���A�R���v���C�A���X�ψ���ȂǁA�Г����f�I�Ȉψ���ɘJ���g���̑�\���Q������B
��R�̃X�e�b�v�F�b�r�q����A�A���P�[�g��Г��]���̎��{�Ɋ֗^����ƂƂ��ɁA�b�r�q���̍쐬�ɂ��Q�����Ă����B�C�O�ł̘J�����Ɋւ��郂�j�^�����O�ɂ��āA�J�g�A�g��}��B<�y�[�W�̃g�b�v��>
(2) �R���v���C�A���X�̎�v�Ȓ�
�����J���́A2004�N�R���ɂƂ�܂Ƃ߂��u�b�r�q���i�ɂ�����J���g���̖����Ɋւ���v�̂Ȃ��ŁA1.�R���v���C�A���X�o�c�A2.�r�W�l�X�E�G�V�b�N�X�A3.�]�ƈ��d���̌o�c�A4.���o�c�A5.�Љ�v�����R���v���C�A���X�̂T�̒��Ƃ��Čf���܂����B�Ƃ�킯�O�R�҂́A�ΘJ�҂ɂƂ��āA�Ƃ��Ɋւ��̐[�����̂ł��B
1.�R���v���C�A���X�o�c
�킪���ɂ����ẮA�R���v���C�A���X�i�@�ߏ���j�Ƃ́A�P�Ɂu�@�߂̕����������悢�v�Ɖ��߂��ꂪ���ł����A�{���̈Ӗ��ɂ�����R���v���C�A���X�Ƃ́A�u�@�߂̕����݂̂Ȃ炸�A���̔w��ɂ��鐸�_�܂Ŏ��A���H���邱�Ɓv�i���ށE���V��w�����j�ł��B
���R�̂��ƂȂ���A��Ƃ̂����銈���Ɋւ��āA���ׂĂ�@���Ō����ɋK�肵�Ă������Ƃ͕s�\�Ȃ킯�ŁA�@�߂ŐG��Ă��Ȃ������A��Ƃ�l�̔��f�Ɉς˂��Ă��镔���ɂ��ẮA��Ƃ��C���e�O���e�B�[�i�������j�������āA���[�K���}�C���h�i�@�I�Ȃ��̂̍l�����j�ɑ���A�֘A�̖@�߂����߂��A�@�̎�|�ɉ����������ōs�����Ă����A�Ƃ����p�����K�v�ɂȂ�܂��B�]���āA�@���ŋ�̓I�ɋ֎~����Ă��Ȃ����炢�����낤�Ƃ��A�@�߂�s���悭���߂��A����Ȃ狖�����͂����A�Ƃ����悤�Ȕ��f�ōs�����邱�Ƃ͋�����܂���B�@���ɂ͗P�\�[�u����Ⴊ�t����Ă���ꍇ�����Ȃ�����܂��A���������P�\�[�u�����𗘗p����̂ł͂Ȃ��A�@�̎�|�ɑ������Ή���ϋɓI�ɐi�߂Ă������Ƃ��b�r�q�ɂ��Ȃ����s���Ƃ����܂��B
2.�r�W�l�X�E�G�V�b�N�X
�R���v���C�A���X�͈̔͂�����߂čL�����Ƃ��炷��A�r�W�l�X�E�G�V�b�N�X�i��Ɨϗ��j�ƃR���v���C�A���X�Ƃ̋��E���͂�₠���܂��ɂȂ邱�Ƃ͔ے�ł��܂���B�������A�R���v���C�A���X���@�𗧋r�_�Ƃ��A�@�̐��_���������悤�Ƃ���̂ɑ��A�r�W�l�X�E�G�V�b�N�X�́A�ϗ��I�ɂǂꂾ���u���݁v��Nj��ł��邩�A�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
3.�]�ƈ��d���̌o�c
��Ƃ��O���[�o����������Ȏs��o�ς����������Ă�������́A�ŏI�I�ɂ́A�]�ƈ��̈ӗ~�Ɣ\�͔����ȊO�ɂ͂Ȃ��A�Ƃ������Ƃ��A���{�ł��A�����ăA�����J�ł��A�ĔF�������悤�ɂȂ��Ă��Ă��܂��B���{���\����G�N�Z�����g�E�J���p�j�[�̌o�c�҂��Nj������ƃ��f���́A�]�ƈ��̎匠���d�����A�����ٗp��ڕW�Ɍf����X���������A�A�����J�ł������ٗp�̗L�������ĔF���������A�Ǝw�E����Ă��܂��B
����҂̑啔���́A�ǂ����̊�Ƃ̏]�ƈ��ł���킯�ł�����A���ɂ����Ƃ��]�ƈ����y�������s�����Ƃ�A���̏�L�܂�A���R�̂��ƂȂ���A����������Ƃɑ������҂̎x���͗���Ă������Ƃ��o�債�Ȃ���Ȃ�܂���B<�y�[�W�̃g�b�v��>
(3) ���{�o�c�A�̂b�r�q�ɑ���Ή�
�o�J�ϕł́A�]�ƈ��Ɋւ��b�r�q�Ɋւ��āA
�E�Ƃ�킯�l�ނɂ��ẮA�]�ƈ��̑��l���A�l�i�A���d����ƂƂ��ɁA���S�œ����₷�������m�ۂ��邱�Ƃ����߂���B�iP.58�j
�Ǝ咣���Ă��܂��B�m���ɂ����ɏ����ꂽ���e�́A�b�r�q�̈ꕔ�ɂ͈Ⴂ����܂��A���ꂪ���ׂĂł͂���܂���B�ΘJ�҂Ɋւ��b�r�q�ł����Ƃ��d�v�Ȃ��Ƃ́A
1.�J����@���͂��߂Ƃ���J���@�K�����炷�邱�ƁB
2.�C�O�̎��Ƌ��_�ɂ����āA���Y���̍����@�̔@���Ɋւ�炸�A��{�I�l���A���j�I�J��������炵�Ă������ƁB
3.�]�ƈ��ɑ��ēK���Ȑ��ʔz����}�邱�ƁB�Œ���̘J���@�K�����炷�邾���ɂƂǂ܂炸�A�˂ɒ����E�J�������A�E����̌�����߂����Ă������ƁB
�ł���Ƃ����܂��B
�������Ȃ���A���{�o�c�A��2004�N�T�`�U���ɔ��\�����u��ƍs�����́v�u��ƍs�����͎��s�̎�����i��S�Łj�v�ł́A
�����j�I�J����̂Ȃ��ł����Ƃ��d�v�Ȓc�����̕ۏE���Ђ̎��R�ɂ��ĐG��Ă��Ȃ��B
���Ɛ�֎~�@�̓O��ɂ��Ă͐G��Ă���̂ɁA�u�J����@�̓O��v�Ƃ����\�L�͂Ȃ��B
�Ȃǂ̖��_������܂��B�o�J�ϕ̂Ȃ��ł��A
�E�@�߂����炷�邱�Ƃ͎g�p�҂̓��R�̐Ӗ��ł��邱�Ƃ͂����܂ł��Ȃ��B�iP.49�j
�Ƃ����A�J�����ԂɊւ���J���s���ɑ��āA
�E�J���֘A�@���̋K���ɘa�̓����Ƃ͔��ɁA�ŋ߂̘J���s���́A��Ƃ̘J�g�������Ƃ̍��ۋ����͂̋�����j�Q�����˂Ȃ��悤�ȓ����������ł���B�iP.51�j
�E�J�����Ԃ��߂���J���ēs���ɂ��ẮA�������N�A����܂ŘJ�g�ɂ���茈�߂����ƂɊ�Ƃ��ƂɂȂ����Ȃ��Ή����Ȃ���Ă��������ɂ��Ă܂ŁA�˔@�Ƃ��Ďw�j��ʒB�������ɁA�J�g�ł̎��g�o�܂�E�ꊵ�s�Ȃǂ�Ύނ��邱�ƂȂ��A��Ƃɑ���w���ē���������Ƃ������Ⴊ�����w�E����Ă���B�iP.51�j
�E�e��Ƃɂ�����J���҂̏A�J�`�Ԃ�E�����e�Ȃǂ̎��Ԃɑ������@���̉��߁A�K�p���Ȃ����ׂ��ł��邵�A�w���ɂ��Ă��������s���邱�Ƃ������v�]�������B�iP.51�j
�ȂǂƎ咣���Ă��܂����A�R���v���C�A���X����͂͂Ȃ͂������咣�ł���A�Ɣ��f����������܂���B
�ŋ߂ɂ�����J���ēs���̋����́A����܂ł̎��Ԃ����܂�ɂ��@�̂߂������̂Ƃ�������Ă������߂ɁA��������A�{������ׂ��p�ɖ߂����Ƃ�����̂ł��B2004�N12���ɂ܂Ƃ߂�ꂽ�����J���ȘJ�������R�c��̌��c�u����̘J�����ԑ�ɂ��āv�ɂ����Ă��A�u�ߏd�J���ɂ��]�E�S�������̘J�ДF�茏�����N��310���ȏ���L�^���A���_��Q���̘J�ДF�茏������������ȂǁA�������Ƃ��߂��錒�N��Q���Љ��艻���Ă���v�Ǝw�E���Ă��܂��B�u����܂łȂ����Ȃ��Ή����Ȃ���Ă����v�Ƃ��A�u�E�ꊵ�s��Ύށv�Ƃ��A�u���Ԃɑ������@���̉��߁A�K�p�v�ȂǂƂ������t�́A��ƕs�ˎ��̉����Ƃ����Ă�����̂ŁA�܂��ɃR���v���C�A���X�Ƃ͑ɂɂ���l�����ł��B�R���v���C�A���X�ł́A�u����܂ŋ�����Ă������ǂ����v�͊W����܂��A�u���ԁv���@�Ƒ��e��Ȃ���A���Ԃ̂ق������������K�v������܂��B�������A�u�@�����������v�u�@�̓K���ȉ��߂��v�Ǝ咣���邱�Ƃ͎��R�ł����A�J���@�K�Ȃ�A�ΘJ�Ґ����̌����J�����̉��P���߂��������ŁA�@������@���߂��s���Ȃ���Ȃ�܂���B<�y�[�W�̃g�b�v��>
(4) �X�e�[�N�z���_�[�ɑ���z�����K�����ǂ������b�r�q�̎�v�ȃe�[�}
��Ƃ���������グ���A�X�e�[�N�z���_�[�ɑ��ēK���ɔz������Ă��邩�Ƃ������Ƃ́A�b�r�q�̎�v�ȃe�[�}�ł��B
�܂����ɁA�K���ȉ��i�ŏ���҂ɒ���Ă��邩�ǂ����A���ɂ̓T�v���C���[�ɑ��ēK���Ȏ�����s���Ă��邩�ǂ����A�����Ă��̌��ʂƂ��Ďc�����t�����l���A�]�ƈ��A�����A����ɑ��ēK���ɐ��ʔz�����s���Ă��邩�ǂ����A���{�E�n�������̂ɓK���ɔ[�ł���Ă��邩�A���`�F�b�N�|�C���g�ƂȂ�܂��B
�������u�K���ȉ��i�v�u�K���Ȏ���v�u�K���Ȑ��ʔz���v�u�K���Ȕ[�Łv�ɋ�̓I�Ȋ�͂���܂���B�@���ᔽ�����Ă���Ζ��O�ł����A�@�߂��N���A���Ă���ꍇ�̔��f��́A���ǁA�]�ƈ��̃������E�����[���E���`�x�[�V�����Ȃ����ƂɂȂ�Ȃ����ǂ����A���ꂪ���J���ꂽ�Ƃ��ɁA���Ԃ̎w�e���邱�ƂɂȂ�Ȃ����ǂ����A�ɐs����Ƃ����܂��B
�b�r�q�̐�i��Ƃɂ����ẮA��v��������ȂǂƓ��l�A�u�b�r�q���v���쐬�����悤�ɂȂ��Ă��Ă��܂��B���������Ȃ��ł��A����グ�A�T�v���C���[�Ƃ̎���z�A�]�ƈ��E�����E����ɑ���z���z�A�[�Ŋz�Ȃǂ����l�������Ė��炩�ɂ����悤�ɂȂ��Ă��Ă��܂��B�i�}�\38�j
���������b�r�q��v�A�t�����l��v�̍l�����́A�P�ɑ��v�v�Z����g�ݑւ��������ł͂���܂���B���v�v�Z���ɂ����ẮA�l����̓R�X�g�Ƃ��ĂƂ炦���Ă���̂ɑ��A�b�r�q��v�A�t�����l��v�ł́A�l������͂��߂Ƃ���X�e�[�N�z���_�[�ւ̔z�����A�܂��Ɋ�Ɗ����̖ړI�Ƃ��ĂƂ炦���Ă���̂ł��B
�b�r�q���ł́A�b�r�q��v�����łȂ��A�J���ЊQ�����A����O�J�����Ԑ��A�Ј��̔䗦�Ȃǂ���������Ă��Ă��܂��B�����E�J�������A�����ĘJ���E�ٗp���̑S�ʂɂ��ď����J���ł���悤�ɁA�����Ă��̎��Ԃ����Ԃ̎w�e������̂łȂ��悤�ɁA��ɘJ�g�Ń`�F�b�N���Ă����Ȃ���Ȃ�܂���B<�y�[�W�̃g�b�v��>
(1) �f�c�o�̓���
�킪���̖��ڂf�c�o�������́A2003�N�V�`�X�����ȍ~�A�O�N��Ń}�C�i�X������E���A2004�N�S�`�U����1.2���A�V�`�X�����ɂ�1.3���ƁA�ᐅ���ł͂�����̂́A�ꌘ�����ڂ��Ă��܂��B
���v���ڂ��Ƃł́A�l���2004�N�S�`�U�����A�V�`�X�����Ƃ�1.4���A�Z����͂S�`�U����3.1���A�V�`�X����1.9���ƂȂ��Ă��܂����A����ݔ������́A2003�N10�`12�����ȍ~�A�U�`�V�����x�̑啝�Ȑ����������Ă��܂��B�A�o�́A2004�N�P�`�R�����ȍ~�A�Q���̐������ƂȂ��Ă��܂����A���R�����f���A�A����2004�N�S�`�U�����ȍ~�͂Q���̐������ƂȂ��Ă��܂��B
�Ȃ������f�c�o�������́A2004�N�P�`�R������4.3�����L�^�A�S�`�U����3.0���A�V�`�X����2.6���Ƃ��݉��X���ɂ�����̂́A�����ɐ��ڂ��Ă��܂��B�i�}�\39�j
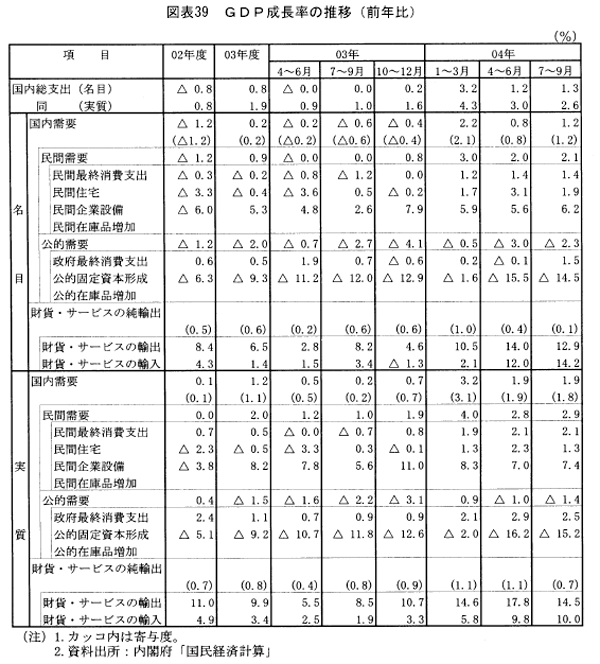
<�y�[�W�̃g�b�v��>
(2) �i�C�w�W�̓���
��ʓI�ɂ́A�z�H�Ɛ��Y�w���̂����́u�o�w���v�̃}�C�i�X�����A�u�Ɏw���v�̃}�C�i�X�������������Ȃ��������i�C�ɓ]�����V�O�i���ł���A�t�Ɂu�o�w���v�̃v���X�����u�Ɏw���v�̃v���X�������������Ȃ��������i�C��ނ̃V�O�i���ł���Ƃ݂Ȃ���Ă��܂��B
2002�N�P�`�R�����ɂ́A�o�w�����O�N�䁢8.4���A�Ɏw������4.2���ƂȂ��Ă��܂������A���S�`�U�����ɂ́A�o�w������1.9���A�Ɏw������10.0���ƃ}�C�i�X�����t�]���A�i�C�ɓ]�������Ƃ������܂����B2002�N�V�`�X�����ȍ~�A�o�w���̓v���X�𑱂������A�Ɏw���̓}�C�i�X�������Ă��܂��B
���߂�2004�N10�`12�����ɂ́A�o�w����1.9���A�Ɏw������0.3���Ƃ��̍������Ȃ�k�����Ă��܂��i�}�\40�j�B
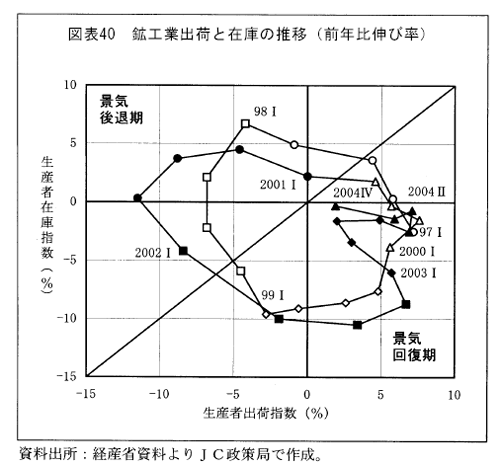
�������Ȃ���P���Ō���ƁA10���ɏo�ׂ��}�C�i�X�A�ɂ������Ɓu�s�����v�̏�ԂɊׂ��Ă����̂��A���̌�͂���������Ƃ���ƂȂ��Ă��܂��B
�̔����v�Ō���ƁA�����Ƃ̔̔��z�́A2004�N�ɓ����Ĉȗ��A�قڑO�N���݂̐����Ő��ڂ��Ă��܂��B�Ɠd�̔��Ȃǂ��͂��߂Ƃ���@�B�����Ƃ́A�����ԑO�N���ꂪ�����Ă��܂������A2004�N�V���A12���ɂ͑O�N��v���X�ƂȂ�A������{�[�i�X���̏���̊���������������ɂȂ��Ă��܂��B
�ݔ������̐�s�w�W�ł���@�B���v�i�D���E�d�͂����������j�́A2004�N�S�`�U������11.9���ƂQ���̐L�ї��ƂȂ��Ă��܂������A�V�`�X�����ɂ�3.8���A10�`11���ɂ�2.3���Ƒ啝�ɓ݉����Ă���A��⌜�O�����Ƃ���ƂȂ��Ă��܂��B
���t�{�E�i�C�E�I�b�`���[�����́u�i�C�̌��f�i�������j�c�h�v�́A2004�N�Q���ȍ~�A50���Ă��܂������A�X���ɂ�47.3�ƂW�J���Ԃ��40��ɒቺ���A12���ɂ�44.2�Ƃ���ɒቺ���Ă��܂��B50�������Ƃ������Ƃ́A�ǂ��Ȃ��Ă���Ƃ������f���A�����Ȃ��Ă���Ɣ��f����X���������Ȃ��Ă��邱�Ƃ������Ă��܂��B�i�}�\41�j
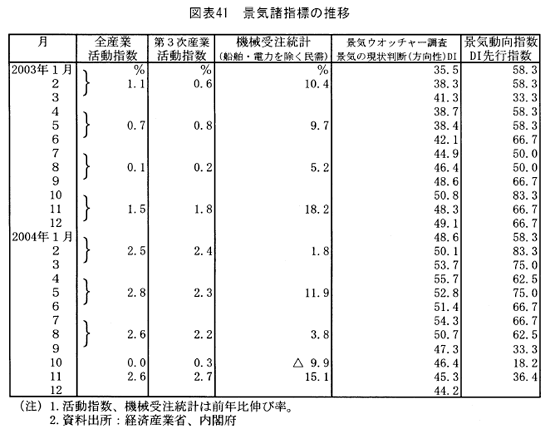
�f�Փ���������ƁA�A�o�z��2004�N��N��12.2���ƂQ�������L�^���܂����B���̂��ߖf�Ս������A17.9���ƂQ���߂������������Ă��܂��B���߂�2004�N10�`12�����ɂ́A�f�Ս������O�N�ɔ��9.0���������܂������A����͗A���z�����i�����ɂ����17.0���̑啝�����ƂȂ������߂ŁA�A�o��11.2���ƈ��������Q�����ƂȂ��Ă��܂��B<�y�[�W�̃g�b�v��>
(3) �����̓���
����ҕ����㏸���i�����j�́A2004�N10������12���܂őO�N��v���X�ƂȂ�A�Ƃ�킯11���ɂ�0.8���ɒB���܂����B����͓V��s���ɂ�鐶�N�H�i�̒l�オ��ɂ����̂ŁA�u���N�H�i�����������v�ł́A���̊Ԃ��O�N��}�C�i�X�������Ă��܂��B2004�N�P���ɓ���ƁA���N�H�i�̒l�オ��̓݉��ɂ��A�u�����v�̏㏸������0.3���i����̐��v�l�j�ƍĂу}�C�i�X�ɓ]���Ă��܂��B�i�}�\42�j
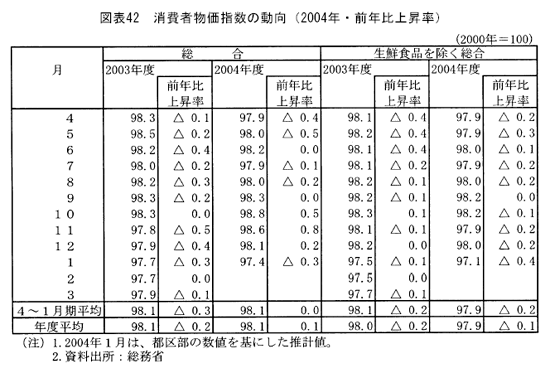
�A�������́A�Ζ��E�ΒY�E�V�R�K�X�A�����E�����i�A���w���i�𒆐S�ɁA2004�N�T���ȍ~�A
�啝�ȏ㏸�������Ă���A���̂��ߍ�����ƕ������Q�����x�̏㏸���Ő��ڂ��Ă��܂��B�i�}�\43�j
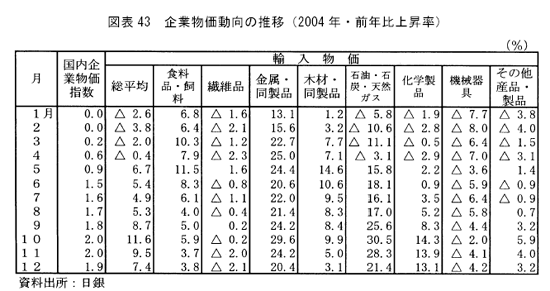
�A�������A������ƕ����̍������A����ҕ����ɔg�y���Ă��Ȃ��ƂȂ��Ă��܂����A����́A���{��s�����R����N�H�i�̉��i�����ɑΉ����A�}�l�[�T�v���C�̑��������S����ɍi�荞��ł��邱�Ƃ��w�i�ɂ���܂��B�t�e�i�����̎��Z�ɂ��A�R���̖��ڐ�����B�����邽�߂ɂ́A16�����x�̃}�l�^���[�x�[�X���K�v�Ƃ������ƂɂȂ�܂����A�����ɂ͂S����̑������ł���A����͖��炩�ɉߏ��Ȑ����Ƃ����܂��B�������������I�ȋ��Z�������߂́A����ҕ����̗}�����݂̖������ʂ����ƂƂ��ɁA�o�ς̌������̌����̂ЂƂɂ��Ȃ��Ă�����̂ƍl�����܂��B<�y�[�W�̃g�b�v��>
(4) �ٗp�
2004 �N�P���ɂ�5.48���ɂ܂ň����������S���Ɨ��́A2004 �N12 ���ɂ�4.43���ւ�1.05
�|�C���g�̉��P�ƂȂ�܂������A�ˑR�Ƃ��č������ɂȂ��Ă��܂��B�܂��A���Ɗ��Ԃ��P�N�ȏ�̎��Ǝ҂��R����������P����Ă��܂���B�i�}�\44�j
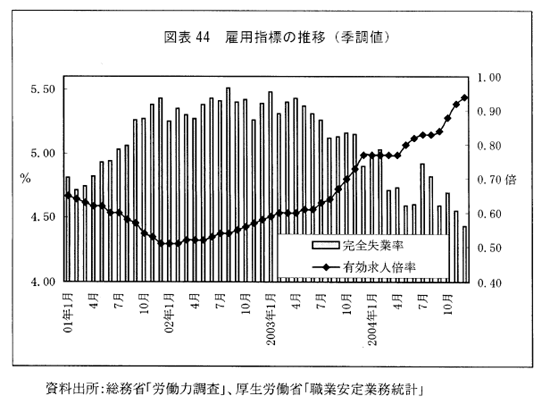
���S���Ɨ��̉��P�́A���Ј��ȊO�̌ٗp�̑����ɂ����̂ƂȂ��Ă��܂��B�J���͒����ŁA�ٗp�`�ԕʂ̘J���҂̑������݂�ƁA2004
�N�̌ٗp�Ґ���0.3���̑����ƂȂ��Ă��܂����A�j�q�̏�ق�98 �N�ȍ~�}�C�i�X�������Ă���A2004
�N�ɂ����Ă���0.4���ƌ������Ă��܂��B�܂��A2004 �N7�`9 ���̘J���͒����E�ڍW�v�ɂ����Ă��A�K�̐E���E�]�ƈ���55
���l���ƂȂ��Ă������ŁA���K�̐E���E�]�ƈ��͑O�N�����䁢76 ���l�ƌ����X���������Ă��܂��B�i�}
�\45�j
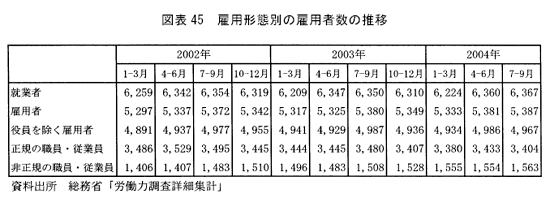
<�y�[�W�̃g�b�v��> |