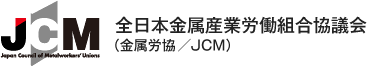誰もが平等に――女性の力がインダストリオールの世界的な運動の中心
2025-11-03

第4回インダストリオール大会の前日、「誰もが平等に」の旗印を掲げて、すべての地域・部門から350人を超える女性が女性大会に集まり、エネルギーと彩り、強い信念で会議室を満たした。
この1日は女性間の連帯・団結の精神を発散し、闘いの物語が強さの物語になり、メンターシップとリーダーシップ、ビジョンが融合して集団的な力の共同宣言になった。
平等の基調を打ち出す
女性大会の冒頭に、クリスティーナ・オリビエ・インダストリオール書記次長が歓迎の挨拶に立ち、過去と現在の年長者たちに敬意を払い、この行事は6年ぶりの対面女性大会だと述べた。
「みんなよくやった」と彼女は、この再会の時を何年も待っていた聴衆に語りかけた。
アトレ・ホイエ・インダストリオール書記長が、ジェンダー平等の推進に精力的に取り組んできた女性委員会とその指導者を祝福した。書記長は、女性が今や世界大会代議員の43%を占めていることを称賛した、この比率は2016年リオ大会の28%から上昇し、明らかな進歩の兆候を示しているが、引き続き取り組んでいく必要もある。
「女性が対等な立場で組合に加わらなければ公正な未来はない」と書記長は出席者に念を押した。
「『誰もが平等に』というテーマは単なるスローガンではなく、協力して私たちの運動の未来を築くという約束だ」
イルバナ・スマイロビッチ女性委員会共同議長が、平等は団結なしでは達成できないと強調した。
「強さと連帯を示さなければならない」と彼女は述べ、包括的な組合と職場を生み出すために男女が団結するよう求めた。
マリー・ニルソン・インダストリオール会長が、心からの省察によって基調を打ち出し、シドニーに発つ前日に3人目の孫(女の子)が生まれたと述べた。
「彼女は大きくなったら、祖母が自分のバリケードになっていたことを知るだろう」
彼女の言葉は、その日の雰囲気をうまく捉えていた――勇気とつながり、そして将来世代のために公正で平等な世界を求める闘いである。
オーストラリアは関連産業でジェンダー平等を求める闘いを先導
この精力的なセッションでは、鉱業・エネルギー労組(MEU)のジャッキー・ウッズが司会を務め、建設、鉱業、製造業、医療および繊維部門の女性が参加。根強い障害を報告するだけでなく、それを克服するための組合組織化の力についても話し合った。
木材供給・繊維労組(TFTU)のジェニー・クルシェルが、女性がどこまで来たか、どれだけの仕事が残っているかを強調した。
「賃金平等は私たちの偉業の1つだが、まだ格差が見られる。公正労働委員会の支援を受けて、使用者は現在、平等を可能にする変革に対応し始めている」
「私の職場では70人中10人が女性だ」とMEUのクレア・ベイリーが述べた。「組合加入を常態にする必要があり、この部門に女性がいることを常態にする必要がある」
オーストラリア労組(AWU)のステーシー・シンナールが、自身の指導者への道筋を熟考した。
「私の組合では、私のジェンダーは重要ではないが、取るに足りないものでもない。私の存在に困惑する男性がまだいる。そのような状況を利用して女性を擁護している」
木材供給・繊維労組(TFTU)のグエット・グエンは、組合加入で人生が変わった。
「組合のおかげで自分の権利に気づき、それ以来、労働者を代表しようと決意している」
オーストラリア製造労組(AMWU)のルネ・ポートランドが、具体的な進展を誇りに思っていると述べた。
「PPEに関する説明会を開き、女性が教育を受けて知識を身につけるようにしている。当組合はそれを実現している」
パネリストたちは共同で、粘り強さによる進展、メンターシップ、認知度、男性優位の産業における平等への集団的要求を生き生きと表現した。見通しは明るく、クリーンエネルギーとSTEMで新たなチャンスが生まれている。
「女性を念頭に置いて明日の方針が立案されるようにしなければならない」と1人の発言者が述べた。
組織化で公正な未来を――権限、公正および転換
力強い世代間セッションに、インダストリオールの女性副会長であるクリスティアーネ・ベナー、ロクサーヌ・ブラウン、ローズ・オマモならびにルシネイデ・バルジョンが参加し、ジェンダー平等がどのように仕事の未来を形成しなければならないかに検討を加えた。
ロクサーヌ・ブラウンUSW副会長がステージから聴衆に力を与えた。
「1、2、3、パワー! パワーを感じるか?」と彼女は大声で叫び、数百人がその言葉を繰り返した。「心の中のその感情、それを覚えておく必要がある。それこそグローバルな労働運動の目的であり、インダストリオールにあるものだ」
彼女の言葉は、この日の鼓動を捉えていた――女性が組織化すれば、職場が変わるだけでなく世界が変わるという信念である。
副会長たちは、公正な移行、デジタル化、公正な未来の基礎としての平等について語った。
ドイツで女性として初めて主要産別組合の指導者となったクリスティアーネ・ベナーIGメタル会長が、組織文化の変革について話した。
「ジェンダー平等は女性の問題ではなく、民主主義の問題だ」と彼女は述べた。「力を共有すれば、私たちが受け継いだ世界ではなく、私たちが生きている世界を反映する、より強力な組合を構築できる」
ケニアAUKMのローズ・オマモが、男女労働者を団結させる共闘を参加者に思い出させた。
「ともに闘い、ともに勝利する。女性が立ち上がれば、組合も立ち上がる」と彼女は述べた。「平等は力を奪うものではなく、力を結集するものだ」
そして、ブラジルCNQ-CUTのルシネイデ・バルジョンが、すべての女性に及ぶ代表の重要性を力説した。
「ブラジルでは、女性の委員会や集団によって、すべての女性、アフリカ系ブラジル人、先住民および労働者階級に耳目が集まるようにしている。それが変革を実現する方法だ」
副会長たちは、ジェンダーを変革する組合、女性を含むだけでなく女性に主導権も与える組合を要求した。「私たちは強い女性に依存している」と1人のパネリストは述べた。
「公正な未来は、それが平等である場合のみ実現可能だ」
ジェンダー主流化と安全なサプライチェーンの構築
このセッションでは、日本最大の産別組合UAゼンセンの永島智子会長の司会で、ジェンダー平等をグローバル・サプライチェーンと産業移行の基礎とする方法を探った。永島会長は繊維、化学、エネルギーおよびサービス部門の労働者190万人を代表して、ジェンダー主流化は平等のためだけでなく、持続可能な産業と公正な経済の構築にも欠かせないと強調した。
このセッションは、進展のモデルとして繊維・衣料・製靴・皮革部門を強調した。
パキスタンHBWWFのゼフラ・カーンとインダストリオール部門担当部長のクリスティーナ・ハジャゴス=クローゼンが、平等の権利、職場の安全、ジェンダーに基づく暴力とハラスメント(GBVH)のゼロ容認を促進するTGSLジェンダー方針を発表した。この方針は、集団行動によって原則を慣行に変え、最も脆弱な層を保護するとともに、生産や交渉にあたって女性が主導権を握るための道を作れるようにするにはどうすればよいかを示している。
トルコÖz İplik İşのフルヤ・ピナル・ウズカンとスウェーデンIFメタルのハイディ・ランピネンが、H&Mとのグローバル枠組み協定(GFA)が、GBVHと闘い、労使関係を強化し、100万人を超えるサプライチェーン労働者の安全な職場を確保するうえで、強力な手段となっていることを報告した。
会場からの介入で、この活動を全部門に広げなければならないことが強調された。インドネシアFSPMIのプリハナニ・ボエナディ電子部門共同議長が、参加者に警戒を怠らないよう促した。「GBVHと闘い続けなければならない。すべての部門がTGSL方針と足並みをそろえ、その教訓を生かすべきだ」
フランスCFE-CGC Métallurgieのコリン・シェウィンが、女性労働者がたびたび目に見えない圧力にさらされていることを強調した。
「女性は重い精神的負担を強いられており、キャリアを伸ばす能力を制限されている。本当の平等がほしければ、この負担の軽減に取り組まなければならない」
ここでの議論ではっきりしたのは、原料から小売に至るバリューチェーンのすべての部分にジェンダー平等を組み込み、公正な移行と人権デュー・ディリジェンス、労使関係を調和させて、万人に公正、尊厳、安全を提供するようにしなければならないということである。
組合の力を構築するための女性のメンタリング
このメンタリングセッションは、女性大会で最も刺激になる瞬間の1つとして際立ち、世代や大陸を超えた連帯がどのように真の労働組合の力に変わり得るかの実例を示した。
このセッションは、2019年の女性大会で初めて設定されたビジョンを反映していた。すなわち、女性がメンターシップを通して成長すれば、彼女らとともに運動全体も成長するということである。
セッションではメンターとメンティーが力強く証言し、指導と根気、信頼によって自信をリーダーシップに変えられることを説明した。
ペルーのウェンディー・キャロル・カルバハル・レオンが、自分の権利や労働組合主義の意味を理解するうえでメンターシップがどう役立ったかを共有した。
「私は組合加入の意味を理解するようになった。メンターシップは、90分の授乳時間の達成のような権利を認識するのに役立ち、権利を求めて立ち上がる力を与えてくれた」
ガーナのアグネス・アマ・アガマスが、この経験によって労働運動における自身の役割をどのように再定義したかを説明した。
「目標達成の方法を学んだ。私は今、所属組合で最も若い女性であり、これは若い男女に等しく道を開いている。このプログラムのおかげで、私の状況は大きく変わった」
ガーナのジョイス・マク・アッピアが、このプロセスの互恵的性質を取り上げた。
「メンターになったことは私に骨組みを与えてくれた。自分がメンティーたちにとって、すべてを満たす存在にはなれないことを悟った。辛抱強く話を聞くことが重要だ。メンターとして、私自身も指導を受けている」
米IAMAWのニコール・フィアーズとディー・コルバートが、同労組のLEADS指導教育プログラムの原則を発表した。
「雇用に関する公正と地域社会へのサービスの原則に根差している」
「ジェンダー平等は労働運動を強化する。私たちはトーチを渡すだけでなく、互いに照らし合っている」
ここでの議論は、メンターシップは慈善行為ではなく集団的な権利拡大戦略であることを再確認した。メンターシップは女性が先導する道を開き、世代間の橋渡しをして、個人の成長を組織の強さに変える。
共通の目的を掲げる運動
女性大会の最後に、インダストリオールの2025〜2029年ジェンダー平等ロードマップ草案が発表された。この案は明確な優先事項を提示している。すなわち、女性の参加とリーダーシップの拡大、同盟者としての男性の関与、賃金平等の達成、無給介護労働への対処、ジェンダーに基づく暴力とハラスメントの根絶、人権デュー・ディリジェンスと公正な移行プロセスへのジェンダー・トランスフォーマティブ・アプローチの統合である。
このロードマップは、具体的な手順や意識向上、訓練、ツールや資料の開発、同盟の構築、部門の垣根を越えたフォローアップの強化を概説しており、次の女性委員会がインダストリオールの組織機構や方針、アクション・プランにジェンダー平等を体系的に埋め込む基礎となる。
イルバナ・スマイロビッチが、締めくくりの言葉で感情と感謝の念を込めて語り、登壇者全員の勇気と強い信念を認めた。この日の力強い交流を振り返り、強さと脆さの両方が現れた場だったと表現した。流された涙は弱さの表れではなく、共感と共通の目的の表れだったと彼女は述べた。女性は他者を優先することが多いが、力を取り戻し、主導権を握り、他者を前方に牽引し続けるためには、自分自身を優先しなければならないときもある。