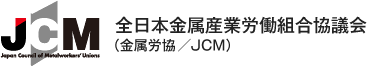|
− 経済の「反グローバリズム的な組合主張」の拡大 −
 |
IMF−JC事務局長
團野久茂 |
IMF労働運動において、いまアメリカを中心とする反グローバル的な主張が発展途上国を巻き込んで、世界的な広がりをみせ始めている。わたしは、IMF会議に出席する度にそんな感覚を強く憶えてしまう。こうした主張をわたしたちはどう捉えるべきなのだろうか。新年早々にしては少し重いテーマだが、考察してみたい。
わたしたちのイメージにある富(利益)は、土地を主体にした時代に形成された。人間の移動や物質の流通が活発でなかった時代、当然のことながら田畑、山林が富を生み出す生産基地であり、すべての生業はフランチャイズをもったうえで活動をしていた。
こうした時代には、富者は必ず土地もちであり権力者でもあったわけである。中世のフランスの封建制度は、国王が家臣に土地を与え、土地を媒介とする領主と家臣の典型的な関係であった。イギリスでも上流階級は土地の大所有者であり、日本においても「大名」はそうであった。土地の広さは戦力を意味していたのである。この時代の人間は土地を富の源泉と考えていたのである。土地本位制度が経済の中心をなしていた日本は、もしかしたらバブル崩壊までそうだったのかもしれない。
産業革命は、土地によらない富を生み出したという点でまさに革命であった。イギリスはその手法の開発者として莫大な創業者利益を獲得したのである。現在、わたしたちが富を考える場合も、やはり土地の生む利益と商品の生む利益が中心になるが、商品の生み出す利益が、あらゆる価値観を逆転させたことを認識しておく必要がある。商品を生むのは市場経済であり、市場経済にこそ金の卵を生み出す活力があることを忘れてはならないのではないだろうか。
日本においても、織田信長や豊臣秀吉といった昔の権力者は、土地だけでは富が十分でなく、商品支配が重要であることを熟知していたのである。楽市楽座の断行はその表れであるし、秀吉はさらに大阪を商業の中心地に仕立て上げ、200万石という直轄地しか持たないにも関わらず、その経済力の大きさは商業による利益に裏打ちされたものだったといえる。それに反して徳川政権は、700万石の領地を背景とした農業政権であったと云える。
もう一つわたしたちが参考にすべき歴史的な大事件がある。それは1929年10月に、ニューヨーク株式市場の大暴落で始まり、たちまち世界中を巻き込んだ大恐慌である。この恐慌の原因は、ある本によれば「ホーリー・スムート関税法」のアメリカ議会への提出だといわれている。第一次大戦中に農作物がヨーロッパに高い値段で売れたので、アメリカ農民は高額の機械を買い入れ土地を購入した。しかし、戦後はヨーロッパが農作物を購入しなくなったため、アメリカ国内の農作物価格は暴落し農業不況がおきた。そこで農民は、圧力団体として補助金と関税の引き上げを要求したのである。その当時、最も強硬な農業保護論者だったのがホーリーとスムートだったわけで、この法案は1930年に可決されている。
これはアメリカのブロック経済スタートのサインとして、世界中がたちまちこれに反応し、およそ1年間で世界の貿易量は約半分になってしまったのである。これに加えて1932年、イギリスが帝国内の関税を引き下げ、あるいは撤廃し、外国に対しては関税を引き上げるという決定を下してしまった。大恐慌は瞬く間に全世界に伝染してしまったのである。本来、農業保護のための法律であったはずが、農民はなんの利益も受けるどころか深刻な不況で大打撃を受けてしまったのである。現在、日本の2国間貿易協定のための協議において、締結の大きな障害となっているコメの自由化問題や見えざる関税障壁を考えるに当っても、よい事例になるはずである。
もう一つは、レーガノミックスである。これは所得税の大減税であるが、この政策によってアメリカの景気のみが回復しただけでない。アメリカ国民の購買力アップの恩恵をもっとも受けたのは東南アジアの諸国である。アメリカ向け製品輸出の急増は、驚異的な経済成長を生み出し、NIES、ASEAN諸国の経済的離陸を完全なものとしたのである。もちろん、こうした東南アジアの離陸を可能としたのは、多くの日本企業が現地に早くから現地に進出し、製品供給基地としての体制を備えていたことが背景にあったことは云うまでもないのである。
私はこうした歴史的経過のうえに、今日の「グローバルな市場経済の拡大」があると認識している。何もこの現象が突然に現れたのではないのである。金属産業は貿易型産業でもあり、その発展のためには自由貿易体制を堅持する必要があるが、また一方で、人・モノ・カネが国を超えて行き交う中で、その影響を受ける人々への対応も忘れてはならない。
<目次に戻る> |